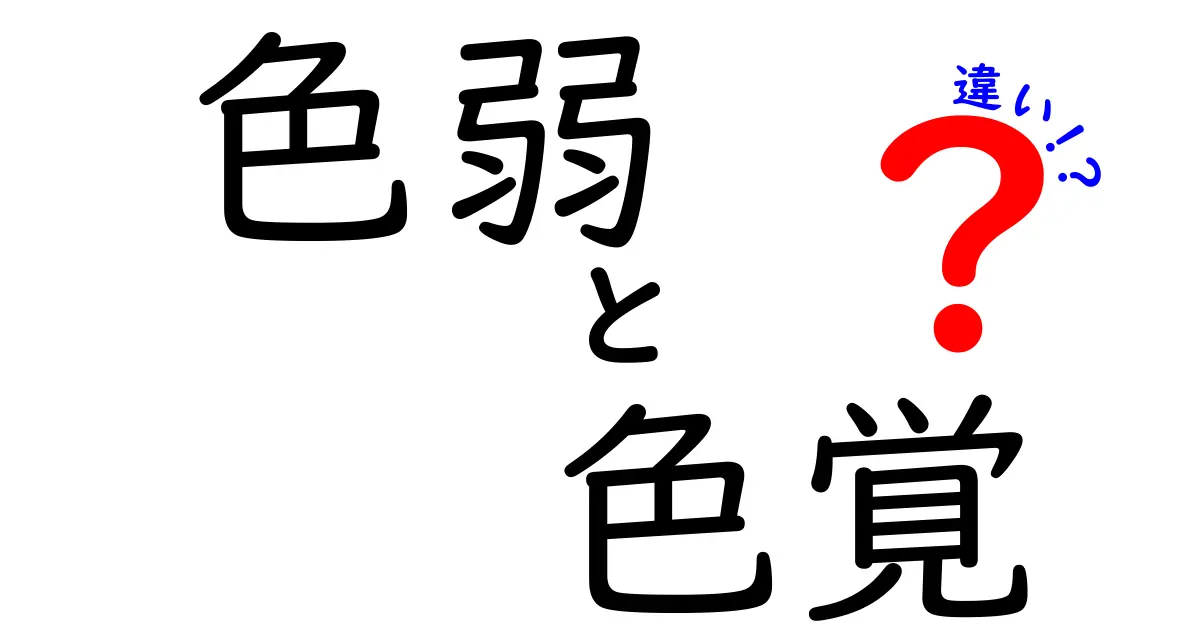

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
色弱と色覚の基本的な違いとは?
みなさんは「色弱」と「色覚」という言葉を聞いたことがありますか?
この二つは似ているようで実は意味が少し違います。色覚とは、簡単に言うと「物を見るときに感じる色の見え方」全体のことを指します。
つまり、私たちが周りの色をどのように認識しているかという感覚のことです。
一方で色弱は、「色覚の中の一部で、色を正しく感じ取れない状態」のことを指します。
例えば、赤と緑の区別がしにくい人がいますが、これが色弱です。
色弱は色覚の異常や特性の一つで、多くの場合、生まれつきのものです。
つまり、色覚は全体の色の見え方や感覚のこと、色弱はその中で色を正しく認識できない状態のことと考えてください。
色弱の種類と原因について詳しく知ろう
色弱にはどんな種類があるのか、そしてなぜ色弱になるのかについて説明していきます。
まず、色弱の主な種類には赤緑色弱があります。これは、赤色と緑色を判別しにくい状態のことです。色弱の中で最も多く、特に男性に多く見られます。
もう一つは青黄色弱で、青色と黄色が判別しにくい状態です。こちらは赤緑色弱に比べて少ないですが、存在します。
また先天性(生まれつき)と後天性(後から起こる)の違いも大切です。多くの色弱は遺伝による先天性のものですが、病気やけが、加齢によって起こる後天性の色覚異常もあります。
原因としては、目の網膜にある色を感じる細胞「錐体細胞」の働きがうまくいかないことが挙げられます。
網膜には赤・緑・青の光を感じる錐体細胞があり、それらが協力して色を見分けていますが、どれか一つの働きが弱かったり欠けたりすると色弱になります。
色弱と色覚の違いを表でわかりやすくまとめてみた
| ポイント | 色覚 | 色弱 |
|---|---|---|
| 意味 | 色を感じる能力や感覚全般 | 色覚の異常の一つで、色が正しく見えない状態 |
| 範囲 | 広い(色の見え方全体) | 限定的(特定の色が見にくい) |
| 原因 | 正常な場合と異常な場合あり | 錐体細胞の不具合や遺伝、病気など |
| 主な種類 | 色の全体的感覚 | 赤緑色弱、青黄色弱など |
| 一般的な割合 | 全員持っている能力 | 男性の約8%、女性の約0.5%に多い |
色弱でも問題なく生活できる工夫とは?
色弱だと一部の色が見にくくて困りそうに思いますが、実は多くの色弱の人は普段の生活でそれほど困りません。
例えば、信号や標識には形や明るさの違いもあるので色だけで判断していません。
また、最近は色弱の人に配慮したデザインやアプリ、メガネなどの補助アイテムも増えています。
デジタルの世界でも、色だけに頼らず形やパターンで区別できる設計がされることが増え、多くの色弱の人が快適に過ごせるようになっています。
大切なのは色弱でも多様な色の見え方があることを理解し、配慮することです。
それにより、みんなが暮らしやすい社会になります。
「色覚」という言葉は、単に色が見える能力だけでなく、脳が色をどう感じて認識するかをも含んでいるんですよ。実は同じ色でも、人によって脳内でのイメージが少しずつ違います。だから絵画やデザインの世界では、“色の感じ方”を考えることがとても重要なんです。色弱の方は特に特定の色が見えにくいことから、色の感覚に違いがありますが、逆にその独特な感じ方が芸術やデザインの新しい魅力を生むこともあるんです。
前の記事: « 知っておきたい!色彩設計と色指定の違いとは?わかりやすく解説





















