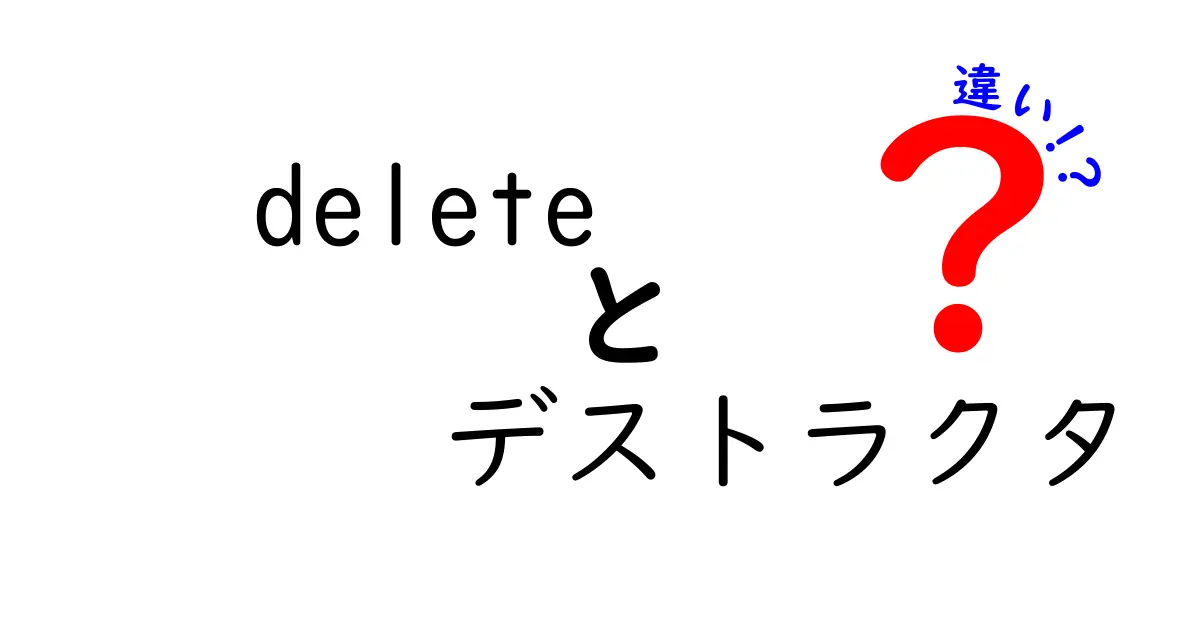

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
「delete」とデストラクタの違いとは?基礎から解説
プログラミング言語C++を学び始めると、よく耳にするのが「delete」と「デストラクタ」という言葉です。どちらもメモリ管理に関係していますが、その役割や使い方には大きな違いがあります。
まず、「delete」はC++で動的に確保したメモリを解放するための演算子です。C++では「new」を使ってメモリを確保しますが、使い終わったら必ず「delete」で解放しないとメモリリーク(使ったメモリが解放されず無駄になる)が発生します。
一方、デストラクタはクラスのオブジェクトが破棄される時に自動的に呼ばれる関数のことです。デストラクタは「~(チルダ)」で表され、主にオブジェクト内部のデータの後始末を行います。つまり、deleteはメモリの解放を命令するもので、デストラクタはオブジェクトの片付けを自動で行う仕組みと言えます。
deleteとデストラクタの役割の違いを理解しよう
もう少し具体的に見てみましょう。
「delete」はポインタが指すメモリ領域を解放します。例えば、newで作成したオブジェクトをdeleteで削除すると、そのオブジェクトのデストラクタが自動的に呼ばれ、オブジェクトの片付けをしてからメモリの解放が行われます。
つまり、deleteを使うことで「デストラクタの呼び出し」と「メモリ解放」の両方を実現しているのです。
一方、デストラクタ自体はオブジェクトの寿命が終了した際に自動で実行され、その中では必要に応じてリソースの解放や終了処理を行いますが、デストラクタはメモリ解放を直接するものではありません。メモリはdeleteやdelete[]が解放するのがC++のルールです。
deleteとデストラクタの違いを表でまとめてみよう
まとめ:どう使い分けるべきか?
C++では、動的に確保したメモリは必ず「delete」で解放する必要があります。その際に、deleteは自動的に対象オブジェクトのデストラクタを呼び出します。
デストラクタはオブジェクトの片付け処理(ファイルのクローズやメモリ以外のリソース開放など)を記述し、deleteはメモリ解放を担うと理解しましょう。
つまり、deleteとデストラクタは仲間であり、「deleteが呼ばれてデストラクタが実行される」という順番で動くため、両方の役割を知って適切に使うことが大切です。
プログラミングを学ぶ皆さんは、この違いを理解し、C++の正しいメモリ管理を身につけましょう!
今回は「デストラクタ」について少し掘り下げてみましょう。デストラクタは日本語で言うと「破壊者」や「破壊関数」みたいな名前でかなり強烈ですよね。でも、実はとても優しい役割なんです。オブジェクトが不要になったとき、勝手に片付けてくれる頼りになる存在なんです。ファイルを閉じたり、他のリソースを整理してくれたりと、私たちプログラマの肩の荷を下ろしてくれています。ちなみに、デストラクタは明示的に呼び出すことはめったにありません。まるで真夏のクーラーのように、必要なときに自然と働いてくれるイメージです。だから名前は怖いけど、中身はとても優しいんですよね。
前の記事: « 初心者でもわかる!DFDとUMLの違いを徹底比較解説





















