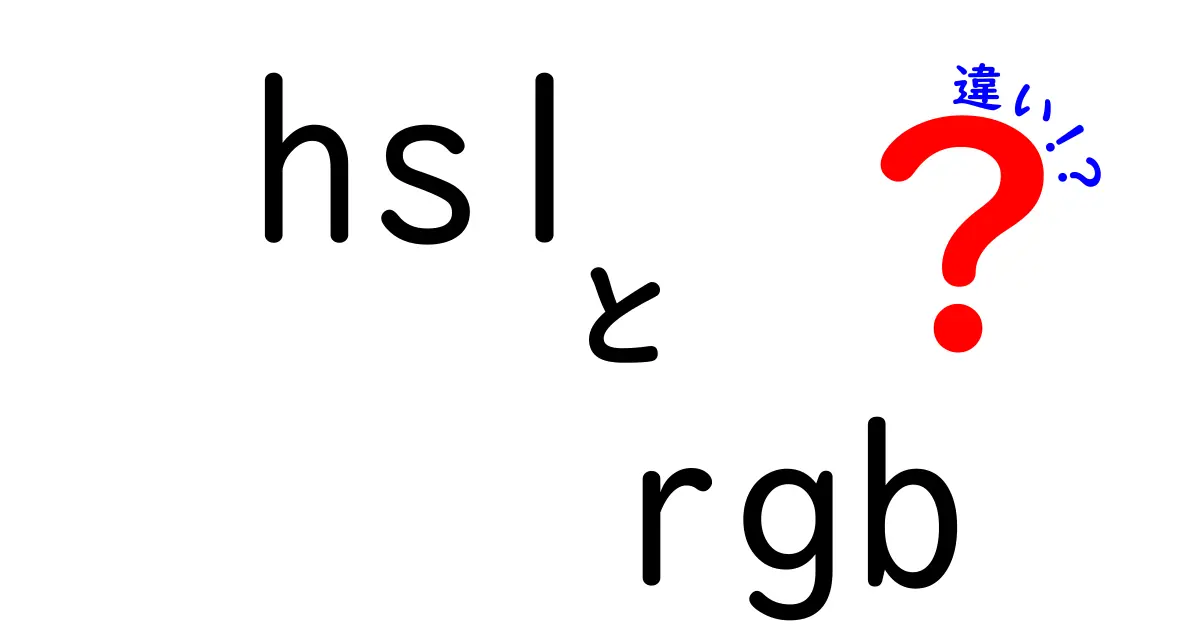

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
HSLとRGBって何?基本の色の表現方法を理解しよう
色をコンピューターで表現する方法はいくつもありますが、HSLとRGBは特に有名な2つの表現方法です。
それぞれがどんなものか知ることで、デザインや写真編集、プログラミングでの色指定がぐんとわかりやすくなります。
まずはそれぞれの基本を押さえましょう。
RGBとは?
RGBは、赤(Red)・緑(Green)・青(Blue)の3色の光の三原色を使った表現方法です。
それぞれの色の強さを0〜255の数値で表し、それらを組み合わせて様々な色が作られます。
例えば、RGB(255,0,0)なら純粋な赤、RGB(0,0,255)なら純粋な青です。
テレビやパソコンの画面など光を使った色表示に便利です。
HSLとは?
一方、HSLは色を色相(Hue)、彩度(Saturation)、明度(Lightness)の3つに分けて表現します。
色相は0〜360度の角度で色を指定し、彩度は色の鮮やかさ(0〜100%)、明度は明るさ(0〜100%)を示します。
HSLは人間の見た目に近い感覚で色を調整しやすいため、デザインの際に重宝されています。
HSLとRGBの違いを表で比較してみよう
違いをわかりやすく整理すると、下の表のようになります。
| 特徴 | RGB | HSL |
|---|---|---|
| 成分 | 赤・緑・青の光の強さ | 色相・彩度・明度 |
| 値の範囲 | 0~255(各色) | 色相:0~360度、彩度と明度:0~100% |
| 使いどころ | ディスプレイ画面の色や光の表現 | 色の見た目調整やデザインカラーの指定 |
| 特徴 | 光の三原色で混ぜる方式(加法混色) | 人間の色感覚に合いやすい調整方法 |
どちらを使うべき?場面に応じた選び方
RGBは光の三原色で直接色を作るので、デジタル画面の色指定に適しています。
一方、HSLは色の見た目に合わせて調整しやすいのが特徴。
色相や彩度を直感的に増減させたいときや、色の明るさを変えたい時に便利です。
たとえば、デザインやイラストの彩度や明度調整、カラーピッカーのツールでよく使われます。
また、プログラミングで色を扱うときには、背後でHSLとRGBの変換がよく行われています。
これは、表現に応じて最適な色の計算が必要なためです。
まとめ:HSLとRGBを使い分けて色を自由自在に操ろう
まとめると、RGBは機械的・直接的に色を指定する方法、HSLは人間の感覚に基づいて色を調整しやすい方法です。
普段のデジタル作業ではRGBが基本ですが、デザイン調整や色のイメージをつかむならHSLがとても役立ちます。
この2つを理解し、必要に応じて使い分けることで、色の表現力がぐっと広がります。
ぜひ色の世界を楽しんでみてくださいね!
HSLの「色相(Hue)」は0〜360度で色を表し、色相環という円形の色の並びをイメージするとわかりやすいです。
例えば0度は赤、120度は緑、240度は青といった具合に、角度で色を指定できるのでデザインの際に色の調整が直感的に行えます。
この色相の角度を変えることで、似ている色や反対の色(補色)も簡単に選べて、カラーホイールというツールを使うともっと楽しく色の調和を考えられますよ。
前の記事: « 【初心者必見】RGBとカラーコードの違いをわかりやすく解説!
次の記事: コントラストと明度の違いをわかりやすく解説!デザイン初心者必見 »





















