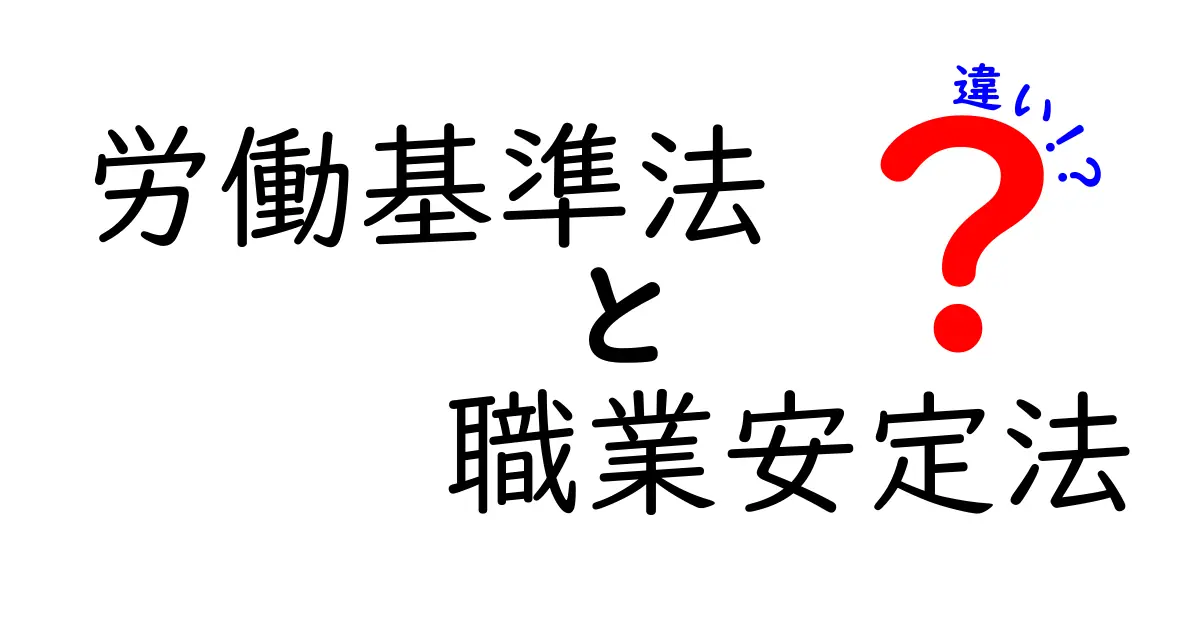

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
労働基準法とは何か?
労働基準法とは、働く人の「労働条件」を守るために作られた法律です。
例えば、働く時間の長さや休みの日、給料の最低額、そして安全に働くためのルールなどを定めています。
この法律は日本の会社で働くすべての人に関係があり、会社が守らなければならない最低限のルールを決めています。
たとえば、労働基準法により1日の勤務時間は原則8時間、1週間で40時間以内と決められています。また、残業は禁止されているわけではなく、一定の条件のもとで認められています。
賃金の支払いは毎月1回以上、一定期日に行うこと、年次有給休暇の取得などもこの法律によって保障されています。
このように、労働基準法は働く人の働きやすさと健康を守るために必要なルールを提供しています。
職業安定法とは何か?
職業安定法は、働きたい人がスムーズに仕事を見つけられるようにするための法律です。
この法律は、ハローワークや人材紹介会社のような「職業紹介事業者」のルールを決めています。
つまり、求人と求職をつなぐ仕組みを安全かつ公平に運営するための法律です。
職業安定法の主な目的は、労働者が適切な仕事を探せるように支援し、また企業には適切な人材を紹介することを促進することです。
一方で、不当な紹介料の要求や不正な雇用斡旋、虚偽の求人広告といったトラブルを防ぐ役割も持っています。
この法律があるおかげで、働く人も企業も信用できる求人・求職の場を利用でき、安心して就職活動が行えます。
労働基準法と職業安定法の違いを表で比較!
まとめ:働く人を守る2つの法律の役割
労働基準法は、働く人の働き方や環境を守るための法律であり、職業安定法は仕事を見つけるときのルールや支援のための法律と覚えるとわかりやすいです。
両方とも働く人と企業の間のトラブルを防ぎ、安心して働ける社会を作るために欠かせない法律です。
これから働くことを考えるときは、この2つの法律がどんなことを守ってくれているかを知っておくと安心ですね。
「職業安定法」って聞くと、単に仕事を見つけるための法律と思いがちですが、実は求人や求職の間で起きるトラブルを防ぐ役割も大きいんです。
例えば、違法な手数料を取られたり、嘘の求人情報でだまされたりしないようにルールが決まっているんですよ。
だからハローワークや人材紹介会社を利用するときは、この法律が守ってくれているから安心というわけです。
ちょっとした法律の存在が、みんなの働きやすさを支えているんですよね。





















