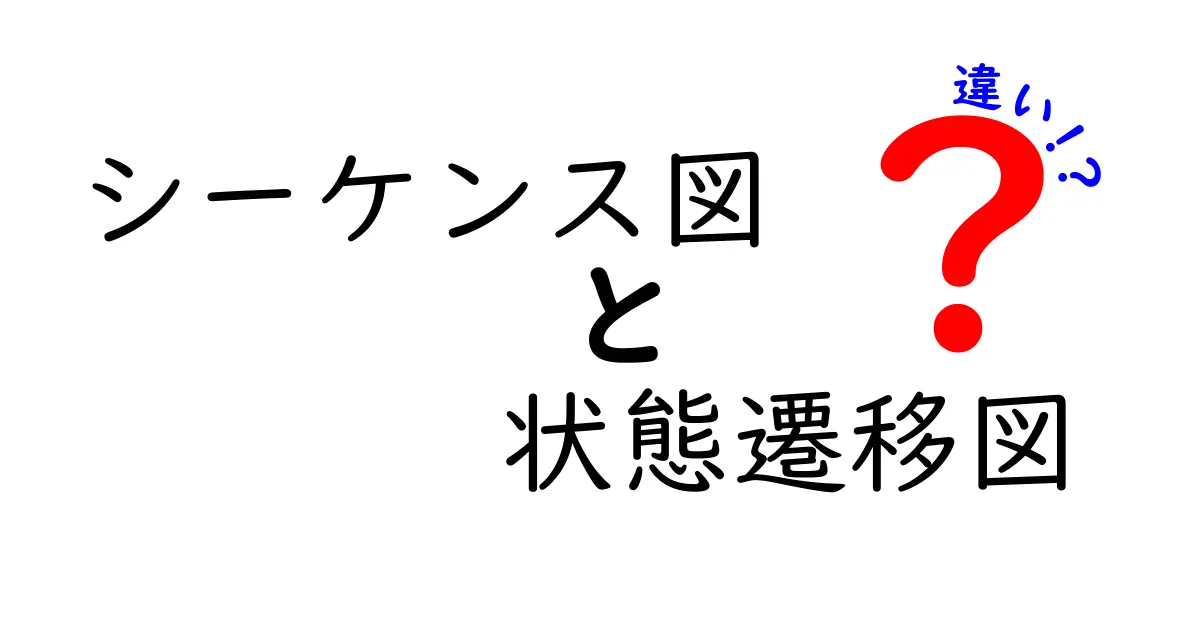

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
シーケンス図とは?基本をわかりやすく説明
シーケンス図は、システムやプログラム内での「やり取りの流れ」を表す図です。たとえば、スマホのアプリでボタンを押したときに、どんな順番でデータが動くのかを時系列で示します。
シーケンス図は、複数の「役割」や「オブジェクト」が登場し、それぞれのやりとりが矢印で表されます。時間の流れは上から下へ進み、メッセージや関数の呼び出しがどのように進むかを見ることができます。
強調したいのは、シーケンス図は“時間的な順番”に重点を置いていることです。したがって、誰が何をいつやるのかを理解しやすく、システムの動作を追うのに役立ちます。
たとえば、ネットショッピングの注文処理では、「ユーザーが注文する」→「支払い処理へ連絡」→「配送手配」など、順序が大切ですよね。こうした順番を表現するのにシーケンス図が便利です。
状態遷移図とは?その特徴と使い方
一方、状態遷移図は、システムやものが取る「状態の変化」を表します。状態とは「ある時点での状態や状況」を指します。
たとえば、交通信号機なら「赤」「黄色」「青」という状態があり、一定のルールに従って次の状態へと移り変わります。状態遷移図は、こうした「状態」と「状態の移り変わり(遷移)」を丸や矢印で表します。
こちらは、シーケンス図と違い時間の流れよりも、「状態の変化のルール」が重要です。条件に応じて次の状態がどう決まるのか、どんなきっかけで変わるのかを理解するのに役立ちます。
ゲームのキャラクターの「立っている」「歩いている」「ジャンプしている」といった動作の切り替えも状態遷移図で表せます。状態遷移図を使うと、複雑な動作や条件の整理がしやすくなります。
シーケンス図と状態遷移図の違いを表でまとめてみました
| 項目 | シーケンス図 | 状態遷移図 |
|---|---|---|
| 目的 | オブジェクト間のメッセージのやりとりや処理の順序を表す | 対象の状態とその状態間の遷移を表す |
| 表現のポイント | 時間の流れに沿ったやり取りの順序が中心 | 状態と状態の変化ルールが中心 |
| 図の要素 | オブジェクト(役割)、メッセージ、タイムライン | 状態、遷移(矢印)、イベントや条件 |
| 使う場面 | システムやプログラムの処理手順の確認や設計 | 機器の動作パターンや複雑な状態管理をモデル化する時 |
| 例 | 注文処理の手続きの流れ | ゲームのキャラクターの動作ステート管理 |
まとめ
シーケンス図と状態遷移図は、どちらもシステム設計で使われますが、注目している視点が違います。
シーケンス図は「時間の流れややり取りの順番」を、状態遷移図は「状態とその変化ルール」を理解するためのツールです。
理解するコツは、「処理の流れを追いたいならシーケンス図」、「状態の切り替えを整理したいなら状態遷移図」という目的で使い分けることです。
どちらも中学生でも学べる基本的な表現なので、ITやプログラミングを学ぶさいにしっかり把握しておくと役立ちますよ。
シーケンス図の面白いところは、時間の流れが見える化されている点です。これはプログラムがどんな順番で動くかを理解したいときに特に役立ちます。
例えば友達と会話するときを想像してみてください。誰が話して、誰が返事して、次は誰の番か、話の流れがはっきりわかると会話がスムーズですよね。シーケンス図もシステム内の“会話”を見える化するようなものなんです。
こんな風に考えると、シーケンス図は単なる図ではなく、プログラムの動きを追体験できる魔法の地図のように感じられるかもしれませんね。
前の記事: « UI設計と画面設計の違いとは?初心者でもわかる分かりやすい解説





















