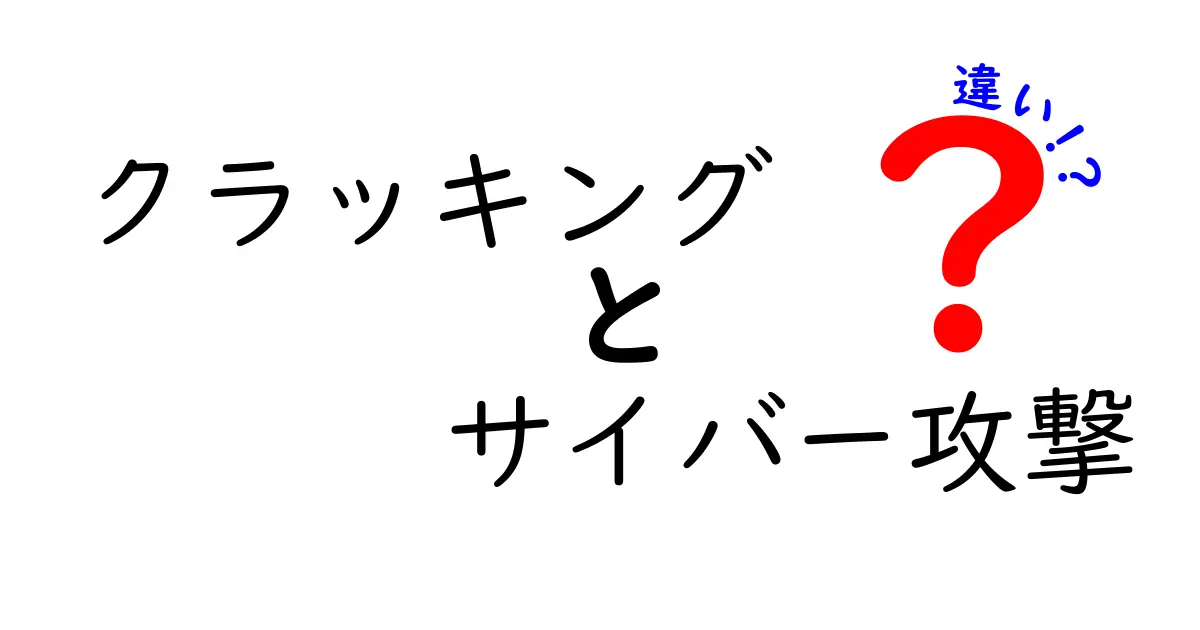

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クラッキングとは何か?
クラッキングとは、コンピュータやネットワークのシステムに不正に侵入し、権限を奪ったりシステムを破壊したりする行為のことを指します。いわば、悪意のあるハッキングの一種です。クラッキングは昔から使われる言葉で、その行為自体は法律で禁止されている不正アクセスにあたります。
クラッキングは、対象のシステムの脆弱性を見つけて侵入することが多く、例えばパスワードの解析やセキュリティの穴を利用します。目的は個人情報の盗取、システムの破壊、金銭目的の詐欺など多岐にわたります。
このようにクラッキングは特定のシステムやネットワークに対する攻撃を指す用語として使われています。
サイバー攻撃とは?
サイバー攻撃とは、インターネットやネットワークを使って電子機器やシステム、サービスに悪影響を与える攻撃全般のことを言います。
サイバー攻撃は多くの形態があり、マルウェアの感染、DDoS攻撃、フィッシング詐欺、データの改ざんなどが含まれます。
つまり、サイバー攻撃はクラッキングを含むもっと広い意味の用語です。攻撃対象もシステムだけでなくウェブサービスやインフラ、個人や企業のデータにも及びます。
また、サイバー攻撃は国家レベルのサイバー戦争や、犯罪集団による金銭目的の攻撃、ハクティビズム(政治的・社会的メッセージを伝える攻撃)など様々な背景や目的があります。
このようにサイバー攻撃はIT社会全体に関係する幅の広い概念であり、専門用語としてもよく使われます。
クラッキングとサイバー攻撃の違い
クラッキングとサイバー攻撃の大きな違いは、クラッキングが特に不正侵入やシステムの破壊を目的とした行為を指すのに対し、サイバー攻撃はネットワークやシステムに対する悪意のある攻撃の総称であるという点です。
以下の表で違いをまとめます。
要するに、クラッキングはサイバー攻撃の中の一つの種類と考えるとわかりやすいです。
近年はクラッキングという言葉そのものの使用頻度はやや減ってきていて、ニュースや記事ではサイバー攻撃という広い言葉が多用される傾向にあります。
クラッキングという言葉は、昔はよく使われていましたが最近はあまり耳にしなくなりました。これは、インターネットがもっと普及してサイバー攻撃の種類が多様になったからです。昔は『クラッカー』と言われる悪意のあるハッカーが主役でしたが、今はマルウェアやDDoS攻撃など色んな攻撃があるので《サイバー攻撃》という言葉でまとめて呼ぶことが多いです。そう考えると言葉の変化もITの歴史の一部なんですね。
前の記事: « UTMとエンドポイントセキュリティの違いとは?わかりやすく解説!





















