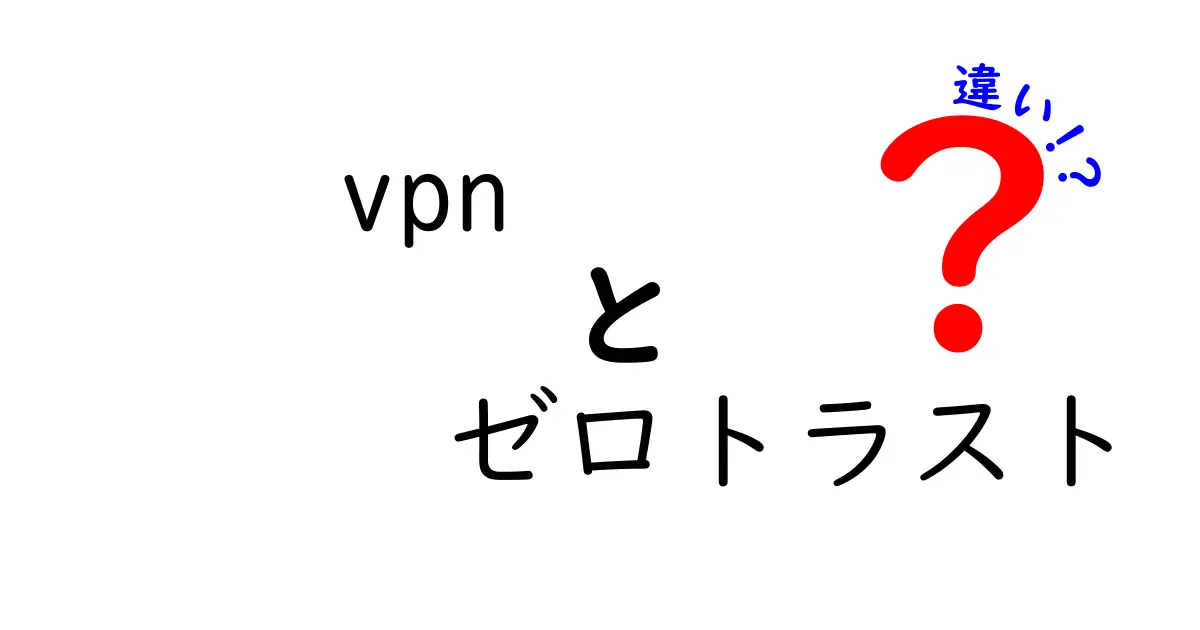

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
VPNとゼロトラストとは何か?基本を理解しよう
まずはVPN(Virtual Private Network)とゼロトラストという言葉が何を指しているのか、基本から解説します。
VPNは、インターネットを通じて安全に通信を行うための技術です。例えばカフェの無料Wi-Fiを使うとき、VPNを活用すると自分の通信内容が暗号化され、外部の人に見られにくくなります。これは“安全なトンネル”を作るイメージで、会社のネットワークに遠隔地から接続するときもよく使われます。
一方ゼロトラストは、セキュリティの考え方そのものを指します。名前の通り「何も信用しない」という姿勢で、ネットワークの内外に関わらず、あらゆるアクセスを常に疑い、細かく認証や許可を行うのです。ポイントは、社内ネットワークだからといって安心せず、すべての通信をチェックすることにあります。これにより、内部の不正や外部からの侵入リスクを低減できます。
このようにVPNは通信の安全を確保する技術であり、ゼロトラストはその安全を守るための総合的な考え方です。
VPNとゼロトラストの主な違いを表で比較
それでは、VPNとゼロトラストの違いを具体的に見ていきましょう。以下の表でポイントを整理します。
| 項目 | VPN | ゼロトラスト |
|---|---|---|
| 基本機能 | 通信経路の暗号化と安全な接続 | すべてのアクセスを検証し、信頼しない安全管理 |
| 信頼範囲 | 内部ネットワークは基本的に信頼 | 内部も外部も信頼しない |
| アクセス制御 | 接続時点で認証(例えばVPNログイン) | 継続的に認証と監視を行う |
| 導入目的 | 安全な遠隔アクセスの提供 | 全体的なネットワークセキュリティの強化 |
| 課題や制限 | 一度接続されると内部は自由に動ける場合が多い | 複雑な管理と運用コストがかかることも |
なぜ最近ゼロトラストが注目されているのか?背景を解説
昨今、ゼロトラストが多くの企業や組織で注目されている理由は大きく3つあります。
1つ目は、働き方の変化です。リモートワークや外出先からのアクセスが増え、従来の「社内ネットワーク=安全」という前提が通用しにくくなりました。VPNで社内にアクセスできても、その中での不正行為や情報漏えいのリスクは残っています。
2つ目は、サイバー攻撃の高度化です。攻撃者は内部に入り込むこともあり、内部からの脅威を防ぐためには常にアクセスを検証する必要があります。
3つ目は、システムやサービスの複雑化です。クラウドサービスやモバイル機器の利用が増えたため、一元的で細かいアクセス管理が求められています。
このような背景があり、単に安全な接続(VPN)だけでなく、多層的に安全性を高めるゼロトラストの考え方が重要視されています。
まとめ:VPNとゼロトラストを上手に活用しよう
VPNは、ネットを通じて安全に社内のネットワークへアクセスするためのトンネルのような役割を果たします。一方、ゼロトラストは「誰も信用しない」原則のもと、あらゆる通信やアクセスを厳しく管理し、セキュリティを確保する新しい考え方です。
現代ではVPNだけでは防げないサイバーリスクが多いため、ゼロトラストの考え方を取り入れることで、より安全なネット環境を作りやすくなっています。
企業や個人でも、それぞれの役割を理解し、必要に応じて使い分けることが大切です。
このブログが、VPNとゼロトラストの違いや役割を理解する助けになれば幸いです。
ゼロトラストの考え方は、「何も信用しない」ことが基本ですが、実はこれって人間の生活の中でも当てはまることがあります。例えば、知らない人にすぐに全てを話すのではなく、徐々に信頼を築いていくように、ネットワークでもすべてのアクセスを慎重にチェックしていくんです。これがサイバーセキュリティで具体的な形になると、『アクセスするたびに本人確認をし直す』という厳しさ。でもこれがあるからこそ、会社の大事な情報を守れるんですよね。ちょっと面倒だけど、その“信用しない安全”がゼロトラストの魅力なんです。
前の記事: « ZTNAとゼロトラストの違いとは?初心者にもわかりやすく解説!





















