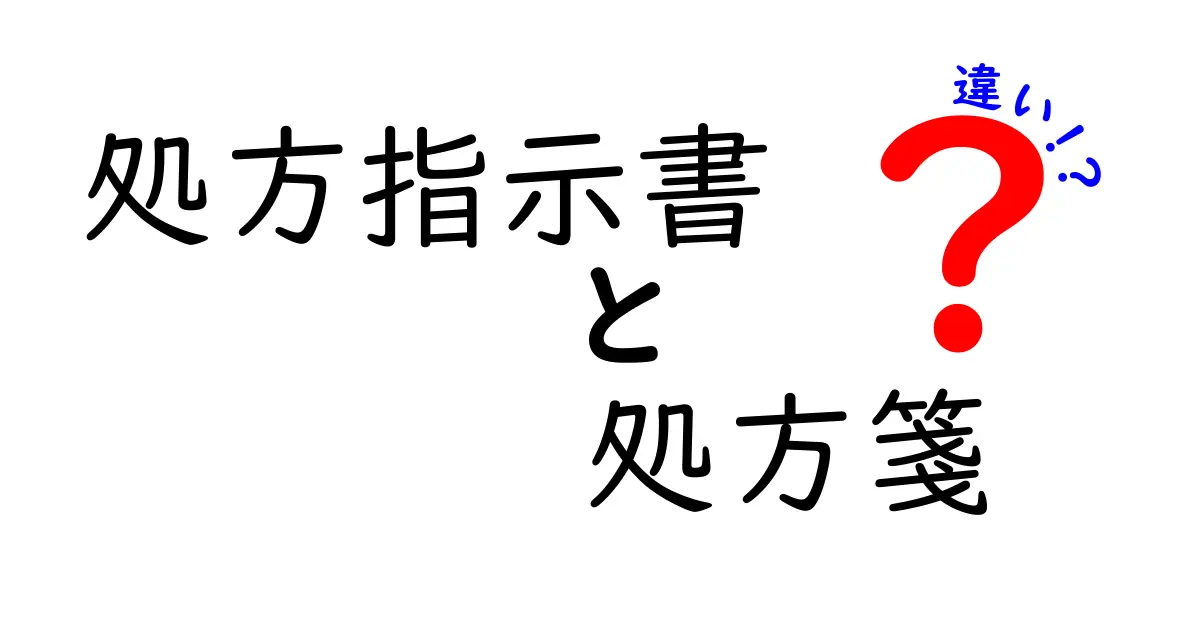

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
処方指示書と処方箋は何が違うの?基本をわかりやすく説明します
薬をもらうときに医師から渡される書類として「処方指示書」と「処方箋」がありますが、似たような言葉で混乱しやすいものです。
処方指示書は主に医師や医療機関内で使われる書類で、患者さんにどんな薬をどのように使うかを指示するためのものです。一方、処方箋は患者さんがこの書類を持って薬局に行き、薬剤師が薬を調剤するために必要な書類です。
わかりやすく言えば、処方指示書は「医師内で使う設計図」であり、処方箋は「薬局に薬をもらいに行くためのチケット」と考えるとイメージしやすいです。
実際に患者さんが薬を持ち帰るときに使うのはほぼ処方箋なので、一般的に見たり聞いたりする機会が多いのはこちらの書類です。
処方指示書と処方箋のそれぞれの役割と使い方を詳しく解説します
処方指示書は医師が患者さんに飲ませたい薬の種類や量、服用方法を書いた内部用の書類です。診察の際に医師間で共有されたり、医療機関内の看護師や薬剤師が確認する目的で使われます。
一方処方箋は、医師が患者さんに渡して薬局で薬を受け取れるようにする法的な書類です。処方箋は決まったフォーマットがあり、医師の署名や印鑑が必要で、患者さんが薬局に持っていくことで薬剤師が調剤を行います。
処方指示書は持ち運びを目的とはしておらず、薬局に直接渡すことはほとんどありません。処方箋は患者さんが薬局を訪れる際の必須アイテムなので、こちらは手元に必ず保管しておく必要があります。
処方指示書と処方箋の違いを表で整理!見分け方が一目でわかります
違いを簡単に理解していただくために、処方指示書と処方箋の特徴を以下の表でまとめました。
このように処方指示書と処方箋は役割も使われ方も大きく違います。薬をもらう際には必ず処方箋を薬局に提出することを忘れないようにしましょう。
みなさん、「処方箋」ってただの紙だと思っていませんか?実は、処方箋には医師の署名や印鑑が必要で、これがないと薬局で薬を出してもらえない重要な書類なんです。法律で決まっているので、処方箋なしで薬をもらうことは基本的にできません。だから、処方箋は単なるメモ以上の意味を持つんですよ。これを知っていると薬局での手続きもスムーズになるかもしれませんね。
前の記事: « 勉強と宿題の違いとは?意外と知らないポイントを徹底解説!





















