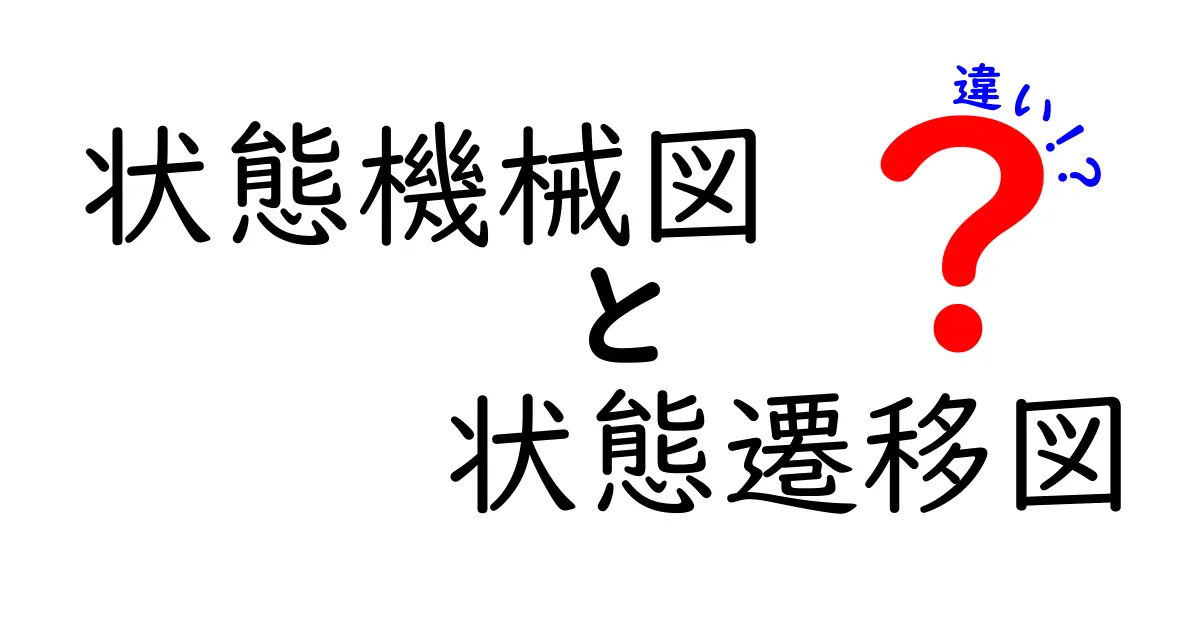

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
状態機械図と状態遷移図とは何か?
まずは状態機械図と状態遷移図という言葉の意味から説明しましょう。どちらも物事やシステムの動きを図で表す方法ですが、少しずつ特徴が違います。
状態機械図は、システムやモノの状態の変化をモデル化したものです。特に、ものがどんな状態になるか、その間にどんな出来事が起こるかを詳しく示します。一方、状態遷移図は、状態機械図の中で特に状態の移り変わり(遷移)に注目した図で、状態間の関係をわかりやすくするために使われます。
どちらもITやプログラミングの世界でよく使われ、たとえばボタンを押したときに機械がどう動くかを整理するときに利用されます。
状態機械図と状態遷移図の違いを具体的に比較!
では、実際に状態機械図と状態遷移図の違いを比べてみましょう。
一般的に言うと、状態機械図は「状態」と「アクション」の両方を表しているのに対して、状態遷移図は状態の間の遷移部分にフォーカスした図です。
以下の表で簡単に違いをまとめました。
このように、状態機械図はかなり総合的に状態と動作を追いかけているのに対して、状態遷移図は「状態遷移の流れ」に特化した図といえます。
なぜ違いがあるのか?それぞれのメリットと使いどころ
なぜ状態機械図と状態遷移図という少し違う図を使い分けるのでしょうか?それは、利用目的により強調したい部分が違うからです。
状態機械図のメリットは、システム全体の状態変化を整理できることにあります。これにより、設計者は全体像を理解しやすくなります。一方で詳しすぎて複雑になることもあります。
状態遷移図は、状態の遷移がメインなので、シンプルに動作の流れを把握したい場合に適しています。動きの確認やバグ探しにも便利ですね。
つまり、システム全体の動きをつかみたいなら状態機械図、特定の動作の流れを確認したいなら状態遷移図と使い分けるのが賢い方法です。
状態遷移図の中でも面白いポイントは「イベント」がどのように状態を変えるかの仕組みです。例えばエレベーターの状態の場合、「ボタンを押す」というイベントが起こることで、ただの『待機中』状態から『昇降中』状態へ切り替わります。
こうしたイベントはプログラムの世界では『トリガー』とも呼ばれ、特定の条件で起こるシグナルのようなものなんです。イベントによって次の状態が決まるこの仕組みは、ゲームのキャラクターの行動やスマホアプリの動作でも活用されています。
つまり、動く物を理解したり作ったりするときに、イベントがどんな役割を果たすかを知っていると、仕組みをぐっと深く理解できるんですよ!
前の記事: « これでスッキリ!DFDと状態遷移図の違いをわかりやすく解説
次の記事: コーヒー豆は標高で味が変わる!その違いをわかりやすく解説 »





















