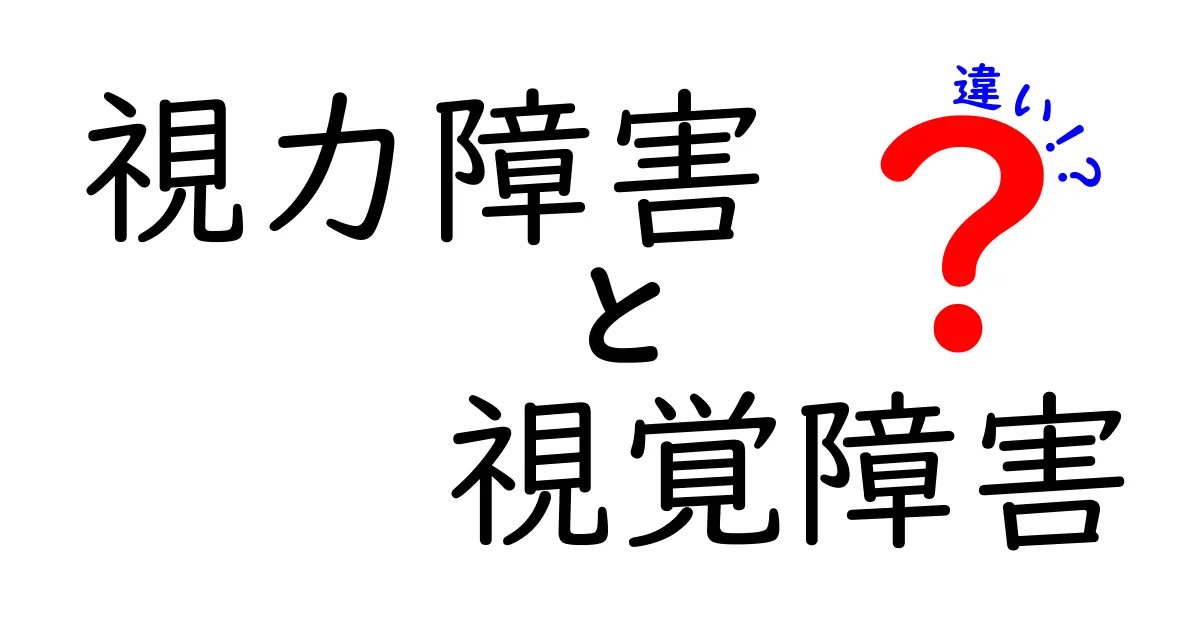

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
視力障害と視覚障害の基本的な違い
まず、視力障害と視覚障害は似ているようで違う言葉です。視力障害とは、文字通り目で見える力、つまり「視力」が低下している状態を指します。視力低下は病気やけが、加齢などが原因で起こることがあります。具体的には、視力検査で測る“見る力”が一定の基準よりも悪くなっている時、視力障害とされます。
一方、視覚障害は視力が低下しているだけでなく、視野の狭さや色の識別が難しいなど、視覚に関わるさまざまな機能が損なわれている状態を含みます。視覚障害の中には、完全に目が見えない「全盲」状態や、部分的に見えづらい「弱視」なども含まれます。
つまり、視力障害は視覚障害の一部と言えますが、視覚障害はもっと広い意味で、視力だけでなく視覚に関係するあらゆる問題を指しているのです。
具体的な区別ポイントと例
視力障害と視覚障害の違いをさらに明確にするために、ポイントを整理してみましょう。
| 区別点 | 視力障害 | 視覚障害 |
|---|---|---|
| 対象となる症状 | 視力の低下(例:裸眼で0.3以下など) | 視力低下だけでなく、視野障害、色覚異常、全盲など |
| 障害範囲 | 目で見る「視力」のみ | 視覚に関わる広い範囲の障害 |
| 医療分野での分類 | 視覚障害の一種として分類される | 視力障害も含む総称 |
| 生活上の影響 | ものがはっきり見えない | ものが見えにくい、見えない、色が区別しにくいなど多岐にわたる |
これらの違いを理解すると、医師の診断や福祉制度の利用時にも正しく区別ができるようになります。たとえば、視覚障害者手帳は視力障害だけでなく視野障害なども含めた状態で申請可能です。
視力障害と視覚障害の社会的な意味と支援について
視力障害や視覚障害を持つ人は、日常生活で困難を感じることが多いです。例えば、文字が見えにくい、色の判別がつかない、周りの物が見えづらいといった問題があります。
日本では、これらの障害を支援するためにさまざまな制度や技術が使われています。視覚障害者用の点字ブロックや音声案内システム、拡大読書器などの補助具が代表的です。また、障害者手帳を取得することで、公共交通機関の割引や税金の控除などの支援も受けられます。
こうした支援は、視覚障害全般に対するものであり、視力障害だけでなく視野の問題や色覚の問題も考慮されています。
このように視力障害は視覚障害の一部であり、広い意味での視覚障害者支援が必要なのです。周囲の理解も重要で、正しい用語の理解から始めることが社会的な支援強化につながります。
視覚障害という言葉はよく聞きますが、実は視力障害はその中の一部分でしかありません。視覚障害は視力の問題だけでなく、目で見える範囲(視野)が狭いことや色の識別が難しいことも含んでいます。つまり、視力障害だけではなく、見え方の全体的な問題を指しているんですね。これは社会の支援制度を理解する上でも大事なポイントです。知らずに『視力障害』だけで判断すると、本当の困りごとに見合った支援を受けられないこともあります。
次の記事: 虹彩と黒目の違いとは?目の不思議をわかりやすく解説! »





















