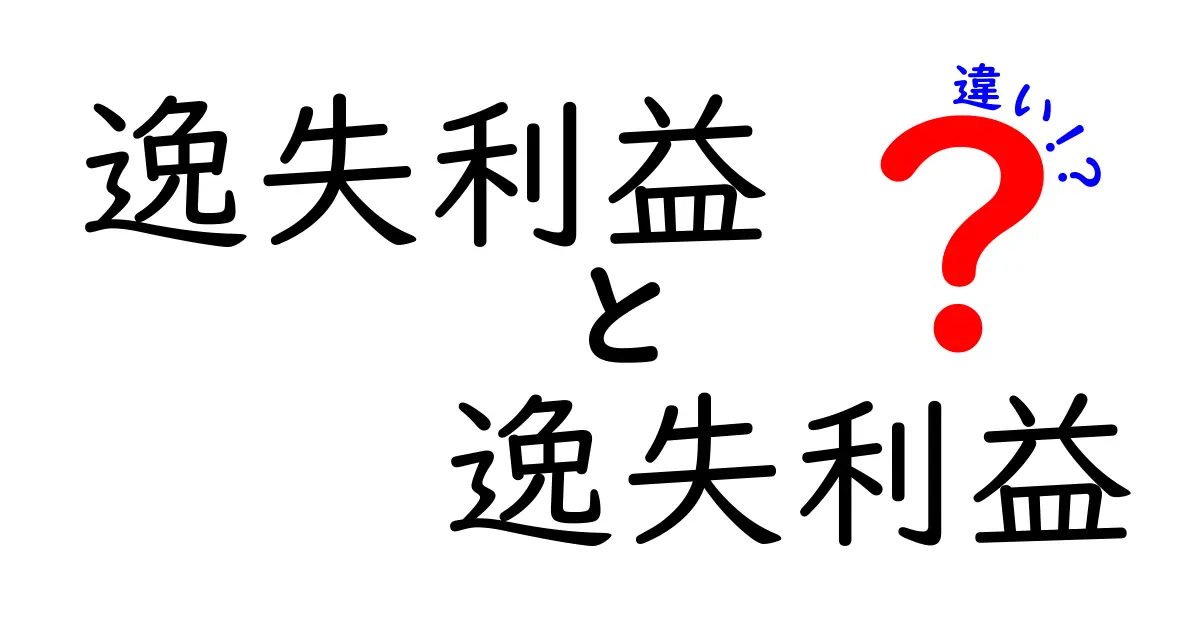

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
逸失利益とは何か?基本の理解を深めよう
まずは逸失利益(いっしつりえき)とは何かを押さえておきましょう。
簡単に言うと、事故やケガ、トラブルが原因で本来得られたはずのお金が得られなくなった損害のことです。
例えば、交通事故で働けなくなった場合、働いていれば得られた給与分のお金が逸失利益にあたります。
これは損害賠償の計算で重要な項目の一つです。
逸失利益は「失った利益」、つまり未来の収入や利益が減ってしまったことを示します。
一般にこれは、事故の後に受ける影響で本来の状態であれば得られていた収入や利益との差額を計算します。
わかりやすく言えば、「もし事故がなかったら得られていたお金」というイメージです。
ここで大切なのが、ただお金の損失だけを指すのではなく、今後の将来の利益も含まれている点です。
この概念は法律や保険では欠かせないものとして理解されています。
「逸失利益」と「逸失利益」の違いとは?同じ言葉でも意味が異なることも…?
一見同じ言葉の「逸失利益」ですが、実は文脈によって使われ方や意味合いが微妙に違うことがあります。
普通は単に損害の一種として捉えられますが、法律や実務、保険の世界では細かい取り扱いの違いもあります。
たとえば、以下のように使い分けることもあります。
- 一般的な逸失利益:事故などで減った将来の収入や利益全般を指す
- 特定分野での逸失利益:たとえば企業会計での取り扱いや税務における扱い、保険請求の詳細な計算ルールなど
また、逸失利益は「損害賠償での具体的計算方法」や「計算の基準」で変わる場合があります。
このため、一言で「逸失利益」と言っても、実は場面ごとに意味や計算方法に微妙な違いが存在すると覚えておくと良いでしょう。
簡単に言うと、同じ言葉の中にも法律上の解釈や使い方が違う場合があるのです。だから「逸失利益」と「逸失利益」の違いは、主に使い方・場面・計算基準の違いで生まれると言えます。
逸失利益の計算や評価のポイントをわかりやすく解説
逸失利益の計算は意外と複雑です。
まず基礎収入を決め、そこから労働能力喪失率や就労可能期間を乗じて計算します。
基本的には下記のような式が用いられます。
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 基礎収入 | 事故前の年間収入・利益 |
| 労働能力喪失率 | 事故によって失った働く能力の割合(%) |
| 就労可能期間 | 働けなくなる期間(年数) |
この3つを使い
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能期間の調整計算
という計算形式になります。
ただし、この「就労可能期間」は普通、未来の収入の損害を考慮して「中間利息控除(利息の調整)」も含めて細かい計算が法律で定められていることが多いです。
このため計算は専門的で、実際の裁判や保険査定では「弁護士」や「損害鑑定士」などの専門家が入ることが多いのも特徴です。
つまり逸失利益を正確に計算することは、適切な損害賠償を受けるために重要ですし、自己で正しく理解しておくことも大事と言えるでしょう。
逸失利益の中でも特に注目したいのが「労働能力喪失率」です。
これは事故や病気によってどのくらい働く力が失われたかをパーセンテージで示すものです。
例えば手や足が動かなくなった場合、その影響の度合いによって労働能力喪失率は変わります。
この数字が高ければ高いほど、未来の収入減少分の計算も大きくなり、損害賠償額も増えます。
労働能力喪失率の判定は医師の診断や裁判所の判断により決まることもあり、実は専門的で難しい部分なのです!
前の記事: « 【初心者必見】機会費用と逸失利益の違いをわかりやすく解説!





















