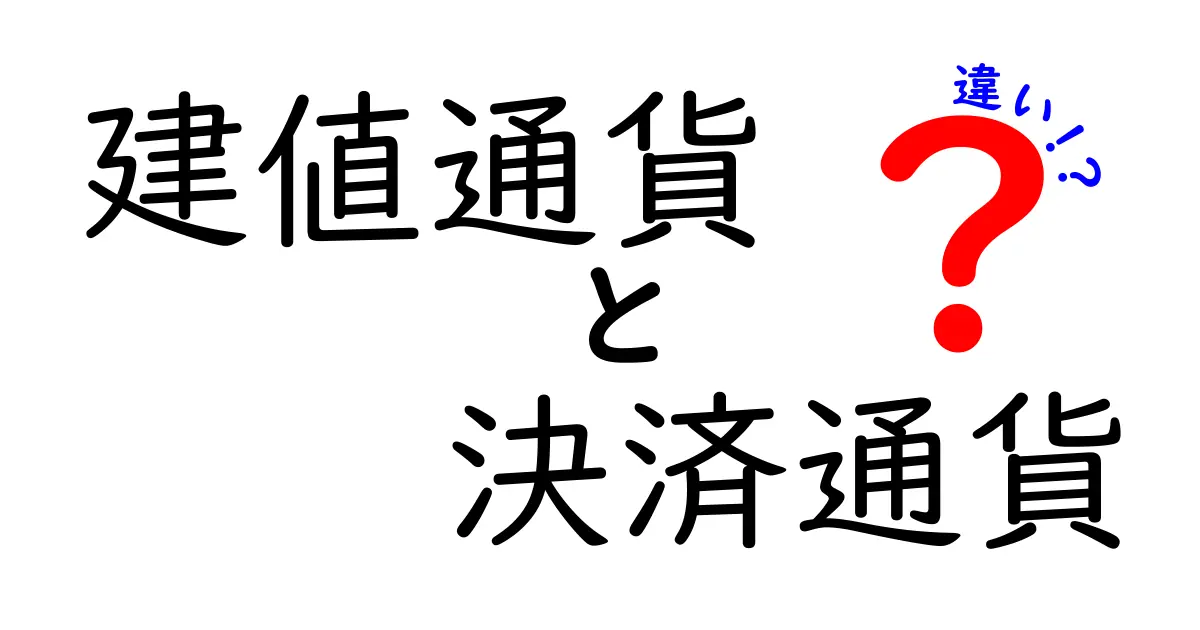

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
建値通貨と決済通貨の基本とは?
海外でお金の取引をするとき、「建値通貨」と「決済通貨」という言葉を聞くことがあります。
この二つは似ているようで違うものです。簡単に言うと、建値通貨は契約上の通貨、決済通貨は実際に支払う通貨のことを指します。
例えば、会社が外国の製品を買うとき、契約書にはある通貨で金額が決められています(これが建値通貨)。しかし実際にお金を払うときは違う通貨を使うこともあり、その場合の支払いに使う通貨が決済通貨です。
この二つが違うと、為替リスクや計算の複雑さが変わってきます。内容を詳しく見ていきましょう。
建値通貨と決済通貨の違いを詳しく解説
建値通貨とは、契約や取引で価格を示す通貨のことです。
例えば、日本の会社がアメリカから商品を買うとき、契約で「1000ドル」と決めたら、このドルが建値通貨です。
一方、決済通貨は、実際に支払いをする際に使われる通貨です。
上記の契約でも、決済通貨が必ずドルとは限りません。場合によっては円建てで支払うこともあり、その場合円が決済通貨になります。
つまり、建値通貨は取引の基準通貨、決済通貨は支払いで使われる通貨です。
この違いは、為替の変動リスクや手数料にも影響を与えます。
建値通貨と決済通貨の特徴を比較した表
| 項目 | 建値通貨 | 決済通貨 |
|---|---|---|
| 意味 | 契約上の価格通貨 | 実際の支払いに使われる通貨 |
| 役割 | 取引の基準となる価値 | 支払い処理の通貨 |
| 変動リスク | 為替変動の基準になる | 支払い時の為替リスク影響を受ける |
| 事例 | 契約書はドル建て | 支払いは円やドル |
建値通貨と決済通貨が異なる場合の注意点
もし建値通貨と決済通貨が違う場合、為替レートの変動で支払い額が変わるリスクが生まれます。
たとえば、契約はドル建てでも、決済時に円で支払うとき、ドル円の為替レートが変わっていれば支払い額は増減します。
このリスクを管理するために、「為替予約」や「ヘッジ取引」を利用する会社も多いです。
建値通貨と決済通貨を同じにすれば、このリスクは減りますが、必ずしもできるとは限りません。
取引先の都合や国際規則などで、決済通貨は別になることが多いです。
また、決済通貨によっては手数料や交換コストも異なるため、会社はコスト管理も重要になります。
まとめ
建値通貨は取引価格を示す通貨、決済通貨は実際に支払う通貨という違いがあります。
為替リスクやコストの面から、この二つの違いを理解しながらビジネス取引を行うことが大切です。
為替の基本を知ることで、これからの経済や貿易についての理解が深まります。
ぜひ覚えておきたい重要なポイントです。
建値通貨という言葉は、契約上の通貨という意味で利用されますが、実は為替リスクの管理でとても重要です。例えば、建値通貨がドルで、決済通貨が円の場合、ドル円の為替レートが変わるだけで支払金額が大きく変わることがあります。会社によっては、このリスクを避けるために為替予約という方法で、あらかじめレートを固定しているんですよ。そうすると、実際の支払い時に為替が動いても安心なんです。こうした細かい工夫が国際取引では欠かせません。





















