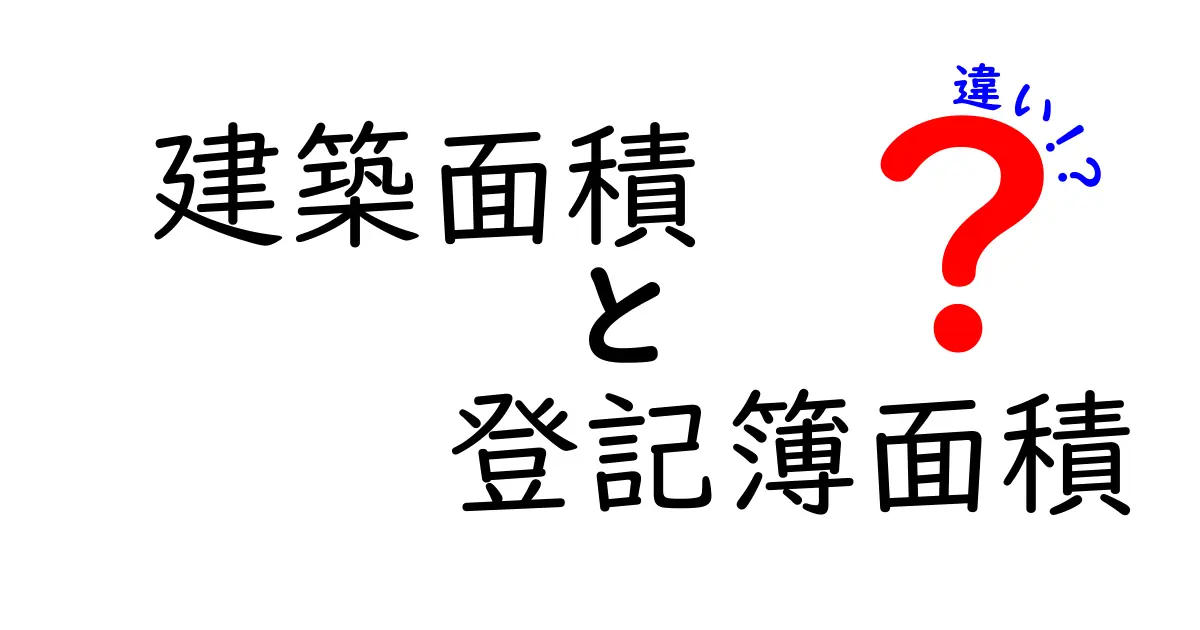

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
建築面積と登記簿面積って何?基本の違いを理解しよう
建築面積と登記簿面積は、どちらも「建物に関する面積」の名前ですが、実はそれぞれ意味が全く異なります。まずはそれぞれがどんな面積を表しているのか、基本をイメージでつかみましょう。
建築面積とは、建物が地面に実際に接している部分の水平投影面積、つまり「建物の建っている土地の広さ」です。上から見た時に建物が占めている床面の面積で、建築確認申請などで使います。
一方、登記簿面積は不動産の登記簿に記載されている面積のことです。建物の場合は一般的に「延べ床面積」が登記されています。つまり、建物の1階から最上階までの床の総面積を合計した数値です。
この違いがわかると、よく混同される「建築面積」と「登記簿面積」の意味がクリアになります。建築面積は土地の上の“ footprint ”、登記簿面積は建物の床の「合計の広さ」と考えるとわかりやすいです。
具体例で見る!建築面積と登記簿面積の違い
例えば、2階建ての家をイメージしてみましょう。1階の床面積が50平方メートル、2階の床面積が40平方メートルだとします。このとき:
- 建築面積:土地に接している部分なので、建物の1階の床面積、=50平方メートル
- 登記簿面積:1階と2階の床面積を足した合計、=90平方メートル
つまり、建築面積は「実際に土地に建物がのっかっている面積」、登記簿面積は「全階の床の合計面積」ということになります。
この違いは不動産の評価や税金計算、登記申請などで大切なポイントとなりますので、しっかり抑えておきましょう。
建築面積と登記簿面積の違いをまとめた表
わかりやすく、それぞれの違いを表にまとめました。ぜひ参考にしてください。
まとめ:使い分けが大切!混乱しやすい面積を正しく理解しよう
建築面積と登記簿面積は、名前が似ているので混同されがちですが、実際には異なる概念です。
建築面積は建物が土地に接している面積、登記簿面積は建物の全階の床面積の合計だと覚えましょう。
不動産を購入したり、設計や建築の手続きをするとき、税金の申告をするときなど、両者の違いを正しく理解しておくことがトラブル回避に役立ちます。
是非この記事でポイントを押さえて、安心して手続きを進めてくださいね。
『建築面積』は建物の地面に接している部分の広さですが、実は屋根の形やバルコニーの出っ張りは含まれません。
例えば、斜めの屋根の下に柱があっても、柱だけは建築面積には含まれないことがあります。
またバルコニーや庇(ひさし)が建物から出ている場合、それらが建築面積に含まれるかは建築基準法の細かいルールによって決まります。
つまり、同じ大きさの家でも設計の違いで建築面積が変わることもあり、この点を理解しておくと建築計画を立てやすくなりますよ。
次の記事: 包装資材と梱包資材の違いとは?初心者でも分かる完全ガイド »





















