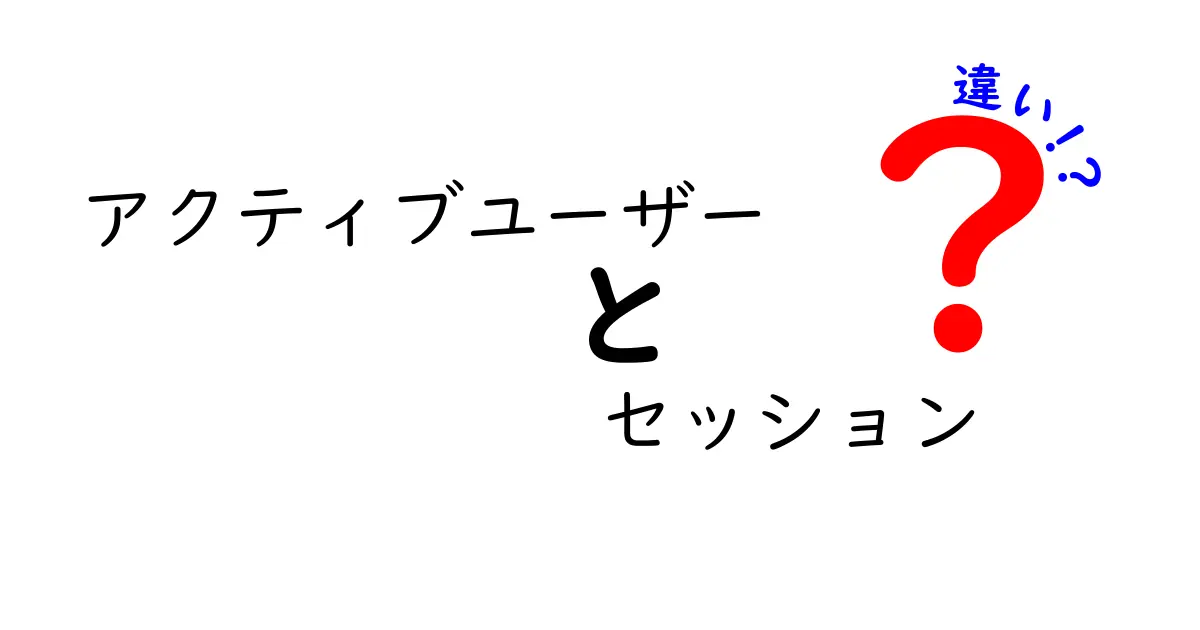

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:アクティブユーザーとセッションの基本を押さえる
このブログでは、ウェブサイトやアプリの分析でよく登場する2つの指標「アクティブユーザー」と「セッション」について、初心者にもわかる言葉で解説します。まず基本を押さえましょう。
アクティブユーザーとは、一定期間にサービスを実際に利用したユニークな個人の数を指します。ここでの個人は通常、同一人物を1人としてカウントします。これに対してセッションは、1人の利用者がサービス内で行った一連の行動のまとまりを指します。例えばニュースサイトを朝に開いて記事を読み、別の記事をクリックしてさらに読み進めるという一連の動作を1回のセッションとして数えます。ここが重要なポイントです。セッションは同一人物が1日あたり複数回発生することもあり、そのたびに新しいセッションが開始されます。こうして「アクティブユーザー」と「セッション」は似て非なるものとして設計されています。分析をする時には、どの指標を使うのか、そして何を比較したいのかを明確にすることが大切です。
例えば月次のレポートでアクティブユーザーが1万人、セッションが25万回と表示されていた場合、同じ人が何回もサイトを開いているのか、あるいは多くの新規訪問があったのか、などの違いを読み解く必要があります。
この章を読んでおくと、データの見方が変わり、現場での意思決定もスムーズになります。
アクティブユーザーとセッションの違いを表で理解する
以下の表は両指標の意味と使い方を整理するためのものです。要点は表の各列に分かれています。読み方のコツは、まずどの指標を用いて現状を把握したいのかを決め、その後に他方の指標を組み合わせて理由を考えることです。データを叩くだけで終わらせず、現場の意思決定につなげられるように意識してください。
この章の内容を実務に落とす際には、期間の設定(日次か月次か)、対象の定義(ユニークな個人かセッションの回数か)、そして解釈の前提(新規 vs リテンション)をそろえることが大切です。
| 指標 | 意味 | 測定対象 | 期間の例 | 使いどころのポイント |
|---|---|---|---|---|
| アクティブユーザー | 一定期間にサービスを利用したユニークな個人の数 | 個々のユーザー | 日次・月次などの期間単位 | 規模感を把握するのに有効。新規・リテンションの両方を見たい時に組み合わせると効果的 |
| セッション | 1人の利用者がサービス内で完結する行動のまとまり | セッション単位の行動 | 日次・週などの短い期間 | 滞在時間や導線の品質、ページ遷移の評価に有効。短時間でのエンゲージメント測定にも使える |
| 併用の見方 | アクティブユーザーとセッションを組み合わせて分析 | 両方のデータ | 任意の期間 | エンゲージメントの変化やリテンションの強さを把握するのに役立つ |
| 注意点 | 表現が混同されやすい、同一人物の重複カウントなどが起こる | - | - | 定義を揃え、期間の設定を統一して比較することが大切 |
この表を見れば、アクティブユーザーとセッションが何を意味しており、どんな使い方をすると有効な洞察が得られるかが分かりやすくなります。実務では両指標を適切に組み合わせて、ターゲット層の行動パターンを検証していくことが大切です。
実務での使い分けと注意点
実務での使い分けは状況によって変わります。新規顧客の獲得状況を知りたい場合はアクティブユーザーの推移を重視し、サイトの導線改善や滞在時間の向上を図るにはセッションの質を詳しく見ると効果的です。分析を進める際には、データの前提をそろえることが重要です。たとえば、同一人物の重複カウントの回避、期間の切り替え時の基準の一致、イベント追跡の整合性などを事前に決めておくと、誤解を減らせます。さらに、セグメントを作って新規 vs リピート、モバイル vs PC、地域別などで比較すれば、改善の優先順位がはっきりします。最後に大事なのはデータだけを見て終わらず、現場の戦略と結びつけて意思決定につなげることです。
分析結果を元にしたタスクを具体化し、KPIの見直しや施策実行へと落とし込むことで、実務での効果を最大化できます。
ある日友だちとカフェで雑談していたとき、アクティブユーザーとセッションの違いの話題になったんだけど、私たちは最初アクティブユーザーが多いほど人気があると思い込んでいた。でも実はそれだけじゃダメなんだよね。アクティブユーザーはその人の数、セッションはその人がサイト内で行った行動のまとまり。Aさんが1日に3回訪れて3つのセッションを作っても、1人のアクティブユーザーにしかカウントされない。だから、ビジネスの評価では両方を見比べることが大事。セッションが多いのに滞在時間が短いなら導線の改善点、逆にセッションは少ないがアクティブユーザーが増えているなら新規獲得に成功していると解釈できる。結局、データは“数”だけでなく“何を意味するのか”を理解して初めて活きてくるんだよね。そういう意味で、分析は数字の羅列ではなく会話のように読み解くことが大切だと思う。





















