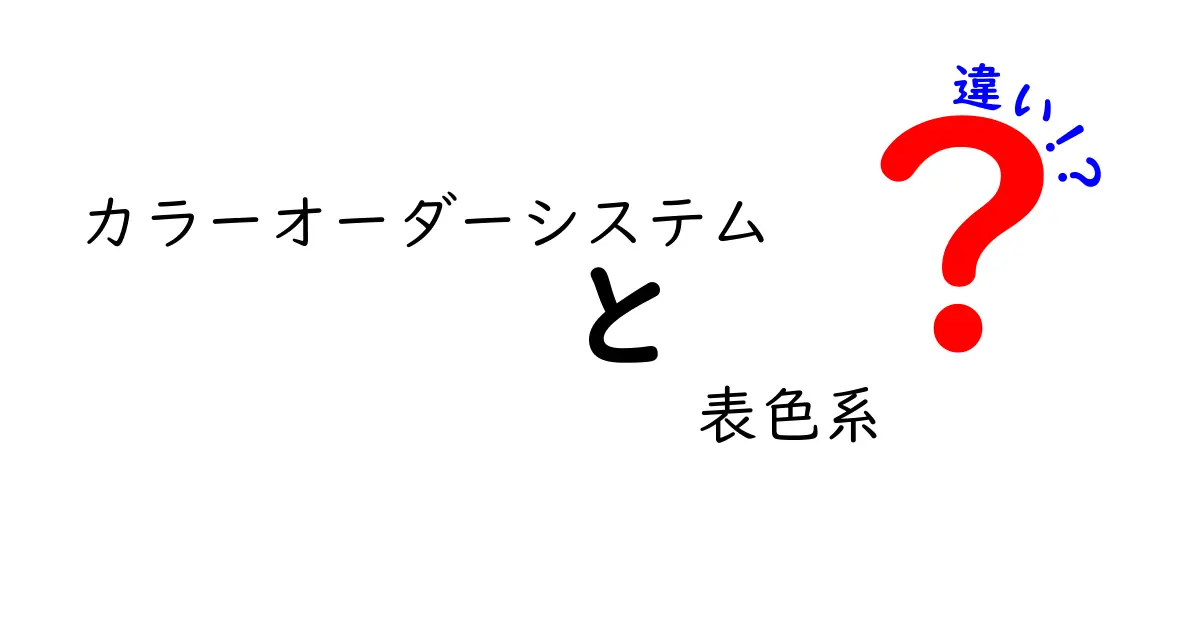

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カラーオーダーシステムと表色系の違いを理解する
色の世界には、色をどう取り扱うかを決める仕組みがいくつもあります。中でもよく出てくるのがカラーオーダーシステムと表色系です。カラーオーダーシステムとは、デザインや製造の現場で色を一貫して再現するための"指示の仕組み"のことを指します。具体的には、色を決める番号やコードを用意して、どの工程でも同じ色を再現できるようにします。印刷所では「この紙とこのインクの組み合わせでこの色になる」という発注情報を、コードとして伝えることが日常的に行われます。Pantoneのような企業固有のカラーコードは典型例で、デザイナーとプロの現場の間で“何色か”を確実に共有する道具になります。これがカラーオーダーシステムの核です。
一方、表色系は色そのものを座標として整理する考え方です。人の見る色を、機械が扱える数値や三次元の空間に置き換えることで、デジタルの世界と現実の色を橋渡しします。表色系を使うと、ある色が別のデバイスでどう見えるかを予測しやすくなり、色管理の出発点となります。つまり、カラーオーダーシステムは「色をどう指示するか」を決めるのに対して、表色系は「色をどう表すか」を決めるのです。ここが大きな差であり、デザインの現場では両者をうまく組み合わせて使うことで、意図した色に近づけることができます。
この関係を日常の例えで考えると、カラーオーダーシステムは“レシピの番号”のようなもの、表色系は“料理の味を測る基準”のようなもの、と言えるでしょう。レシピが同じでも使う食材が違えば味や見た目は変わります。色の世界も同じで、同じコードでも媒体の特性が違えば最終的な色は変化します。重要ポイントとして、カラーオーダーシステムは流れを統一するための設計図、表色系は色を正しく表現するための座標系と覚えておくと混乱を避けられます。さらに、デザインの学習では、両者の使い分けと連携の仕方を体感することが、現場のスキルを高める近道になります。
表色系の違いと具体的な活用ポイントを深掘りする
表色系の具体的な中身を深く理解するには、いくつかの代表的な色空間とその性質を知ることが役に立ちます。まずRGBは、光を三原色として組み合わせる方式で、主にデジタル画面の表示に使われます。モニターが発する赤・緑・青の光を混ぜて色を作るので、画面上の色は非常に直感的に再現できます。ただし、印刷の世界とは相性が悪く、同じ数値でも紙の白さやインクの特性によって見え方が変わる点には注意が必要です。次にCMYKは、印刷で使われる色空間で、シアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの四色を組み合わせて色を作ります。紙という媒体の性質上、再現できる色域には限界があります。デザインの現場では、CMYKに変換する工程で「見た目の差」を最小限に抑える工夫が欠かせません。さらにLabは、デバイスに依存しない色空間として使われることが多く、色の距離を測るときのベースになることが多いです。表色系はこれらの色空間を比較・結合するための地図の役割を果たします。
また、ICCプロファイルという小さな情報が、ある機器の色再現を正確に再現する鍵になります。例えばウェブだけを見ればsRGBが十分という場合が多いですが、印刷物を高品質に仕上げたい場合はAdobe RGBやCMYKの組合せを検討する価値があります。色管理の作業では、用途と媒体の特性を最初に決め、それに合わせて表色系を選択・調整することが重要です。ポイントは、広い色域を選ぶことが目的ではなく、最終成果物が実際にどの媒体でどう見えるかを予測し、適切なプロファイルを設定することです。こうした理解が深まると、デザインの段階での修正回数が減り、制作全体の効率が上がります。
- 用途別の色空間の選択:ウェブ用にはsRGB、印刷用にはCMYKやAdobe RGBを検討するのが基本です。
- デバイス依存のリスクを減らす:ICCプロファイルを活用して機器間の色のずれを抑えることが大切です。
- 実務のコツ:最初の段階で媒体と用途を決め、変換後の色味の検証を必ず行う習慣をつけると良いです。
たとえば、表色系の話を友だちと雑談するならこんな感じです。RGBは“光の色のレシピ”みたいなものだから、画面で赤と緑を混ぜると黄色っぽい光になる、という具合に、どの色を足すかで見える色が変わるんだ。だけど印刷を想定すると話は別。紙は光を反射して見えるので、同じRGBの値でも紙の白さやインクの性質で色がずれる。だからCMYKという別の色空間を使って、紙の上で近い色を再現する工夫をする。表色系を理解していれば、デジタルとプリントの間のズレを事前に予測できるようになるから、作品の仕上がりが安定してくるんだ。





















