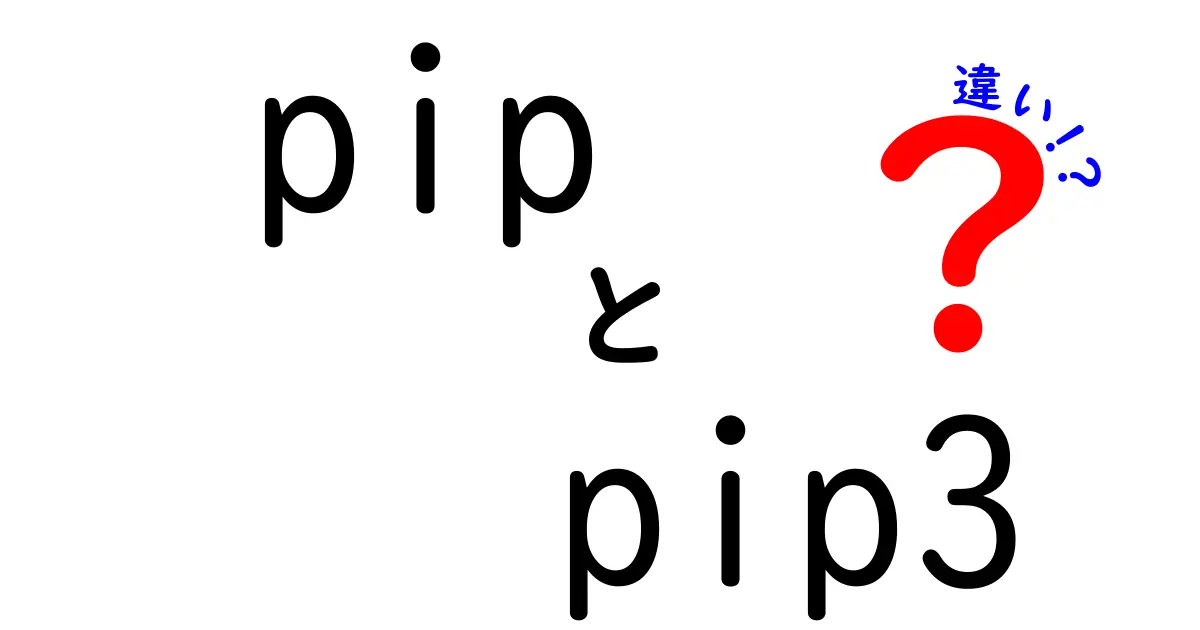

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
pipとpip3の違いを徹底解説!初心者でも分かる使い分けのポイント
この話題はPythonを触る人が初めてつまずくポイントの一つです。pipとはPythonのパッケージを管理する道具で、数多くの外部ライブラリを手軽に導入できる非常に便利な機能です。pipとpip3の違いを知ると、なぜ同じコマンド名が異なるPythonの実体に作用するのかが見えてきます。特にWindowsとUnix系の違い、仮想環境の扱い、そして環境依存のトラブル回避の観点から理解しておくと良いです。以下のポイントを頭に入れておくと、授業の課題や自習が格段に楽になります。まず基本的な考え方として、pipは現在のシステムで使われているPythonのパッケージ管理ツールを指しますが、環境によってはPython2向けのものを指すこともあります。この点が混乱の原因になります。反対にpip3は、Python3向けのパッケージ管理ツールを明示します。つまり、Python3を使っているときはpip3を使えば確実に3系の環境に対して操作できます。ここで重要なのは、どのPythonを使っているかを確かめる癖をつけることです。コマンドラインで簡単に確認できます。pip --version や pip3 --version を実行して、どのPythonのどのバージョンと紐づいているかを読み解くのが最初の一歩です。もし自分の環境でpipがPython2を指していた場合には、python2 -m pip のような形になるかもしれません。現代の主流はPython3ですが、古いシステムを触る機会はまだあります。そこで、Python3を前提に話を進めると混乱は減ります。次の実務的なポイントとして、python -m pip でパッケージを操作する方法を紹介します。これは「どのPythonが使われているか」を常に確定させるうえで最も安全な方法の一つです。例えば python -m pip install numpy のように書くと、現在実行しているPythonに紐づくpipが使われます。これを覚えておけば、Python2とPython3の両方が同じマシンに存在していても、意図しないバージョンのライブラリを取り込むリスクを抑えられます。
pipとpip3の違いを理解する基本ポイント
ここからは、使い分けの具体的な基礎を丁寧に整理します。まず最初のポイントは、どのPythonの環境に対してパッケージを追加するのかを特定することです。Python2とPython3が同じマシン上に混在している場合、pipはPython2向け、pip3はPython3向けと解釈されるのが一般的です。しかし、現代の多くの環境ではPython2自体が使われなくなってきており、pipがPython3を指すケースが多くなっています。それでも、環境次第ではpipがPython3を指していないこともあり得るため、まずは pip --version と pip3 --version を実行して、実際にどのPythonバージョンと紐づく鍵かを確認してください。次に覚えておくべき実務ポイントは、仮想環境を活用することです。仮想環境を作ると、特定のプロジェクトだけで使うパッケージを隔離できます。これにより、別のプロジェクトの依存関係が壊れるリスクを減らせます。仮想環境の作成コマンドは、python3 -m venv myenv で環境を作成し、source myenv/bin/activate(Windowsなら myenv\Scripts\activate)で有効化します。その後のパッケージ導入には pip3 install package のように、3系のpipを使います。もし複数のPythonが共存している場合は、python -m pip install package の形式を使うと、現在アクティブなPythonに対してのみ操作されるので安全です。現場でよくある苦手ポイントとして、パスの設定ミスや環境変数の影響があります。これを避けるために、まずは仮想環境を整え、そこに対してpip3を使い、必要に応じてpy -m pipやpython -m pipを使い分けると良いでしょう。最後に、パッケージのアップグレードや削除のコマンドも覚えておくと、運用がぐっと楽になります。アップグレードは pip3 install --upgrade package、削除は pip3 uninstall package の形で実行します。これらの基本を身につけておけば、どんな環境でも安定して作業を進められます。
今日は pip3 の話題を深掘りします。最近はPython3が主流ですが、現場ではまだ pip と pip3 の混乱が続くことがあります。私自身も最初はどちらを使うべきか迷いました。結局のところ、環境を確認して python -m pip を使う癖をつければ安全です。小さな会話のように、友だちと雑談するくらいの気持ちで環境を確認するのがコツです。





















