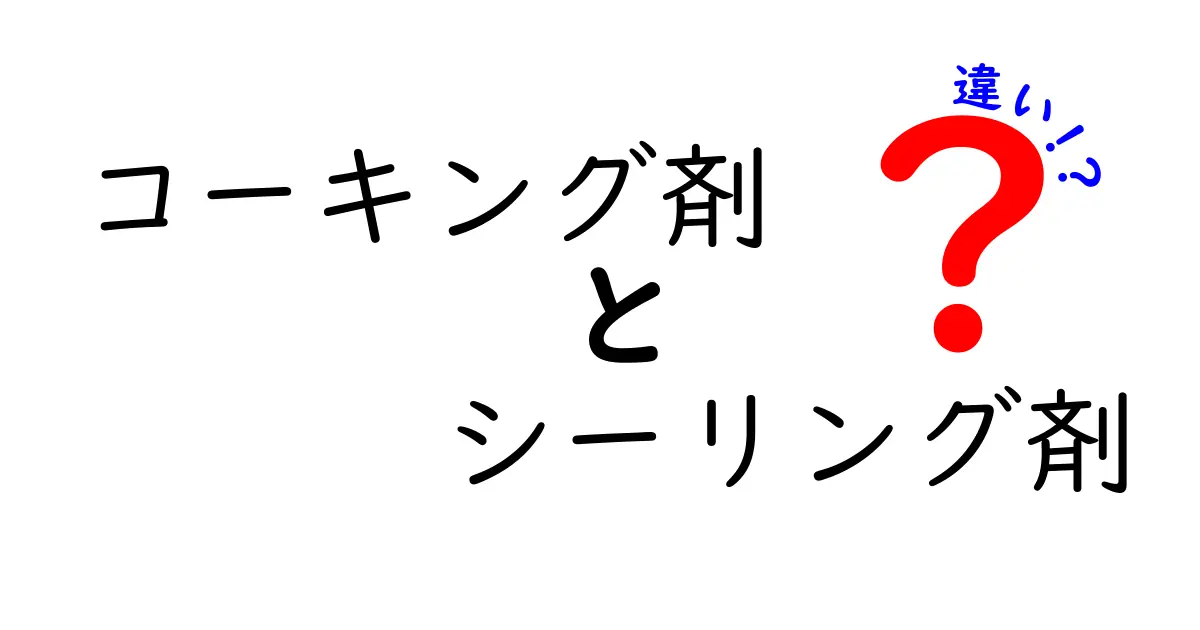

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
コーキング剤とシーリング剤の違いを分かりやすく解説!用途別の選び方と失敗しない使い方ガイド
家づくりやリフォームの現場でよく目にする「コーキング剤」と「シーリング剤」。似た名前で混同されがちですが、実は役割や特徴が少し異なります。ここでは中学生でも分かるように、まず基本的な違いを押さえたうえで、どの場面にどちらを使うべきか、選び方のコツと実際の使い方のポイントを丁寧に解説します。
丁寧に選べば、長持ちして水漏れや亀裂を未然に防ぐ効果が高まります。これからのDIYや学校の工作、家の補修にも役立つ内容です。
まず大事なのは「コーキング剤」と「シーリング剤」が同じカテゴリーの製品でありながら、成分や粘性、硬化の仕組み、そして使える場所が少し違うという点です。
以下を読み進めると、意味がはっきりと分かり、適材適所の選択が自然と身につきます。
コーキング剤とシーリング剤の基本的な違い
まず知っておきたいのは、コーキング剤とシーリング剤の語源と使い方の違いです。コーキング剤は「隙間を埋めるための材料」という意味合いが強く、外壁や窓回り、床と壁のつなぎ目など、動きが出る場所に使うことが多いです。成分としてはシリコーン系、ポリウレタン系、アクリル系などがありますが、伸び率や耐候性、塗装の可否が異なります。これに対してシーリング剤はより広い意味で、建物の結合部や地下・水回りなど水分が関わる場所に使われる総称です。実際には多くの製品がコーキング剤として扱われることがあり、販売店でも混同されやすい点は注意が必要です。
重要なポイントは「用途と素材に合わせて選ぶこと」。シールしたい場所の動き・ひずみ・紫外線・水分の影響を考慮して選別することが長持ちのコツです。
また、可動部での硬化後のひび割れを防ぐには、適切な柔軟性・弾性を持つ製品を選ぶ必要があります。
どの場面でどちらを使うべきかの具体的な目安
実際の現場では、場所ごとの特性をチェックして選ぶのがコツです。屋外の窓枠・ベランダの水回り・外壁のジョイントなどは紫外線と温度変化にさらされるため、耐候性と長期の柔軟性が高いコーキング剤を使うのが基本です。反対に、内装の隙間や天井裏の小さな穴塞ぎ、木材と石膏ボードの接合部など、水が直接かかりにくい場所にはシーリング剤が適しています。粘度の違いによって使い分けることも大切で、硬化時間が長い製品は作業のしやすさを生む一方、短時間で仕上げたい場合は別の選択肢を検討します。
また、塗装を前提とする場所には塗装適性のある製品を選ぶと色合わせが簡単です。
効率よく進めるなら、まず下地の処理・清掃を徹底し、養生テープでラインをきっちり作ることが失敗を減らすコツです。
実際の作業のコツとよくある失敗
最後に、作業を楽に進め、仕上がりを美しく保つコツをまとめておきます。
下地の清掃は必須です。埃や油分が残っていると接着力が落ち、端の密着が甘くなります。養生テープを貼ってラインをきっちり作り、余分な材料をよく拭き取ることが重要です。
素人がやりがちなのは「厚く盛りすぎて流れる」「乾く前に触ってしまう」こと。適正な厚みと指で押して形を整えるタイミングが仕上がりを大きく左右します。石膏ボードや木材の接合部では、ひずみの動きに追従できる製品を選び、定期的な点検を忘れずに。
正しく選び、丁寧に作業すれば、ひび割れや水漏れを長い間抑えることができます。
さらに、季節や温度によって硬化の感じ方は変わります。夏場は日差しで乾燥が速くなるため、下地の湿度を見ながら作業を進め、冬場は温度が低く硬化が遅くなるので、作業時間を多めに確保します。道具の清掃と適切な換気も大切です。
最近、家の補修をしていると、コーキング剤とシーリング剤の違いが気になる友達がいます。実際には同じ家の材料として使われていて、名前のニュアンスが違うだけという話をしました。コーキング剤は主に隙間を埋めて動きに対応する伸びのある材料で、外の窓回りや床下の隙間に使われることが多いです。シーリング剤はより広い意味での防水・結合を目的とする材料で、内部の結合部や水回りの周りにも使われ、耐候性や塗装適性の違いを考慮して選ぶ必要があります。友達と話していると、粘度や硬化時間、色の合わせ方まで話が広がり、実際にDIYを始めるときのワクワク感が増してきたのを覚えています。





















