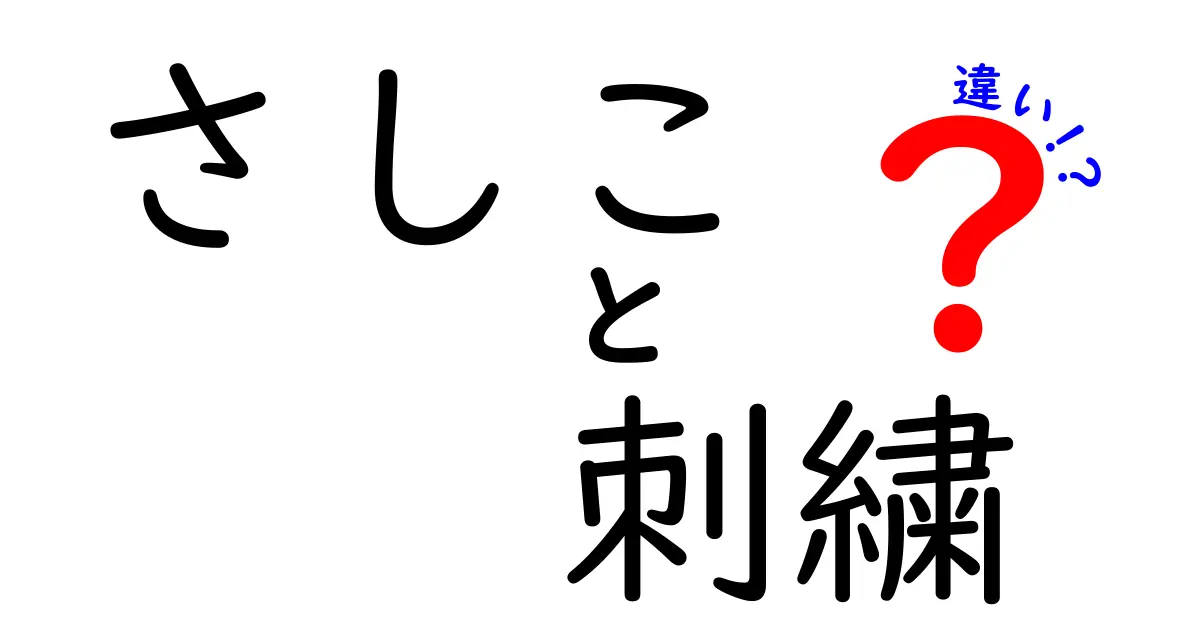

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:さしこ(刺し子)と刺繍の違いを知ろう
さしこ(刺し子)と刺繍の違いを理解する第一歩は、それぞれがどんな目的で生まれたかを知ることです。日本の布文化には、実用性と美しさの両立を求める伝統がありました。さしこは、布地の補強や冬の暖かさを増すための実用技法として生まれ、手縫いの細かな縫い目で布を重ねて強くしました。材料は主に藍染めや生成りの布と白い糸が中心で、縫い目は走り縫い(running stitch)などシンプルな技法が基本です。これにより、布の破れを防ぐと同時に、布面に白い模様が現れ、意図的な美しさが生まれました。
一方、刺繍は世界中で多様な模様と色を使って布を装飾する技法の総称です。材料や道具はさしこと同じような糸と布を使うこともありますが、縫い方は多岐にわたり、幾何学模様、動植物の絵柄、文字など限界のない表現が可能です。実用の補強から芸術表現へと用途が広がり、布の繊細さを活かすために、糸の種類や布の目を選ぶ工夫も進化しました。
このような違いを踏まえると、さしこは“機能と伝統美の両立”を目指した技法であり、刺繍は“装飾と自己表現の広がり”を追求する技法だと言えます。
現代では、さしこは手作りの小物、クッション、巾着、布団カバーなど日常生活の中で実用とデザインを両立させる作品に使われ、刺繍は衣服の装飾、バッグのデザイン、アート作品など様々な場面で活躍します。これを理解すると、作品づくりのときに何を優先するかが見えてきます。
さしこ(刺し子)の特徴と歴史
さしこは江戸時代頃から広がった日本の布補強技法として始まりました。主に藍染めの布と白い糸が組み合わされ、布の縫い目を走り縫いで並べるシンプルな図案を規則的に並べます。初期は農民や漁師の衣類、古着の補修が目的でしたが、模様を施すことで布の補強効果も高まり、次第に風合いの良さや楽しさを求める人が増えました。代表的な模様として麻の葉、矢羽、格子などがあり、白い糸と藍のコントラストが特徴です。現代ではキルトや布団カバー、ポーチ、バッグなど日常生活の中で楽しむ趣味の対象として人気があります。道具は基本的に針と糸、布、そして定規。
さしこは地域ごとに異なる模様のパターンを持ち、地域の文化や季節感を映す鏡のような役割も果たします。伝統模様をそのまま学ぶこともできますし、新しいモチーフと組み合わせることで現代の作品にも合います。
以下の表は、さしこの基本的な要素を整理したもの。
| 用途 | 布の補強・保温・装飾 |
|---|---|
| 材料 | 布(主に藍染め・生成り)、白い糸、時には別の色糸 |
| 技法 | 基本は走り縫い。図案は幾何学模様が多く、連続した縫い方が特徴 |
| 仕上がり | 白い縫い目の連続模様が布面に現れ、丈夫で温かみのある風合い |
| 代表的な模様 | 麻の葉、矢羽、格子、市松など地域ごとに異なる |
刺繍の特徴と幅広い技法
刺繍は世界各地で長い歴史を持つ布装飾技法です。材料は布と糸を基本に、布の種類や糸の素材を変えることで風合いを変えます。糸は絹、綿、羊毛、金糸など多彩で、布地は薄手のシルクから厚手のキャンバスまでさまざま。技法は無数にあり、サテンステッチ、バックステッチ、チェーンステッチ、ボヴィンステッチ、コーナリングなど、目的に応じて組み合わせます。色の組み合わせや糸の太さ・長さで表現は大きく変わり、立体感を出す工夫も多くあります。刺繍は衣類の装飾、バッグ、タペストリー、壁掛け、アート作品など用途が広く、技法を習得すると描くように布を“作る”楽しさが広がります。現代の刺繍はデジタル図案と組み合わせて新しい模様を生み出す人も増え、若い人々の手芸としても人気です。
刺繍の魅力は、糸と布が織り成す小さな世界に、色彩と形の表現を自由に追加できる点です。古くからの伝統模様を受け継ぐこともできますし、自分の好きなモチーフを描くこともできます。世界中の伝統模様と現代デザインが混ざり、新しい作品が次々と生まれています。
違いを整理して使い分けるコツ
日常での使い分けは、実用性と装飾性のバランスで決まります。大きな布地を長く丈夫に使いたい場合はさしこが適しています。さしこは布に走り縫いの模様を連続させることで、見た目の美しさだけでなく布の補強効果も得られます。布団カバーや財布・ポーチの縁など、日用品のアクセントとして使うと効果的です。
一方、衣服やバッグの装飾、壁掛けのタペストリーなど、色と形を自由に表現したいときには刺繍が適しています。複雑な模様や立体感を出す技法を選べば、作品がグッと華やかになります。
初心者には、同じ布と糸でさしこ風の図案を練習してから、刺繍へと段階的に移るのがおすすめです。道具は似ていますが、布の目の細かさや糸の太さを変えるだけで作品の印象が大きく変わります。大切なのは「何を作りたいのか」を最初に決め、そこに適した模様と技法を選ぶことです。
さしこについて友達と雑談していたとき、私はふと違いの根底にある考え方の違いに気づきました。さしこは布を補強して生活を守るための実用的な知恵から生まれた技法で、走り縫いの規則的な美しさが特徴です。それに対して刺繍は色と形で自己表現を広げる表現の自由さが魅力です。同じ布と糸を使っていても、目的と見せ方がまるで違います。話をしていると、友達の作る作品の雰囲気が変わるのが分かり、私も自分の作品づくりでどちらを主役にするかで作品の印象が大きく変わると感じました。さしこは冬の暖かさを運ぶ布、刺繍は春の色彩を運ぶ布。そんな具合に、使い分けを考えるだけで日々のクラフトが楽しくなるのです。





















