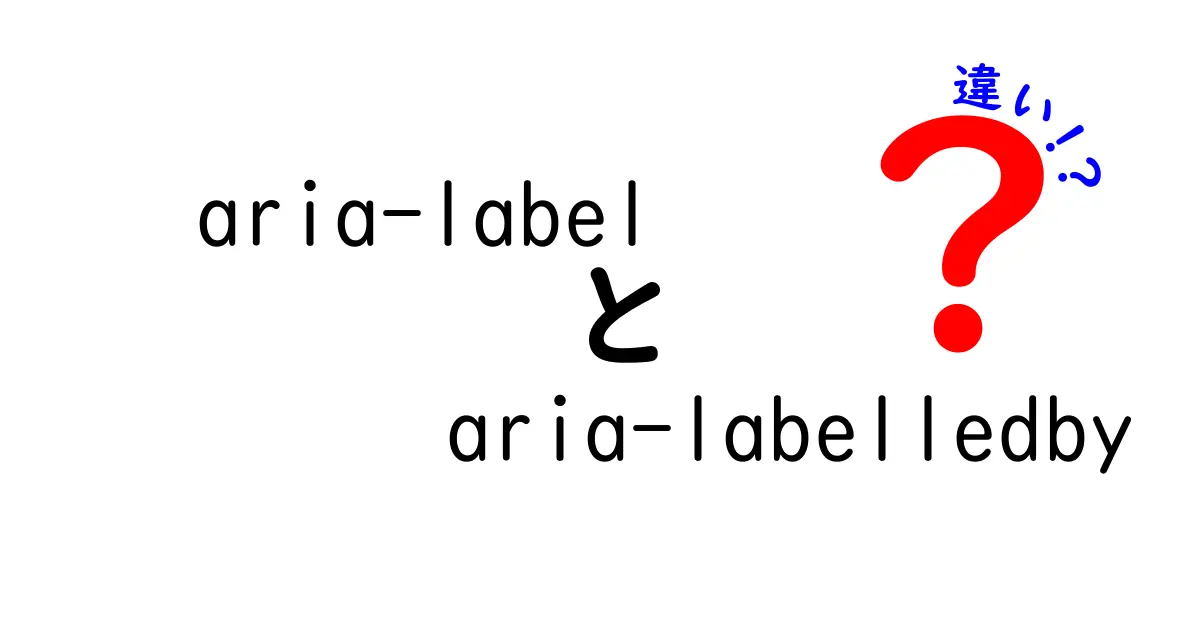

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
aria-labelとaria-labelledbyの違いを理解するための基礎ガイド
ウェブアクセシビリティを意識して作業する際に耳にするaria-labelとaria-labelledbyは、見た目には似た機能を持つように見えますが、使い方の目的と時と場合で大きく役割が異なります。aria-labelは要素に直接名前をつける手段で、短い説明や単語で読み上げを完結させられることが多いです。対してaria-labelledbyは別の要素を参照してラベルを構築する仕組みで、長い説明や複数の要素から一つのラベルを作るのに適しています。実務ではこの違いを理解して使い分けることで、ボタンやアイコンが何をするものかを適切に伝えられ、スクリーンリーダーを使う利用者にとっての操作性がぐっと良くなります。
このガイドでは定義の違いだけでなく、実際の使い方のコツ、注意点、そして簡単な比較表を用意しました。読み終わる頃には自分のプロジェクトでどちらを使うべきか、迷わず判断できるようになります。
さあ、まずはそれぞれの属性がどんな場面で力を発揮するのかを見ていきましょう。
aria-labelとは何か
aria-labelとは要素に直接文字列を割り当て、読み上げ対象として使われる属性です。短くても的確な説明を設定でき、ボタンやアイコンなど視覚情報だけでは意味が伝わりにくい場合には特に有効です。例としては検索ボタンに aria-label を設定して「検索」と読み上げさせるケースや、アイコンだけのボタンに説明を付けて使いやすさを確保する場合などがあります。aria-labelの大きな利点は外部要素を必要とせず、すぐに説明を追加できる点ですが、長文の説明をそのまま表示したい場面には向きません。長い説明を別の要素に任せたいときには aria-labelledby との使い分けを考えましょう。さらに aria-label を適切に使うことで、画面上のデザインと聴覚に伝える内容を分けて設計することが可能になります。
また、 accessibility の観点からは読み上げ順序にも気をつける必要があります。画面上には見えない説明が存在している場合、スクリーンリーダーはそれを読み上げることがありますので、情報の提供順序を混乱させないよう注意してください。ここまでを理解すれば、aria-labelが「短いラベル」で、aria-labelledbyが「複数要素の集合としてのラベル」を作る手段であることが自然と分かってくるはずです。
aria-labelledbyとは何か
aria-labelledbyとは別の要素を参照してラベルを構築する属性です。複数の要素を組み合わせて一つのラベルを作る場面や、長い説明を再利用したい場合に適しています。使い方のポイントは参照先の要素に必ず id が付いていることと、参照先が表示されていなくても読み上げ対象として機能することです。具体的には見出しと説明文、あるいは複数のテキスト要素を組み合わせてボタンに対するラベルを作るといったケースで有効です。aria-labelledbyを使うと、説明を一箇所に集約して管理でき、UIを変更してもラベルの更新を楽に行えます。しかし参照先が削除されたり名前が変わってしまうと、ラベルが崩れるリスクもあるため、監視とテストが欠かせません。
この方法は特に長文の説明や複数の文字列を一つの意味として読んでほしい場合に力を発揮します。aria-labelと組み合わせて、読み上げの品質を高める設計を心がけましょう。
実務での使い分け
実務では UI の性格に合わせて aria-label と aria-labelledby を使い分けます。短い指示やアイコンの直感的な意味を伝えたいときには aria-label が手軽で効果的です。反対に、長い説明を組み合わせて一つのラベルを作る必要がある場合や、複数の要素から情報を読み上げさせたい場合には aria-labelledby を選ぶのが自然です。実装時のコツとしては
まとめと表
ここまでのポイントを一言で整理すると、 aria-label は短いラベルを直接与える道具、 aria-labelledby は複数要素を結合して長いラベルを作る道具です。実務では状況に応じて使い分けを行い、読み上げ順序や補足情報の扱いにも注意します。以下の表は基本的な違いを比較したものです。
表の内容は確認用の参考として読んでください。
| 項目 | aria-label | aria-labelledby | ポイント |
|---|---|---|---|
| 定義 | 要素に直接名前を設定 | 他の要素を参照してラベルを形成 | 使い分けの核心 |
| 長さと構造 | 短い説明に適する | 長い説明や複数要素の組み合わせに適する | 説明量に応じて選択 |
| 更新と保守 | 直接編集可能 | 参照先の更新で自動反映 | 保守性が高い場合あり |
今日は aria-label について友達と雑談をしました。私は最初、アイコンだけのボタンには適当に文字をつけてしまい、スクリーンリーダーの友人がボタンの意味を理解できず困っているのを見てショックを受けました。そこで aria-label の力を思い出し、検索ボタンには aria-label を「検索」と設定しました。読み上げは以前よりはるかに的確になり、使い勝手が格段に良くなりました。さらには aria-labelledby の存在も知り、長い説明を別の要素へ分けて管理することのメリットとデメリットを友人と語り合いました。結局のところ、UIの見た目と読み上げの内容を分離して設計することが、誰にとっても使いやすいWebを作る近道だと感じました。これからも aria-label と aria-labelledby の使い分けを意識して、分かりやすくて思いやりのある設計を心がけたいと思います。





















