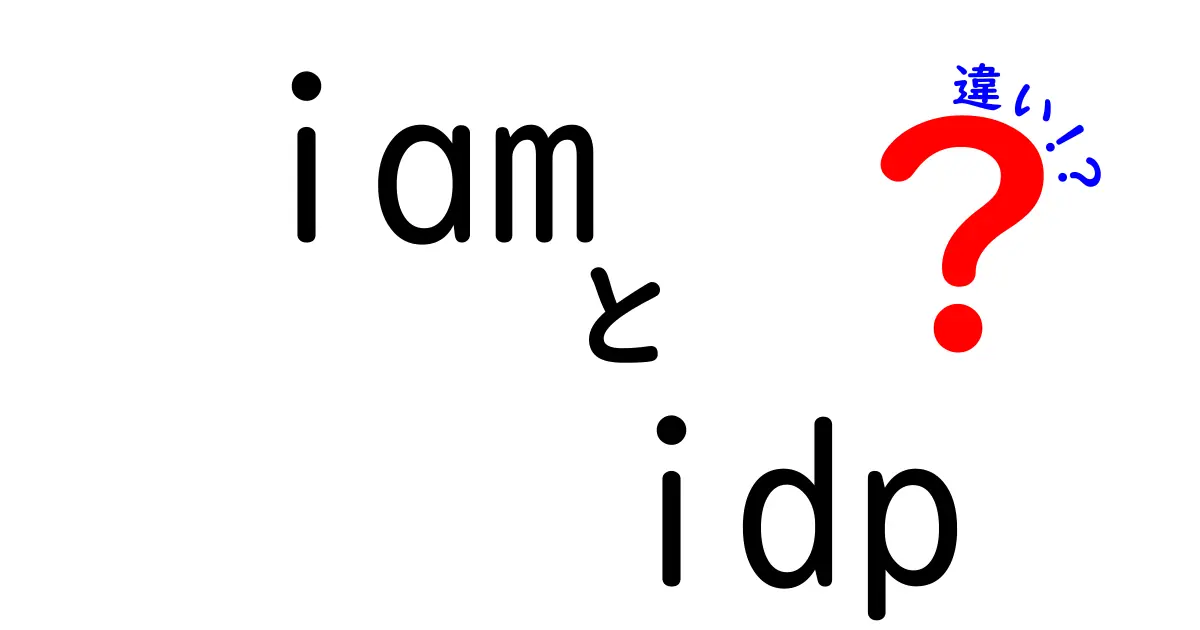

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
IAMとIDPの違いを理解するための基本ガイド
IAMとIDP、この2つの用語は似ているようで役割が違います。ここでは中学生にも分かるように、まず用語の定義を丁寧に整理します。
IAMはアイデンティティとアクセスを管理する仕組み全般を指す広い概念です。人のアカウント作成、権限の割り当て、どの人がどの資源にアクセスできるかを管理します。クラウドでも社内でも、ユーザーの情報を一元的に管理する仕組みがIAMです。
一方IDPは「アイデンティティプロバイダ」と呼ばれ、認証情報を受け取り、身元を確認して他のサービスへその情報を渡す役割を果たします。要するにIDPは認証の窓口であり、あなたが正しい人かどうかを判断して結果を渡す人です。
これらを正しく組み合わせると、サービスを利用する人が別々のサービスごとにIDとパスワードを覚える必要がなくなり、1回のログインで複数のサービスを使えるようになります。これがSSOと呼ばれる仕組みの土台にもなります。
基本用語の整理:IAMとIDPとは何か
IAMは組織の全体的なアクセスと権限の管理を指します。IDPは外部のサービスに対して本人認証を提供する仕組みです。例えば社内で人事情報を管理するユーザーアカウントを作成・更新するのがIAM、そのアカウントの正当性を検証して他のアプリケーションへ通知するのがIDPです。
そして現場ではSSOやOAuth、SAML、OpenID Connectなどの技術が混在します。
これらの技術は一部がプロトコル名であり、別の言い方をすると情報のやりとりの決まり事です。
SSOを使うと、ひとつの認証で複数のサービスにアクセスでき、毎回別のパスワードを入力する手間を減らすことができます。ここまで理解すれば、IAMとIDPの関係が見えてきます。正確にはIAMが「誰がアクセスできるかを決める管理者側の仕組み」で、IDPが「誰かを認証する窓口」という役割分担になります。
現場での役割の違いを具体例で比較
想像してみてください。あなたの会社ではOktaのようなIDPを使い、クラウドサービスのGmailやAWS、社内のアプリを一度のログインで使えるようにしています。ここでIDPはあなたが正しい人物かどうかを確認し、認証済みの証拠(トークン)を各アプリに渡します。一方IAMはこの人がどのアプリを使えるか、どの資源にアクセスできるかを組織全体で決めます。例えば人事部の人には給与データへのアクセス権を与え、経理部には別の権限を与える、という形です。
具体的な流れをもう少し細かく見てみましょう。社員Aが社内のポータルにログインすると、まずIDPがAのIDとパスワードを検証します。認証が通ると、IDPはAに対して「この人は正しい」という証拠を返します。次に各サービスはこの証拠を検証して、Aが許可された資源のみを表示します。ここでIAMの設定が効いてくるのです。もしAが人事部の権限しか持っていなければ、給与データにはアクセスできません。
この仕組みにより、セキュリティを高めつつ、ユーザー体験を向上させられます。現場ではIDPとIAMが連携して動作することが多く、認証と認可の分担を理解することが重要です。
実務での使い分けと注意点
実務ではIDPとIAMを別々に考えると混乱が生まれやすいですが、基本の考え方はシンプルです。まずIDPは「誰かを証明する窓口」であり、認証の信頼性を確保します。次にIAMは「誰に何をさせるか」を決める権限管理です。実装時のポイントとしては、以下の点が挙げられます。
- MFAの導入と強化: 認証の堅牢性を上げるため、パスワードだけでなく追加の認証要素を組み込みます。
- 権限の最小化: 必要な権限だけを付与する原則を徹底します。
- ログと監査の徹底: 不正アクセスを早期に検知するための監査ログを残します。
- 認証方式の統一: SAMLやOpenID Connectなど複数のプロトコルを使い分ける場合は、統一した運用ルールを作成します。
- 外部連携のセキュリティ: 外部のIDPを利用する場合の信頼関係やデータの取り扱いに注意します。
これらを適切に設計すれば、使い勝手とセキュリティの両立が実現します。
よくある誤解とこれだけは知っておきたいポイント
よくある誤解として、IAMとIDPを同じものだと考えるケースがあります。しかし実際には役割が別物です。IDPは認証の窓口、IAMは権限管理の土台です。もう一つの誤解はクラウドとオンプレミスの混同です。現代の環境ではIDPはクラウドと連携することが多いですが、オンプレミスのアプリにも対応可能です。要点は「1回の認証で複数のサービスを安全に利用できる状態を作ること」と、「誰が何をできるかを厳格に管理すること」です。これを念頭に置けば、導入時の設計がスムーズになります。
さらに覚えておくべきポイントとして、プロトコルの選択があります。SAMLは古くからあり互換性が高い一方、OpenID Connectは現代的でモバイルにも適しています。組織のニーズに合わせて適切なプロトコルを選ぶことが重要です。
表で見る違いと要点
ここでは要点を整理するための簡易表を用意しました。実務での判断材料として活用してください。
IAMの役割:組織全体のアクセス権限の設計・運用。
IDPの役割:認証情報を受け取り、信頼できる証拠をサービスへ提供。
例:社内のアカウント管理と外部サービスの認証を橋渡しする役割分担。
メリット:セキュリティ向上、利便性の向上、監査性の確保。
デメリット:設定が複雑になることがある、運用コストが増える場合がある。
要素 説明 IAM 誰が何をできるかを管理する中心的機能 IDP 誰かを認証する窓口。認証結果を渡す SSO 1度の認証で複数サービスへアクセス OpenID Connect IDPと連携する認証プロトコルの一つ SAML 古典的な認証プロトコル。主にエンタープライズ向け
この表を読むだけでも、IAMとIDPの違いと連携のポイントが見えてきます。組織の規模や利用するサービスの数が増えるほど、緻密な設計が重要になります。
友人とカフェで雑談していたときのような雰囲気で進めます。私たちはIAMとIDPの違いを、ただの用語の話ではなく日常のシーンに落とし込みながら理解を進めました。IDPは“認証の窓口”という役割を果たすことで、あなたが誰なのかをサービスに伝え、IAMは“誰に何が許されているか”を決めるルールを作ります。二つがうまく連携すると、毎回のパスワードを覚える手間が減り、セキュリティも高まります。





















