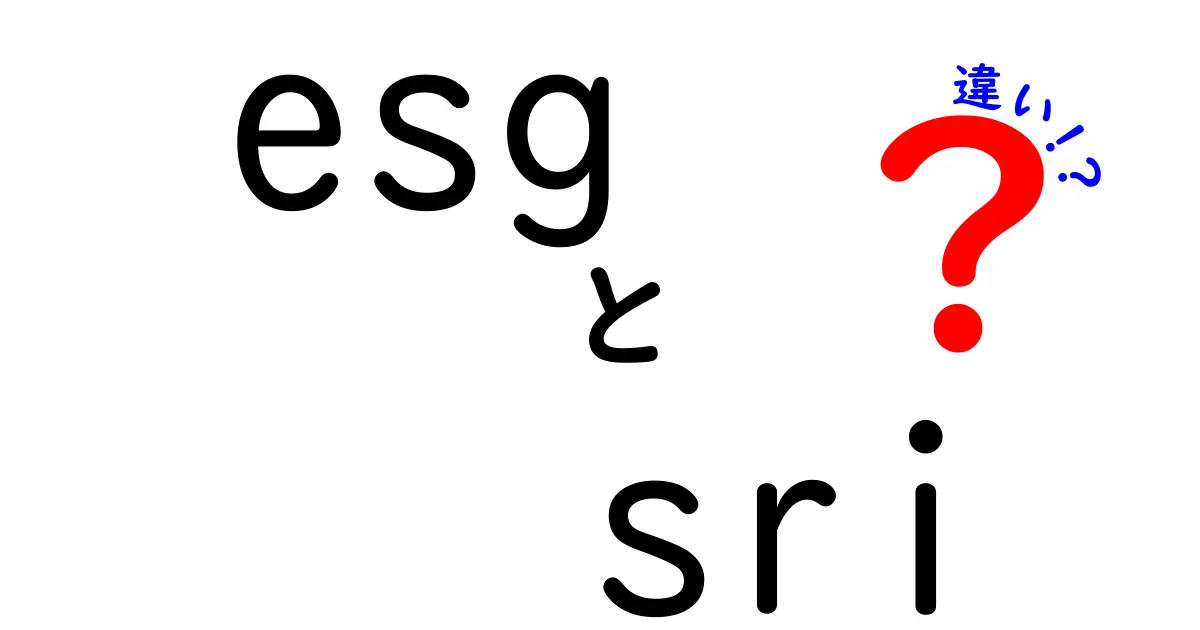

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ESGとSRIの基本を押さえる
ESGとは Environmental, Social, Governance の略で、環境・社会・ガバナンスの3つの観点から企業の持続可能性を評価する考え方です。企業の行動が長期的な成績に影響するという前提で、投資家や金融機関はこの3つの要素を分析します。具体的には、環境面では二酸化炭素排出量や資源の使用効率、気候変動への対応、社会面では従業員の待遇、ダイバーシティ、地域社会との関係、ガバナンス面では取締役会の独立性・透明性、リスク管理の仕組みなどを見ます。これらの情報は開示資料や第三者機関の評価、企業との対話などから得られ、“企業の将来の耐久力”を測る指標として使われます。
例えばある大手メーカーが再エネの導入を進め、サプライチェーンの労働環境を改善すると、ESG評価は上がりやすくなります。
このようにESGは企業そのものの内部プロセスと行動の質を見て、長期的なリスクと機会を評価する枠組みです。
ESGとSRIの違いを理解する実務的ポイント
一方、SRIはSocially Responsible Investingの略で、投資家の倫理観や価値観に基づいて資金の出し方を決めます。「何を投資するか」ではなく「何を除外するか」が大きなポイントになる場合が多いのが特徴です。一般的には銃器・たばこ・ギャンブル・兵器など社会的に問題視されやすい分野を除外するネガティブ・スクリーンが用いられます。また、環境や社会に配慮した企業に限定して投資するポジティブ・スクリーンを行うケースもあります。これにより、投資先は倫理的・社会的への影響を考慮した選択になります。ただしSRIは「投資の目的が倫理性に偏る」点が特徴であり、必ずしも財務面での最適解と一致しないこともあります。
この組み合わせを理解するには、基金やファンドマネージャーが公表している運用方針・スクリーン基準を確認することが大切です。
また、現代の市場ではESGとSRIは互いに排他的ではなく、同時に活用するケースが増えています。つまり、「企業の持続可能性を評価する」ためのESGと、「倫理的な投資を実現する」SRIの両輪を使うことで、投資判断の幅と深さが広がります。表や図を使って整理すると理解が深まるので、次の表も参考にしてください。
SRIについて友人とカフェで雑談していたとき、彼は「倫理って難しくて、結局どこまで許せるかが問題になるんだろう」と言いました。そこで私はこう答えました。「SRIは“除外”と“選択”的投資の組み合わせだよ。例えば武器やタバコを避けるのは基本中の基本。でもそれだけで終わらず、環境や社会に配慮する企業を積極的に選ぶこともある。つまり倫理性と財務性の両方を天秤にかける作業だ。さらに長期的には、SRIだけでなくESGの情報を併用することで、投資判断の納得感が増すんだ。要は、個人の価値観と市場の現実をどう結びつけるかというバランス感覚が大事ということなんだよ。





















