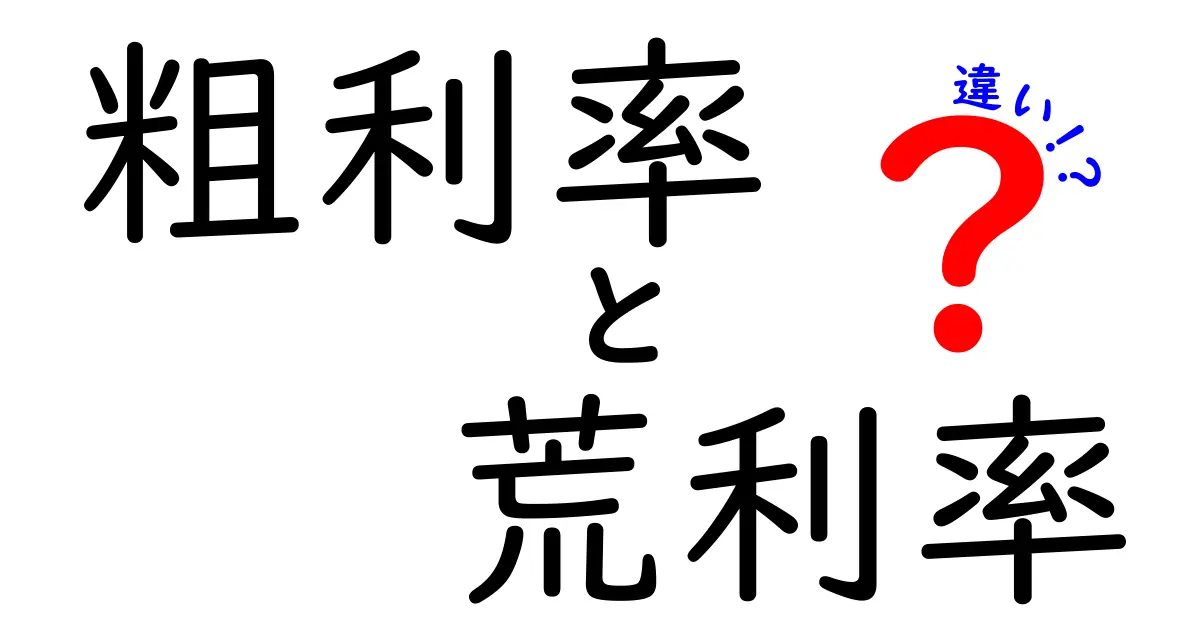

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
このセクションでは、粗利率と荒利率の違いを基本から丁寧に解説します。似た言葉ですが、使われる場面や意味のニュアンスが違うことが多いです。中学生にも分かるよう、身近な例と日常の会話風の導入を交えつつ、結論を先に伝え、その後に根拠を積み重ねていきます。まず覚えておきたいのは、どちらの指標も「売上と原価の関係」を示す数値で、企業の利益を把握するための基本的な道具だという点です。
この二つの言葉は、会計ノートや決算説明資料で頻繁に登場しますが、同じ意味として使われることもあれば、業界の慣習で微妙に意味が異なる場合もあります。
以下の説明を通じて、違いをはっきりさせ、実務や授業で使える具体的な読み解き方を身につけましょう。
粗利率の基本と実務での使い方
ここではまず「粗利率」の定義と計算方法をはっきりさせます。粗利率は、売上高から「売上原価」を引いた値(=粗利)を売上高で割って、100を掛けた割合です。式で書くと、粗利率 = (売上 - 原価) / 売上 × 100% となります。日常の例で考えると、文房具を1000円で売って、仕入れ値が700円なら粗利は300円、粗利率は30%です。ここで大事なのは「原価」に含まれる費用の範囲が、どの費用を指しているかを確かめることです。製造業と小売業では原価の考え方が少し異なるため、資料によっては原価の定義が変わることがあります。
このような差を避けるため、資料の注釈を読んで、売上原価に何が含まれているのかを確認しましょう。
また、粗利率は利益の“入口”の指標であり、あくまで売上に対する利益の割合を示します。人件費や広告費などの後続の費用は、この段階の「粗利」には含まれません。したがって、粗利率だけを見て満足するのではなく、次の段階の利益率(営業利益率など)とセットで見ると、企業の健全性がよく分かります。
荒利率の実務的な扱いと注意点
一部の業界や地域では「荒利率」という言葉を粗利率の別名として使うことがあります。意味は基本的に似ていますが、使われる場面や資料の定義が異なることがあり、混乱のもとになることがあります。荒利率を読み解くコツは、まず「原価の範囲」がどこまで含まれているかを確認することです。販売費や一般管理費などの間接費を含めるかどうかで、同じ売上高でも値が変わることがあります。初心者の人は、決算書の注記を読み、原価の算定範囲を把握する習慣をつけると理解が深まります。なお、現場では「荒利率は粗利率の同義語として使われることが多い」という前提の説明も多く見られます。その場合には“荒利”と“粗利”の両方の言葉が使われる理由を、会計の人に確認するようにしましょう。
業界別の使い分けと注意点
業界によっては用語の使い方が異なります。小売業や卸売業では「荒利」と呼ぶ場合があり、荒利率は「売上高から仕入原価を引いた金額を売上高で割る」という解釈で使われることが多いです。一方で製造業では「粗利率」が中心の指標となり、原価には製造原価が含まれ、場合によっては部品費や外注費を含めるかで数値が変わります。こうした差異を避けるには、資料の前提条件を必ず確認することが大切です。なお、学校の授業では「粗利と荒利は同じ意味と考えてよい」という前提で説明されることもありますが、実務では“どの原価を含めるか”の差が判断の key になります。
日々の会計ノートでも、「この値はどの範囲で計算されたのか」を併記する癖をつけると、後で見返すときに混乱を防げます。
表で見る計算例
下の表は、売上1000、原価700、仕入原価600などの複数のケースを並べ、粗利率と荒利率を比較するものです。実務ではこのように複数のシナリオを並べて確認します。
数値はすべて端数を切り捨ててありますが、実務では小数点以下も使われることがあります。
覚えておくべきポイントは、原価の定義が変わると同じ売上でも値が変動するということと、粗利率と荒利率の関係性は基本的には同じ方向に動くことが多い、ということです。
放課後、友だちのミユキとファミレスでお金の話をしていた。授業で習った“粗利率”の話題が頭の中をぐるぐるしていた。私は「売上から原価を引いた額を売上で割るんだよね」と言うと、ミユキはコーヒーの湯気を見上げながら同意した。私たちは雑談風の実例を交えつつ、粗利率と荒利率の違いを繰り返し深掘りした。1000円の文房具を仕入れて売るとき、原価が700円なら粗利は300円、粗利率は30%だ。荒利率についても同じ感覚で考えることが多いが、原価の定義が資料ごとに異なる点を確認するのが大切だと結論づけた。
この話のあと、私たちは文化祭の品物計画にも同じ考え方を適用して、現実的な利益見通しを作る練習をした。





















