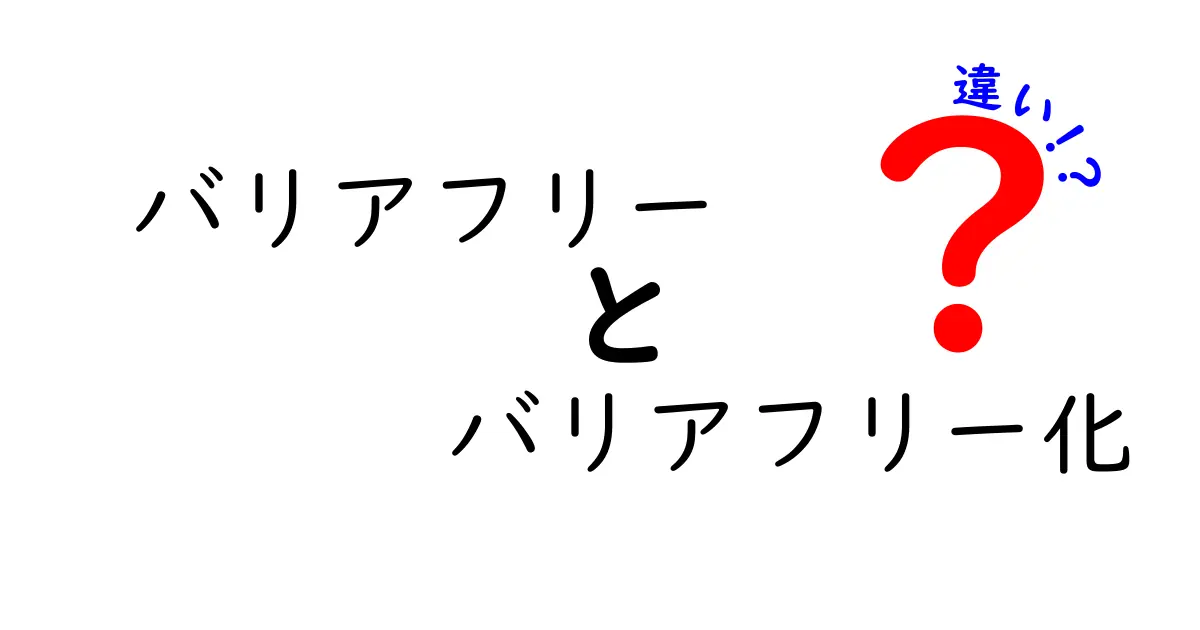

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
バリアフリーとバリアフリー化の違いを徹底解説:意味と使い分けをわかりやすく
まず、バリアフリーという言葉は“障害のある人や高齢者が日常生活で直面する壁(物理的・社会的な障壁)を減らす考え方”を指す、社会全体の理念や考え方のことを表します。つまりこれは状態や理想の姿を示す名詞的な概念です。公的機関の方針や教育のカリキュラム、メディアの報道など、抽象的・総論的な場面でよく使われます。
対して、バリアフリー化とは、その理念を現実の行動・工程として実際に進めることを意味します。具体的には「どの場所を」「誰のために」「どのくらいの期間で」「どのような手順で」変えていくのかを決め、実務として実施していく過程を指します。
この2つは“何を進めるのか”という視点の違いに現れます。日常会話やニュース、計画書の表現にも、相手に伝わるニュアンスの差が出ます。|
では、日常生活の場面でどう使い分けるのがよいでしょうか。駅や公的施設の話題では、バリアフリー化を進めるという表現が一般的です。具体的には車いす利用者の動線確保、点字ブロックの設置、音声案内の導入、トイレの多機能化、段差解消などの対策を指します。これらは現場で進行中の工程であり、誰が責任を持って進めるのか、いつまでに完成を目指すのかといった要素を明確にすることで、関係者の協力を得やすくなります。反対に、社会全体の価値観や理念を説明する場面では、バリアフリーという語を使い、理念の共有・理解の統一を図ります。ここでは、誰のために、何を大切にするのか、という問いが中心になります。
このように、同じテーマでも“変える対象”と“変える手段”を切り分けると、説明が伝わりやすくなります。現場の実務では、計画を具体化する際に目的・対象・工程・責任者・予算を分けて整理することがコツです。例として、駅の改修計画では動線の確保と案内表示の改善を同時進行で進める、学校のウェブサイトの場合はバリアフリー対応のポリシーを明文化する、などが挙げられます。
最後に重要なポイントを整理します。
1) 状態と工程を分けて考える。
2) 相手に合わせた用語選択をする。
3) 計画書には“目標”と“手段”を別々に明記する。
4) 現場の声を反映させる。
5) 予算とスケジュールをきちんと示す。
この5点を意識するだけで、説明がずっと分かりやすくなり、関係者との誤解を減らせます。
バリアフリーとバリアフリー化の使い分けのコツ
実務での使い分けをさらに深掘りしていきます。まずは「状態」か「工程」かをはっきり分ける癖をつけましょう。
次に、話す相手や場面に合わせて用語を選ぶ練習をします。たとえば地域住民向けの説明なら「バリアフリー」という理念的な表現を多用し、行政の計画書や技術打ち合わせでは「バリアフリー化」という具体的な改修・作業の語を用います。
さらに、現場の声を拾うための仕組みをつくることも大切です。現場の職員、利用者、設計士の意見を定期的に集め、短期・中期・長期の段階計画に反映させます。
最後に、成果を示す指標を決めておくと進捗管理が楽になります。例えば「動線の幅の改善率」「段差解消箇所の数」「案内表示の読みやすさの改善度」など、定量的な指標と定性的な評価の両方を組み合わせると、継続的な改善に役立ちます。
今日は放課後の学校の話題を雑談風に深掘りしてみます。友だちと教室の入り口を見渡しながら、バリアフリーとバリアフリー化の違いについてふとした会話を交わしました。友だちは『化ってつくと難しそうだよね、何をどう進めるの?』と素朴な疑問を投げかけます。僕は『理念と実際の作業の違いだよ』と答えつつ、教科の授業で習った言葉の意味を思い出します。実際には、学校の廊下の段差をなくす、トイレの表示を見やすくする、ウェブサイトの情報を読みやすくする、これらはすべてバリアフリー化の具体的な取り組みです。一方で、教室の授業資料や学校全体の方針としての“皆が暮らしやすい学校”という考え方はバリアフリーの理念にあたります。こうした話を友だちと繰り返すうちに、小さな改善の積み重ねが大きな変化につながるんだなと実感しました。たとえば段差をなくすと、車いすの子やベビーカーを使う家族も移動しやすくなり、授業の導入資料も読みやすくなります。そんな地道な努力が、日々の生活をより楽しく、安心して過ごせる場へと変えていくのだと感じました。





















