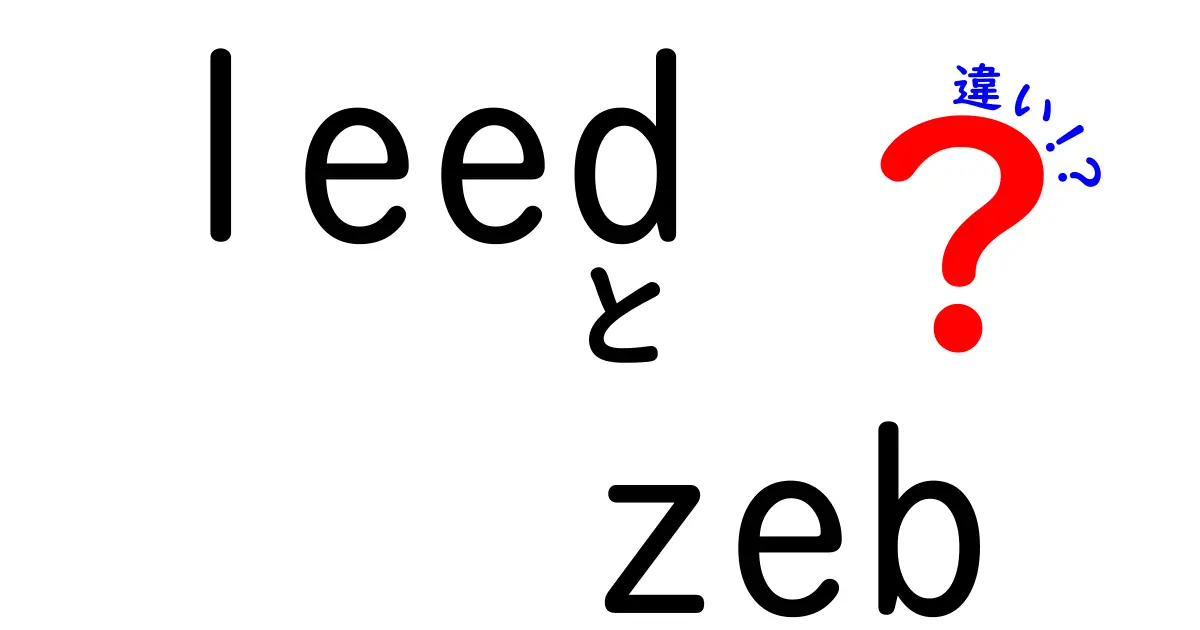

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
LEEDとZEBの基本と違いを理解するためのガイド
LEEDとZEBは、建物の環境性能を評価する重要な枠組みです。LEEDは米国の団体が開発した認証制度で、設計段階から運用までの総合的な評価を目指します。評価は材料・エネルギー・水資源・室内環境・交通・景観などの複数カテゴリーに分かれ、点数を積み重ねることで認証レベルが決まります。
このしくみの大きな特徴は、設計の質や長期的な持続可能性を重視する点です。
一方のZEBはゼロエネルギー建物を指す日本語の概念で、建物が年間で消費するエネルギーを自家発電や省エネ設備で相殺して実質的にゼロに近づけることを目標とします。
ZEBは公開されている実績値で評価されやすく、エネルギー使用を抑える設計と発電設備の導入をセットで考える必要があります。
この二つを比べると、LEEDは“設計と運用の総合評価を地域的背景も含めて評価する”点が強く、ZEBは“年間のエネルギー収支をゼロに近づける現実的な技術と運用”が中心です。
つまり、LEEDは評価の枠組みとして広範囲をカバーしやすく、ZEBは実際のエネルギー数値を重視する実務寄りの目標と言えます。
費用や実現性の面でも違いがあります。LEEDは国際的な拠点を作る場合に有利になることが多い反面、認証取得の手続きや審査の時間がかかることがあります。ZEBは初期投資がやや大きくなることがありますが、長期的には光熱費の削減と快適性の向上につながります。設計者や建築主は、目的に合わせて選ぶことが大切です。
認証の仕組みと評価のポイント
LEEDの仕組みは、まず前提条件と呼ばれる必須の要件を満たした上で、複数のクレジットを取得して点数化します。
点数が累積するすると各認証レベルが決まります。設計・施工・運用のデータ提出が必要で、第三者機関による審査があります。重要なのは、設計段階での決定が評価に直結する点と、材料・資源・室内環境などの要素も総合的に評価される点です。
ZEBの評価は実績データに基づきます。年間のエネルギー消費量、一次エネルギーの使用量、再生可能エネルギーの割合などを計測し、設定した目標と比較します。実際の運用データが評価の中心になるため、現場の運用改善がそのままスコアに反映されやすい特徴があります。ZEBには段階表示があり、段階的な省エネ・自給の取り組みを示すことができます。
プロジェクトを進める際のポイントは、目標の設定を早い段階で確定させ、データの収集と分析を継続的に行うことです。設計時には高性能な外皮(断熱・気密)、省エネ機器、照明の計画を最優先に、建設後にはエネルギー監視システムの導入と運用ルールの整備が重要です。これらを組み合わせると、長期的なコスト削減と快適性の両立が見込めます。
友だちと LEED と ZEB の話をしていて、私はある疑問をぶつけてみました。結局のところ、LEEDは設計・運用の総合評価を通して建物の質を高める枠組みであり、ZEBは年間のエネルギー収支をゼロに近づけることを目的とする実務寄りの目標だ、という結論に落ち着きます。国際拠点を持つ企業なら LEED の認証でブランド価値を高めやすく、長期的なエネルギーコストを抑えたい場合は ZEB の導入を検討する、という使い分けが現場で役立ちます。設計者と運用担当者がこの違いを理解して協力すれば、建物はよりサステナブルに、そして快適に生まれ変わるのです。





















