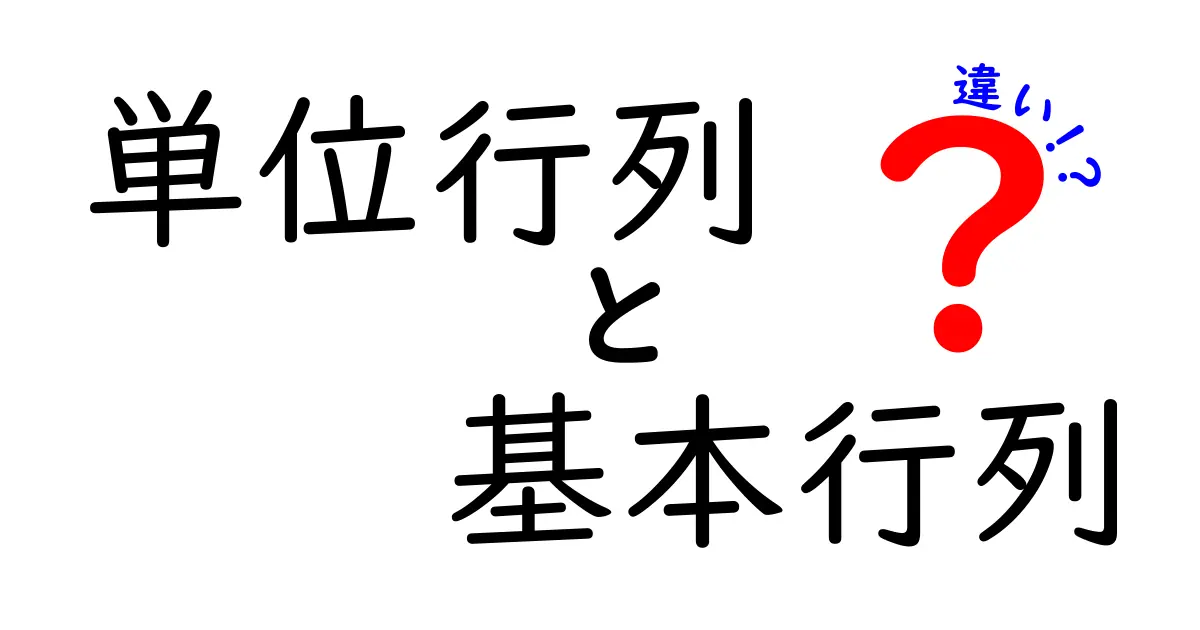

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:単位行列と基本行列の違いをおさえる
このテーマは、数学の中でも線形代数の基礎となる「行列」という考え方を理解する第一歩です。
単位行列と基本行列は名前こそ似ていますが、それぞれの役割が異なる“道具”として位置づけられます。
単位行列は計算の基準となる特別な存在で、行列の積を計算するときに“形を変えず”元の行列を守りつつ処理を進める役割を果たします。
一方、基本行列は行の入れ替えや足し算、拡大・縮小といった具体的な操作を表す道具で、行列を変形させる目的で使われます。これらを正しく区別できると、方程式の解法や線形変換の性質を直感的に理解できるようになります。
本記事では、まず単位行列の基礎を固め、次に基本行列の作り方と役割を実例つきで紹介し、最後に両者の違いを整理します。
さらに身近な例えや練習問題のヒントも添えるので、授業や自習にそのまま活用できるはずです。
この二つの道具を覚えるコツは、「単位行列は計算の基準、基本行列は計算の道具」という二つの役割を明確に区別すること」です。これを念頭に置くと、複雑な行列の操作もぐっと分かりやすくなります。
1. 単位行列とは何か
単位行列とは、対角線上の要素がすべて 1 で、その他の要素が 0 の正方行列のことを指します。サイズを示す記号として I_n の形で表され、n は行列の行数と列数の大きさを表します。例えば、2×2 の場合 I_2 = [ [1,0], [0,1] ]、3×3 の場合 I_3 = [ [1,0,0], [0,1,0], [0,0,1] ] となります。
単位行列には「乗算で何も変えない」性質があり、任意の行列 A に対して AI = IA = A が成り立ちます。これは代数の世界での“基準の役割”を果たす重要な性質です。
実際の計算では、行列の連続的な操作を進めるとき、まず I を上手に使って他の行列と同じ形になるように整え、そこから新しい情報を導き出すことができます。
この性質は、逆行列を求めるときにも手掛かりとなり、解法の流れを安定させる鍵になります。
2. 基本行列とは何か
基本行列とは、行列の行や列に対して“基本的な操作”を表す行列の総称です。具体的には、以下の三つの操作が典型的な基本行列として挙げられます。
1) 行を入れ替える操作を表す基本行列 (行を入れ替えると対応する行がそのまま入れ替わる)。
2) 行の一部を他の行の定数倍と足す操作を表す基本行列 (ある行に別の行の整数倍を足す)。
3) 行を一定の倍数で拡大・縮小する操作を表す基本行列 (行のスケーリング)。
これらの基本行列を実際に A に掛けていくと、行列の形を整える“ガウスの消去法”が成立します。
例えば、A に対して行を入れ替える基本行列 E_swap を掛けると、A の行が入れ替わる新しい行列 E_swap A が得られます。
また、特定の行に 3 倍を加える操作を表す E_add は、A の 1 行に 3×他の行を足す変換を可能にします。これらの手順を組み合わせると、元の行列を目的の形へと変換することができます。
基本行列はまた、行列の「変換の道具箱」として、線形方程式の解法や行列計算の設計において欠かせない存在です。
この部分を理解しておくと、後の章で出てくる計算の流れが格段に見通しよくなります。
3. 違いを理解するコツ
単位行列と基本行列の違いを覚えるコツは、役割を分けて考えることです。単位行列は計算の基準として働き、乗算のときに他の行列の形を変えずにそのまま残る特別な存在です。対して基本行列は、行列の形を変える「道具」であり、実際に適用するたびに元の行列がどう変化するかを観察する必要があります。
練習として、小さな行列を選び、ある基本行列を A に掛けたときの結果を手で追ってみると、変換の意味が体感できます。さらに I を使ってガウスの消去の手順を追うと、操作の順序と変換の意味が視覚的に理解しやすくなります。
表を使って、違いを一目で見分ける工夫もおすすめです。
違いを一言でまとめると、「単位行列は変えない基準、基本行列は変える手段」という二つの役割を分けて覚えることが最短です。この考え方を軸にすると、後の学習で混乱しにくくなります。
このほかにも、実際の演習問題を解くときには、「どの操作を使えばどの変換が起きるか」を意識することがコツです。最後に、単位行列と基本行列の両方を使う場面を想像しておくと、いつどの道具を取り出せばよいかが自然に分かるようになります。練習問題を解くときには、答えだけでなく、その過程でどの道具を使い、どういう意味の変化が起きているかを意識すると力がつきます。
友達と数学の話をしていたとき、単位行列の I がかっこいい理由を雑談で語ったことがあります。『I は「変えない人」だと思えばいいんだ。AI の A と掛けても IA = A になるのは、単位行列が“何も変えない基準”だから。もし I が混ざる場面を想像すると、他の操作の影響を素直に受けながらも、元の形を保つ救世主みたいな役割だとわかる』と。友だちは納得して、式の中での I の位置を探す遊びを始めました。結局、基本行列の組み合わせを理解する鍵は、この『何も触れない基準』の感覚だと思います。





















