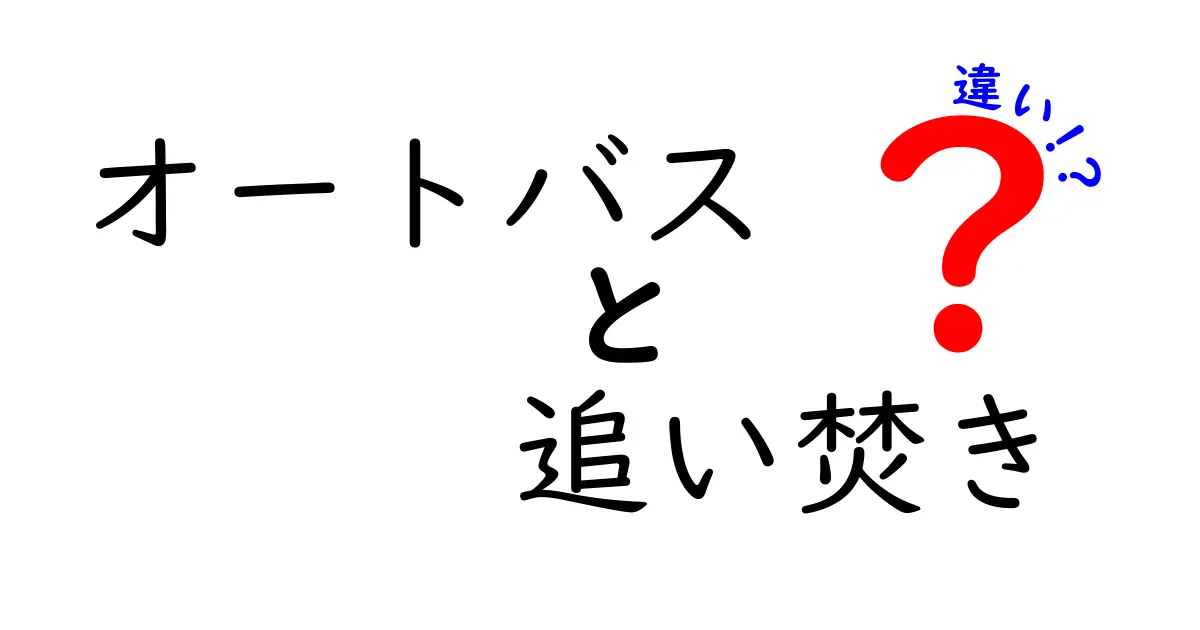

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
オートバスと追い焚きの基本的な違いを知ろう
日常の入浴を快適にするための機能にはいろいろありますが、中でもよく混同されやすいのが オートバス と 追い焚き です。まず覚えておきたいのは、両者は「役割が違う機能」であるということです。
オートバス は浴槽全体の温度を自動で保つ機能や、湯量・湯温の管理を行う仕組みを指します。設定温度に達すると自動で湯温を安定させ、入浴中の温度が下がりにくいように保温します。これにより、長時間お風呂に浸かっていても急な温度の変化を感じにくくなります。対して 追い焚き は「すでに入っているお湯をもう一度温める」行為そのものを指します。浴槽内のお湯を捨てずに、再度ヒーターを使って温度を上げるのが基本的な役割です。
このふたつの機能の違いを理解すると、「今日は温度を保ちたいのか」「今いるお湯をもう少し温めたいのか」という判断がすぐにつくようになります。オートバスは入浴中の一貫した快適さを狙い、追い焚きは必要な場面での温度再加熱を素早く行います。どちらを主に使うかは、ご家庭の人数・入浴の頻度・光熱費の考え方・給湯器の性能などに影響を受けます。
選択のポイント は大まかに三つです。まず第一に「家族の人数や入浴時間のパターン」。次に「追い焚きの回数や頻度が多いかどうか」。最後に「光熱費と初期費用のバランス」。この三つを比べて決めると良いでしょう。なお、最新の給湯器には オートバス と 追い焚き の両機能を組み合わせたモデルも増えています。これらの機器は操作が直感的で、設定温度を細かく変えることができる点が魅力です。
実生活での使い分けと注意点
実際の生活では、オートバス と 追い焚き、あるいはその組み合わせの使い分けをどのように行うかが重要です。まずは自宅の給湯器がどの機能を持っているかを確認しましょう。古い設備では片方しか搭載されていないことも珍しくありません。新しい機種は両機能を備え、温度設定を細かく調整できるものが増えています。
使い分けの目安としては、以下の点をチェックするとよいです。
- 家族人数が多く、湯温の安定を優先したい場合はオートバスが便利
- 湯がぬるくなるのを避けたい場面は追い焚きで再加熱
- 深夜の節約を考えるなら、時間帯設定や自動運転機能を活用
- 機器の年式によっては追い焚きの効率が劣ることがあるため、最新機種の検討も有効
さらに選択には設置環境も関係します。浴槽のサイズ、循環ポンプの能力、配管の長さなどによって、同じ機能でも実際の使い勝手が変わることがあります。施工費用と運用コストのバランスを考えることも忘れないでください。結論としては、家族構成・生活リズム・予算・住まいの設備状況を総合的に判断して選ぶのが最も賢い方法です。
ある日、友だちと風呂の話をしていて「オートバスと追い焚きって、実はどう違うの?」と聞かれたんだ。彼は最初「お風呂を温め直すのが追い焚きで、温度を保つのがオートバスだよね」と答えた。だけど、家によっては両方が同時に動くモデルもあるし、使い方次第で電気代も変わる。そこで私は、彼と実際の生活を想定して深掘りしてみた。朝は時間がなく、子どもが急いで入る家ではオートバスの安定感が助けになる。一方、夜は一人でゆっくり入りたいとき、追い焚きだけを使って安く済ませることも可能だ。結局、機械の性能だけでなく、家族のリズムと習慣、そして光熱費の考え方をどう組み合わせるかが大切だと感じた。





















