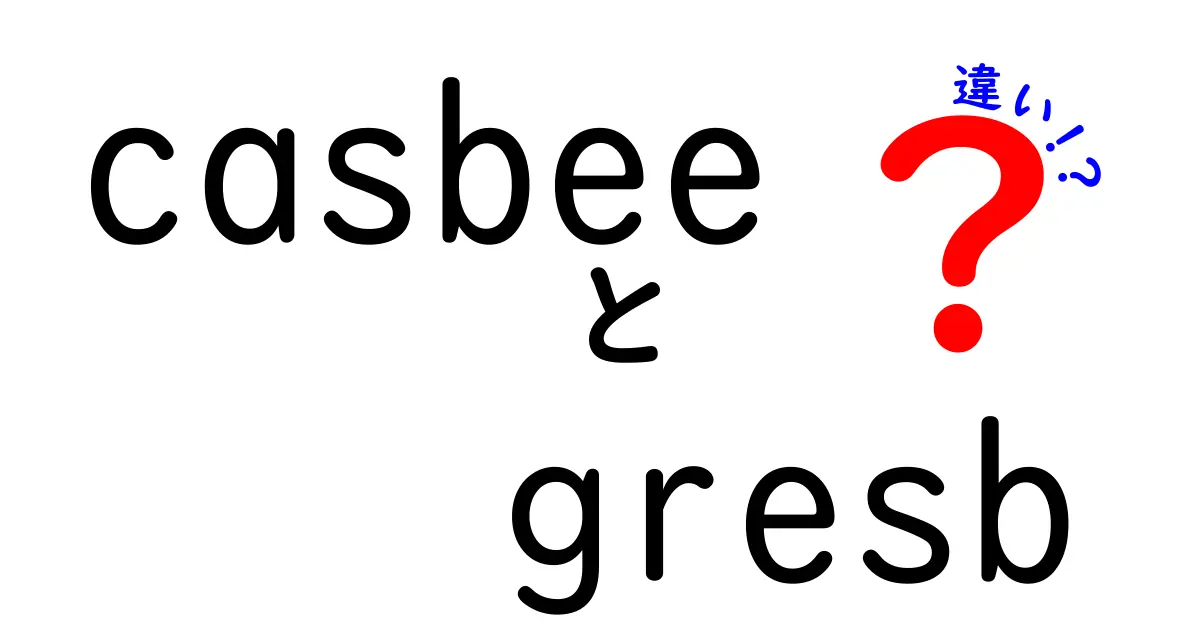

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CasBeeとGRESBの基本をざっくり整理
CasBee(Cas BEE、正式には CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency)は、日本で開発された建物全体の環境性能を評価する制度です。設計段階から運用・維持管理までの過程を総合的に見て、建物がどれだけ環境に優しいかを判断します。評価は建物個別を対象に行われ、結果は等級や点数として示され、認証としての形をとることが一般的です。
それに対してGRESB(Global Real Estate Sustainability Benchmark)は、世界規模の不動産セクターを対象とするベンチマークです。投資家やファンドなどの資産ポートフォリオ全体のESGデータを収集・比較し、パフォーマンスを数値化します。個々の建物よりも、ポートフォリオ全体の傾向や改善余地を見つけ出すことに向いています。
この二つは「環境評価」という共通の軸を持ちますが、対象の規模・評価の目的・活用方法が異なるため、それぞれの強みを生かして使い分けることが重要です。以下では、casbeeとgresbの基本、評価の核となるポイント、そして具体的な使い分け方を詳しく見ていきます。
まずは基本的な性質を整理してみましょう。CasBeeは日本市場に特化した建物単体の評価制度であり、建物の設計・施工・運用の各局面を総合的に評価します。一方、GRESBはグローバルな資産ポートフォリオを対象にしたデータ集約・比較の仕組みで、ESGの観点から投資家の判断材料を提供します。
この章の要点は以下のとおりです。
・CasBeeは建物単体の詳細な評価を重視する日本向け制度
・GRESBはポートフォリオ全体のデータと投資家視点のベンチマークである・両者は評価の対象と目的が異なるため、適した場面で使い分けることが重要・企業やファンドの実務では、両方を組み合わせるケースも増えている
CasBeeの特徴
CasBeeの特徴は、建物を対象として、設計・建設・運用の各段階から見た「環境性能の総合評価」を行う点です。評価は日本国内の法規制や地域特性、建物の用途(オフィス、住宅、商業施設など)に合わせて重みづけが変わることが多く、地域適応性が高いのが大きな強みです。
具体的には、エネルギー効率、CO2排出、 indoor environment(室内環境)、資材の環境影響、ライフサイクルの視点、地域の災害対応など、さまざまな要素を総合的に評価します。評価結果は星のような等級や点数で表示され、建物にとっての成功指標を明確に示します。
CasBeeは日本の建築市場に特化しており、自治体の導入事例や税制・補助金との連携がある場合も多いです。結果として、日本国内での建物認証・市場価値向上・長期的な運用コストの削減といった目的に直結します。
CasBeeを活用する際には、初期設計段階からデータを整備し、竣工後の運用データも継続的に記録することが重要です。定期的な見直しと改善の計画を立てることで、認証レベルの維持・向上を図ることができます。
総じて、CasBeeは建物の「設計と運用の品質」を高め、地域特性に合わせた具体的な改善案を提示してくれる制度です。強みは日本市場のニーズと最新の法規制動向に適合している点にあります。
GRESBの特徴
GRESBは、世界規模で不動産投資家・ファンドが利用するベンチマークであり、ポートフォリオ全体のESGデータを統一的に評価します。そのため、個別の建物を超えた「資産クラス横断」の比較が可能です。データは自己申告が中心となるケースが多く、データ品質の確保と透明性の担保が重要視されます。
GRESBは、マネジメント(方針・組織体制)、パフォーマンス(エネルギー・水・温室効果ガスの実績など)、データ品質・ガバナンスといった複数のモジュールで構成され、ファンド・ポートフォリオ・アセットのレベルでスコアが算出されます。結果として、投資家は業界全体のトレンドを把握し、改善優先度を戦略的に決定できます。
GRESBの強みは「グローバルな比較可能性」と「投資判断への直接的な影響力」です。世界各地の規制や市場慣行が異なる中でも、同じ指標セットで比較できるため、資産の国際的な評価基準を統一的に把握できます。
実務上は、データ収集の体制づくりとデータ品質の担保が最重要ポイントです。現場の温室効果ガス排出量・エネルギー使用量の計測、サプライチェーンの管理、テナントとの協働など、データの透明性と正確性を高める取り組みが求められます。これにより、GRESBのスコア改善に直結する具体的なアクションを特定しやすくなります。
比較と使い分けのポイント
CasBeeとGRESBは、目的が異なるため、同時に使うことで相乗効果を生み出しやすい組み合わせです。日本国内での建物認証を強化したい場合はCasBeeを優先し、資産全体のESG情報を投資家へ訴求したい場合はGRESBを活用します。以下のポイントを押さえると、実務での使い分けが明瞭になります。
1) 評価の対象: CasBeeは建物単体、GRESBはポートフォリオ全体が基本。
2) データの性格: CasBeeは設計・運用の品質に焦点、GRESBはデータの網羅性と比較可能性を重視。
3) 地域性: CasBeeは日本特有の法規・慣習に適合、GRESBはグローバルな基準で比較可能。
4) 出力形式: CasBeeは認証証明が主、GRESBはスコアやランキングが主要なアウトプット。
5) 更新頻度: CasBeeは竣工後の評価の更新が中心、GRESBは年次ベースでの更新が一般的。
このように、目的に応じて「建物レベルの認証」と「資産全体の比較・透明性確保」のどちらを優先するかを決めると、現場でのデータ収集や改善計画がスムーズになります。
実務での活用と注意点
実務でCasBeeとGRESBを活用する際の注意点を整理します。まず、データ基盤の整備が最優先です。CasBeeは建物ごとの詳細データ、GRESBは資産全体の統合データが求められるため、データの粒度と正確性を揃えることが不可欠です。次に、組織内の役割分担を明確化しましょう。データ収集担当、評価担当、報告担当といった役割分担を事前に決め、定期的なデータ更新スケジュールを設定します。さらに、ステークホルダーとの連携が重要です。テナント、管理会社、設計・施工のパートナー企業と協力し、エネルギー使用量の正確な計測・報告を行う体制を作ることが成果につながります。最後に、改善計画を具体的なアクションに落とし込み、費用対効果を検証します。短期的なコスト削減だけでなく、中長期的な資産価値の向上を見据えた施策を選択することが成功の鍵です。
総括すると、CasBeeは日本市場での建物の品質向上を、GRESBは世界市場での資産価値と透明性の向上を目指す道具です。両者を適切に組み合わせることで、建物の価値と企業の信頼性を同時に高めることが可能になります。
なお、最新の制度改定や地域の運用実務は日々更新されるため、公式ガイドラインのチェックと実務担当者間の情報共有を欠かさないことを強くおすすめします。
比較表
以下の表は、CasBeeとGRESBの主要な違いを分かりやすく整理したものです。表を参照して、どの制度をどの局面で使うべきかを判断してください。
以上がCasBeeとGRESBの大まかな違いと使い分けの要点です。目的に合わせて使い分けることで、建物の品質と資産の透明性を同時に高めることができます。
友だちA「CasBeeって日本の建物専用の評価だよね。GRESBとは何が違うの?」友だちB「CasBeeは個別の建物を、GRESBは資産全体のESGを見てるんだ。CasBeeは設計・運用の品質を日本の規制や地域性に合わせて評価する。一方GRESBは世界の投資家が資産を比較できるよう、データの透明性とガバナンスを重視している。だから、日本での建物認証を重視するならCasBee、投資家向けのポートフォリオ評価ならGRESBが主役になる。もし両方を使えれば、個別の建物の価値と資産全体の信頼性を同時に高められるんだ。なお、データの集め方や報告のルールは少し異なるから、担当者同士でしっかりすり合わせをすることが大事だよ。こうした違いを知っておくと、現場の意思決定が格段にスムーズになるんだ。
前の記事: « 熱波と猛暑の違いを理解して夏を安全に過ごすための基本ガイド





















