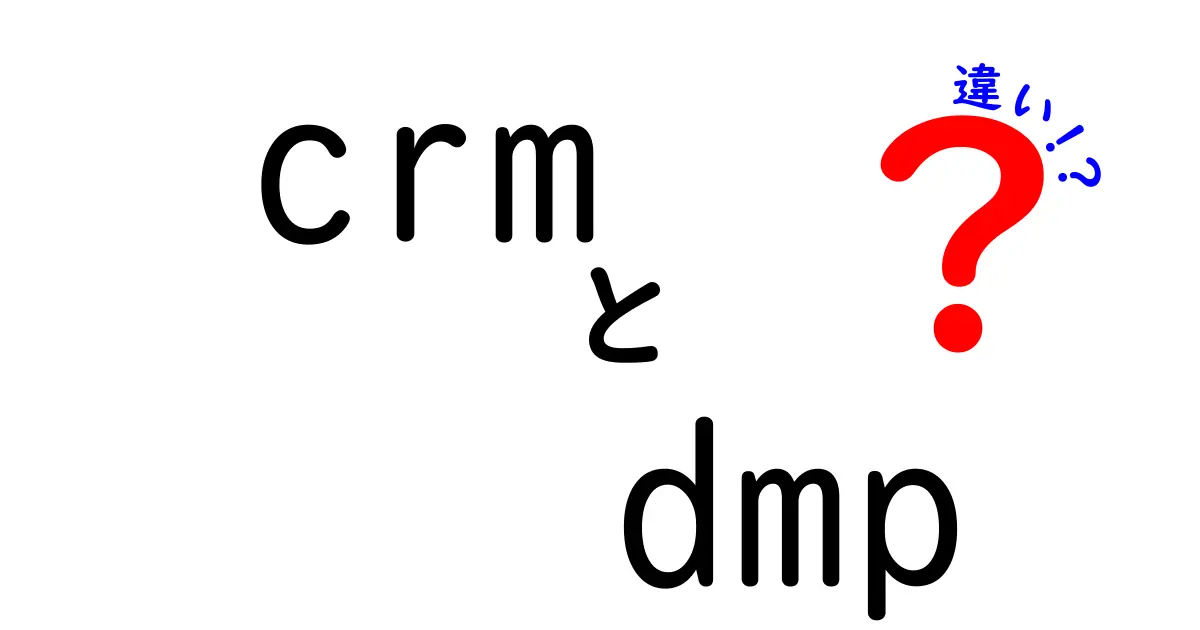

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CRMとDMPの基本的な違いをひと目で把握する
CRMとDMPは、企業が顧客データを活用して売上を伸ばすための重要な道具ですが、役割が異なります。まずCRM(Customer Relationship Management)は、個人を特定できる情報を中心に、顧客との関係を育てる仕組みです。販売担当者の連絡履歴、購買履歴、サポートのやりとり、見積もりのステータスなど、顧客ごとに紐づく情報を蓄積して、次のアクションを“個別最適化”します。CRMのデータは通常、企業の社内で管理され、販売・マーケティング・カスタマーサポートの現場が直接参照します。ここで大切なのは、データの粒度が細かく、顧客一人ひとりの履歴をつぶさに追える点です。反対にDMP(Data Management Platform)は、匿名データや推定データを扱い、ウェブサイトの訪問履歴や広告の接触状況などを集めて、広範囲のオーディエンスを一つのグループにまとめます。DMPは個人を特定しない形でデータを統合することが多く、複数のデータソースを横断して“誰に”ではなく“どんな行動をした人たちに”広告を届けるかを設計します。こうした違いは、データの起点や利用目的、そして組織の運用ルールにも大きく影響します。
具体的には、CRMは毎日の受注処理や顧客サポートの品質向上、リテンションを高める施策と結びつきやすい一方で、DMPはウェブ広告の効果改善・サイトの分析・新規オーディエンスの発見に適しています。さらに、データの寿命や更新頻度、プライバシー管理の観点でも差があり、組み合わせて使うことが多いです。企業はまず自分たちのビジネスの目標を明確にし、個人データの取り扱いに関する社内ルールと法規制を確認した上で、CRMとDMPの役割分担を設計します。
この段階での重要なポイントは、データの“出どころ”と“使い道”を分けて考えることです。CRMは顧客と直接的な関係性を育てるための核となる情報源として機能します。DMPはサイト訪問者の行動傾向を把握して、広告配信やパーソナライズの幅を広げる役割を果たします。
最終的には、両方を適切に連携させることで、個別対応の質を保ちながら、広範囲の市場にもアプローチできるようになります。ここまで読めば、CRMとDMPの基本的な違いと、それぞれが向く役割が見えてくるはずです。
実務での使い分けと注意点を深掘りする
実務での使い分けを考える際には、具体的なワークフローを想定するのが役立ちます。まずCRMは、営業やカスタマーサポートの現場で“個々の顧客”を中心に回る流れを整えます。顧客が問い合わせをしたらチケットを作成し、担当者が対応履歴を追記します。購買データは受注・決済・返品といったトランザクションデータと結びつき、リピートの可能性を高めるためのタイミング提案や、アップセルの機会を逃さず記録に残します。DMPは逆に、ウェブサイトの閲覧履歴やメール開封・クリックなどの行動データを集約します。広告予算を最適化するために、どのオーディエンスセグメントに広告を出すべきか、どのページの改善がコンバージョンにつながるかを分析します。これらを一つの企業戦略に落とし込むには、データガバナンスを意識することが不可欠です。データの取り扱い方針、同意管理、データの更新頻度、外部パートナーとの契約条件を明確にしておくことで、トラブルを避け、信頼性の高い施策を実行できます。さらに、CRMとDMPを連携させると、個人情報を守りつつ個別化を進められます。例えば、CRMで分かる顧客の嗜好をDMPのオーディエンスセグメントに反映させ、ウェブ広告は適切なタイミングで表示されるように設計します。この連携は、マーケティングのROIを高め、長期的な顧客関係の質を向上させます。具体例として、中学生でも理解できるレベルで言えば、学校の部活のように“個々のメンバーの得意分野を活かすチーム作り”と“全体の雰囲気や方針を整えるルール作り”の両方を上手に組み合わせる感じです。最後に、導入時の注意点として、ツールの機能だけに頼らず、組織の実務フローと人材のスキルを整えること、そしてデータの質を高めるルーティンを作ることを強調します。
koneta: 最近、友だちとCRMとDMPの違いについて雑談していて、DMPが広告の話題を広げる魔法の箱みたいに感じた反面、CRMは本当に個々の人に寄り添う道具だと再認識しました。DMPは匿名データを使って大きな塊を作るのが得意で、どんな人がどのページを見たかを眺めて最適な広告を出すのが仕事です。対してCRMは名前と顔と履歴がつながっていて、営業やカスタマーサポートが個別の対応を設計するための情報源になります。つまり、DMPは集団の行動を読み解き、CRMは個人の関係を深める。両方がうまく回ると、広告の適切さとサービスの質の両方を高められるんだよね。こうした話題は、データの使い方を考えるときの良いヒントになります。
次の記事: CDPとDMPの違いを徹底解説!初心者にも分かる選び方と使い方 »





















