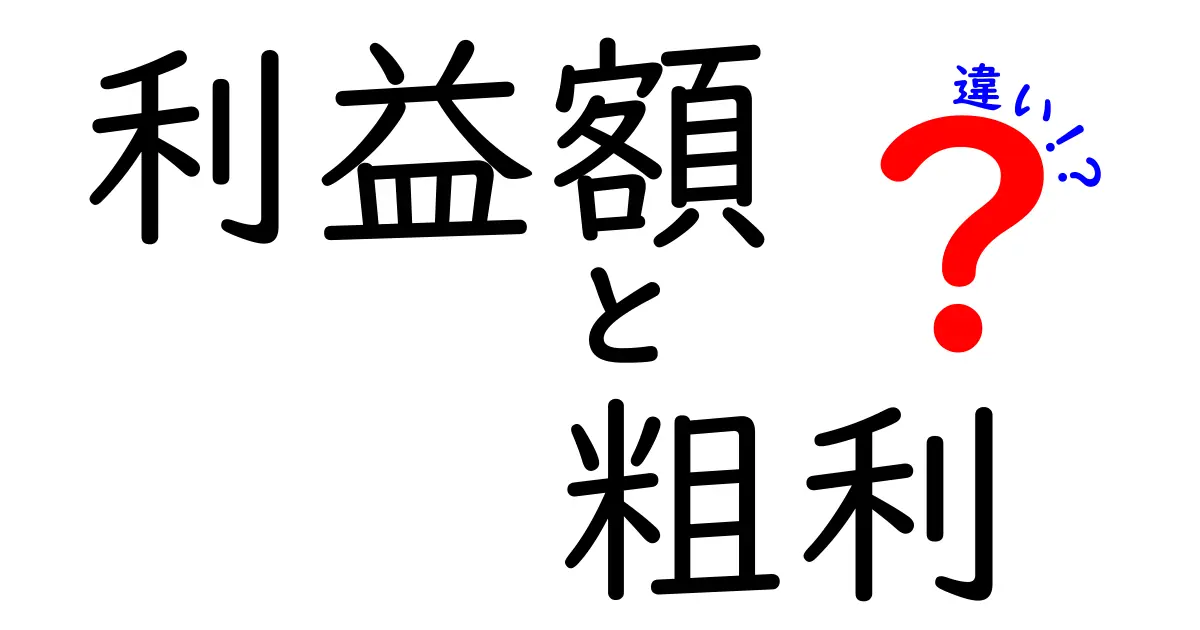

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
利益額と粗利の違いを理解する理由
私たちは会計の話をするときに「粗利」と「利益額」という言葉をよく耳にします。これらは似ているようで意味が異なる場面があり、混同すると判断を間違えやすくなります。まず、粗利は売上高から売上原価を引いた額です。つまり「商品を売ることそのものからどれだけ直接的に利益が生まれるか」を示す指標です。
その反対に、利益額という言い方は文脈によって意味が変わり得ます。多くの人は最終的に手元に残るお金、つまり純利益を指すことが多いですが、時には営業利益、経常利益など別の利益を指すこともあります。
この違いをはっきりさせておくことは、財務を読み解く力を養う第一歩です。数字だけを見て意味を取り違えると、企業の実力や状況を正しく判断できなくなります。
この違いを正しく理解しておくと、ニュースで見かける財務指標の解釈が正しくなり、商品やサービスの収益性を評価する際の判断材料が増えます。たとえば、ある商品の粗利が高くても、宣伝費や人件費などの費用がかさんでいれば、最終的な利益額は低下します。逆に粗利が低くても、固定費を抑えたり効率的な運用をしていれば、利益額が十分に確保できることもあるのです。
このような現象は、実務の現場で頻繁に起こるため、単一の指標だけを見て判断するのではなく、複数の指標を組み合わせて見る訓練が大切です。
粗利と利益額の違いを把握する鍵は「局所の収益と全体のコストを分けて考えること」です。粗利は売上の育成力を測りますが、最終的な利益は費用の管理や税金、財務の影響を含めた全体のパフォーマンスを映します。ここを押さえておくと、経営判断や財務分析がずっとわかりやすくなります。
定義と計算の整理:実務での使い分けと表での比較
ここでは粗利、営業利益、経常利益、純利益の順に定義と計算を整理します。まず粗利は売上高から直接費を差し引いた額です。直接費には原材料費や直接人件費、製造に関わる直接的な費用が含まれます。
次に営業利益は粗利から販売費及び一般管理費を差し引いた額となり、日常の事業活動でどれだけ利益を生んでいるかを示します。
経常利益は営業利益に加え、営業外の収益と費用を反映させた額です。つまり「本業以外の収入や費用」を加味した指標で、企業が通常の活動でどれだけ稼いでいるかを示します。
最後に純利益は経常利益から法人税等を差し引いた最終的な金額で、株主に還元されるのか、内部留保として蓄えるのかを判断する基準になります。
実務ではこれらを目的に応じて使い分けます。粗利は「商品力・価格設定の指標」として、営業利益は「日常の運営の健全性」、純利益は「財務の健全性・成長余力」を測る目安になります。複数の指標を同時に見ることで、単なる売上の多さだけではない本質的な強みや弱みを見抜く力が身につきます。
たとえば、ある期間の粗利が高くても、販管費が急増していれば営業利益は落ちます。逆に粗利が低くても、費用を抑える施策で営業利益を維持できる場合もあります。結局は、複数の指標を同時に見る習慣をつくることが、正しい意思決定につながります。
例の数値をもう一度手元で動かしてみましょう。売上高1000、売上原価600、販管費200、営業外費用50、法人税等100の場合、粗利は400、営業利益は200、経常利益は150、純利益は50です。このような計算の練習を日常的に行うと、数字の変化が現実の影響として直感的に理解できるようになります。
実務の現場では、これらの指標を使い分けて判断します。粗利は販売力の指標、純利益は財務健全性の目安、という観点を持つとよいです。さらに、数字を経営戦略に落とし込むには、期間比較や部門別分析も併せて行うと効果的です。
たとえば、ある期間の粗利が高くても、販管費が急増していれば営業利益は落ちます。逆に粗利が低くても、費用を抑える施策で営業利益を維持できる場合もあります。結局は、複数の指標を同時に見る習慣をつくることが、正しい意思決定につながります。
例の数値をもう一度手元で動かしてみましょう。売上高1000、売上原価600、販管費200、営業外費用50、法人税等100の場合、粗利は400、営業利益は200、経常利益は150、純利益は50です。このような計算の練習を日常的に行うと、数字の変化が現実の影響として直感的に理解できるようになります。
ある日、近所の友だちとこの話題で雑談をしていました。
友だちが「粗利って何?利益額とどう違うの?」と聞くので、私はこう答えました。
粗利は売上高から直接費を引いた額、つまり材料費や直接人件費など、商品づくりに直接かかった費用を引いた“手元に残る直接の利益”のことだよと。
すると友だちは「なるほど、じゃあ売上が多くても費用が多いと結局は減るんだね」と納得。私は続けました。
「でも利益額は文脈によって意味が変わることがある。最終的な利益、すなわち税金を引いた後の“実際に手元に残るお金”を指すことが多いんだけど、場合によっては営業利益のことを指す場合もあるんだ。」
この会話をきっかけに、私たちは粗利と利益額の違いを日常の話題に落とし込むようになりました。
そのうえで、「どうやって数字を組み合わせて判断するか」を深掘りしました。粗利が高くても固定費が多いと利益額は下がるし、粗利が低くても費用を抑えることで利益額を保てる場合もある。結局は、数字を断片として見るのではなく、全体の構造をつかむ視点が大事だという結論に至りました。
前の記事: « 受取利息と受取利息割引料の違いを徹底解説|会計の基礎から実務まで





















