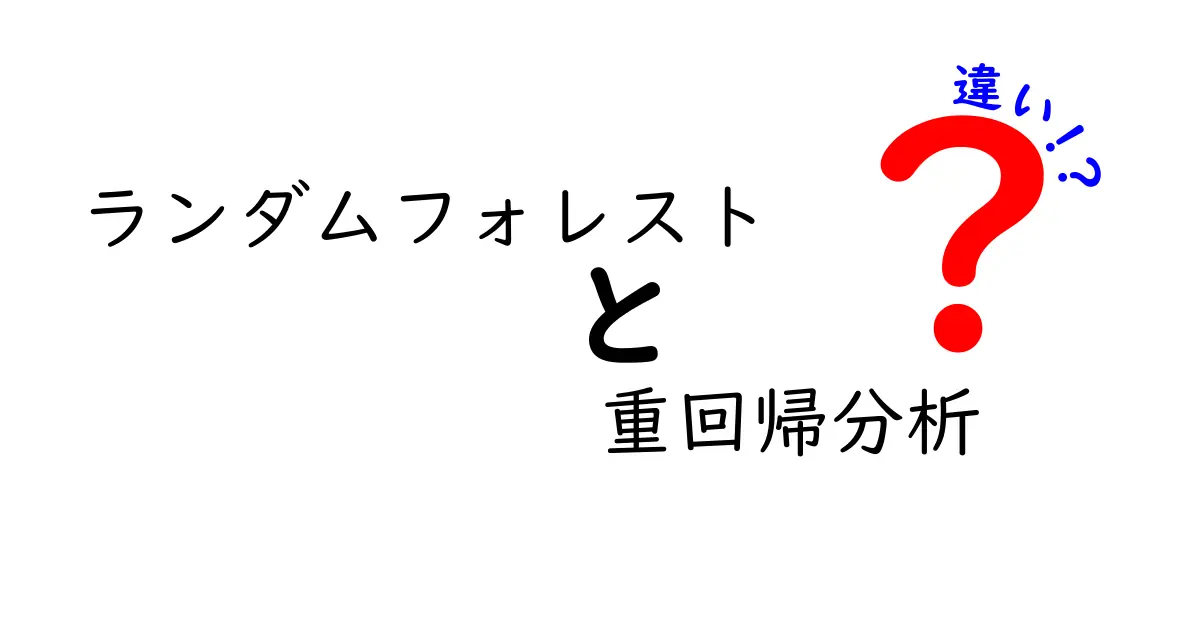

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ランダムフォレストと重回帰分析の違いを理解するための基本の話
このセクションでは、データを使って未来を予測する「方法」の違いを、身近な例と比喩を使いながら説明します。まず、ランダムフォレストと重回帰分析の基本的な考え方を押さえましょう。ランダムフォレストは、たくさんの決定木を組み合わせて答えを出す方法です。木はデータの特徴を順番に分けていく道筋を作ります。たとえば、テストの点数を予測するとき、"どういう科目が点数に影響するのか"を木が段階的に決めていく感じです。複数の木が意見を合わせるので、一つの木が間違っても全体として正解に近づくことがあります。これが非線形な関係や相互作用をうまくつかめる理由です。
一方、重回帰分析は、データの説明変数と目的変数との間に「線形な関係があるはずだ」という前提のもと、係数を使って予測します。係数は一つひとつ“この変数が結果をどれだけ引っ張るか”を示してくれるので、モデルの解釈がしやすいのが魅力です。ですが、現実の世界には「曲がったライン」や「変数同士の組み合わせの効果」など非線形な要素が混ざっていることが多く、そうした場面では重回帰だけではうまく予測できないことがあります。さらに、データが多いほど計算が重くなることがある点や、外れ値の影響を受けやすい点も覚えておくべきです。これらのポイントを踏まえると、二つの方法は「得意な場面が違う」ことが分かります。
この違いを知っておくと、データ分析の現場でどの手法を選ぶべきか判断しやすくなります。次のセクションでは、実務での使い分けのコツや注意点を具体的に見ていきましょう。
まずは「データの性質」を把握することがとても大事です。非線形な関係が強いと感じる場合はランダムフォレストが有効なことが多く、係数の意味を明確に知りたい場合や、説明責任のある場面では重回帰分析が向いています。データ前処理の要件や計算資源の制約も考慮して選ぶと、予測精度と解釈性のバランスが取りやすくなります。
実務での使い分けとポイント
実務では、データの性質や求めるものによって使い分けが変わります。大量のデータがあり、非線形の関係が複雑に絡む場合はランダムフォレストが強い味方です。特徴量が多くても、木の集合が平均化して過学習を抑えやすく、予測の安定性が高くなることが多いです。逆に、モデルの透明性を重視し、変数の影響をはっきり知りたい場合には重回帰分析が適しています。特に教育データや医療データのように、係数の意味を説明できることが求められる場面では有利です。データ前処理の観点では、ランダムフォレストは比較的手間が少ないことが多いですが、カテゴリカルな変数の扱い方や欠損値の扱いには工夫が必要です。一方、重回帰分析は線形性の検証、変数のスケーリング、欠損値の補完などが重要で、適切な前処理をしないと予測が乱れることがあります。評価指標としては、回帰問題ならRMSEやMAE、決定係数R2などを使い、交差検証を取り入れると過学習を防ぐ手助けになります。最終的には、実務の現場では「どのくらいの解釈性と予測精度が必要か」「データの性質はどうか」を合わせて選ぶと良いでしょう。
この理解を基に、次のような使い分けのコツを覚えておくと実務がスムーズに進みます。まずはデータを可視化して、非線形性や変数間の相互作用が強いかを確認します。次に、重要な変数の組み合わせがあるかを探すためにも、まずは重回帰分析で基準を作るのが有効です。続いて、非線形性が強いと感じた場合にはランダムフォレストを試してみて、性能を比較します。最後に、時間と計算資源が許すなら、他のアルゴリズムと組み合わせてアンサンブルを作ると、さらに堅牢な予測が得られる可能性が高まります。
友達と学習会の合間、過学習について話していた。私はこう言った。「過学習は、データのノイズまで覚えちゃって、テストデータでさえも正しく予測できなくなる現象だよ」。そこで、ランダムフォレストなら木を多く作って平均するので、単一の木が外れる場面を補い、過学習のリスクを抑えられることを深掘りした。けれど、木々の結論を全部説明するのは難しくなることもある。だから、場面に応じて説明可能性と予測力のバランスを取ることが大切だと結論づけた。
次の記事: AIPとAPSの違いを徹底解説:意味・用途・選ぶときのポイント »





















