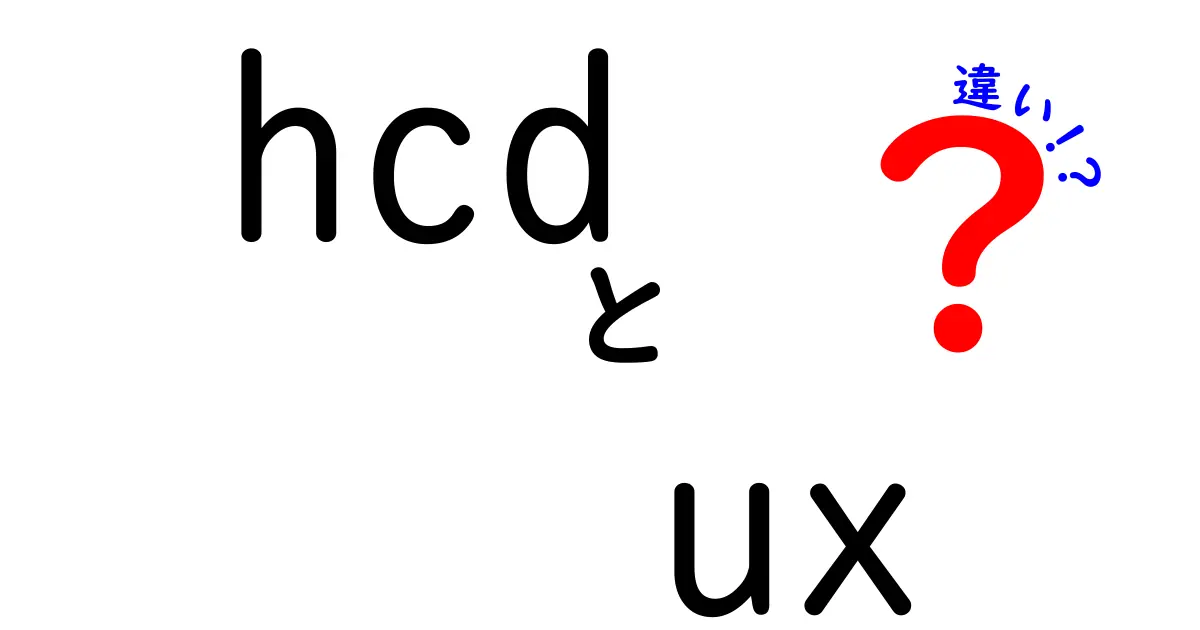

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
この章ではまず HCD と UX の基本をそもそも何なのかを整理します。HCD は人間中心設計の略であり、製品が生まれる前の段階から人の視点を最優先して設計を進めるやり方です。人の行動や文脈を観察し、利用者が抱える不安や動機を見つけ出し、それに合わせた解決策を作る過程を重ねます。UX はユーザー体験の総体を指し、製品を使うときの感情、思考、行動の連続を評価します。ここでポイントになるのは、HCD が設計の姿勢自体を決めるものであるのに対し、UX はその姿勢から生まれる体験の質を測る評価軸だという点です。
これらは別個の概念のように見えますが、実務では互いに補完し合い、同じゴールに向かいます。つまり、HCD の方法で得られた洞察を UX の評価軸に落とすことで、使われる場面や使われ方を深く理解できるのです。
ここから先では、HCD と UX の違いを具体的な場面に落とし込み、だれが、いつ、どんな決定を下すべきかを考えます。
違いと共通点を分解して理解する
HCD と UX の違いは、焦点とプロセス、成果の性質に現れます。まず焦点の違いです。HCD は人そのものとその文脈を中心に据え、どのような環境でどんな課題が生まれているかを理解します。これに対して UX は製品やサービスを使うときの体験全体を対象にします。次にプロセスの違いです。HCD は観察、共創、反復を基盤にした設計プロセスを強調し、ユーザーと直接対話する場面が多いです。UX は分析、デザイン、評価、実装といった段階を跨いで、最終的に体験の連続性を評価する役割を持ちます。これらは別個の概念のように見えますが、実際には同じ現場で一体的に動くことが多く、HCD の手法を取り入れることで UX の品質を高められます。
例えば新しいアプリを開発する場合、まずユーザーの行動を観察し、どんな課題が日常的に困難を感じさせているのかを記録します。すると、設計の軸が自然と決まり、UI が単なる見た目の改善ではなく使い勝手と意味づけの改善へと変わるのを感じられるはずです。
ここで重要なのは、共通点を忘れずに両者を組み合わせることです。どちらか一方だけに偏ると、技術的な美しさはあっても使い手の心を動かす体験にはつながりにくくなります。
この表を見れば、HCD と UX の関係が分かりやすく理解できます。言い換えれば人に寄り添う設計が体験を深め、体験の深さが事業の成果につながります。
企業や学校のプロジェクトでも、まずは人の暮らしを観察するところから始めると良いです。これが HCD の第一歩です。
現場での使い分けと実践のヒント
現場で HCD と UX をどう使い分けるかは、プロジェクトの目的と対象ユーザーの特性で決まります。短期間のアップデートで即効性を求められる場合には、UX の評価指標を先に設計し、仮説検証と反復を重ねます。一方で長期的な製品開発では HCD の深掘りが欠かせません。ユーザー訪問、ペルソル研究、共創ワークショップを組み合わせて、仕様の優先順位を決定します。
具体的な手順としては、1) ユーザー調査のゴールを明確にする、2) 痛みポイントを整理し共感マップを作る、3) 低コストのプロトタイプを作って検証、4) 体験の指標を設定して継続的に評価する、の4つが基本です。
これらを意識すると、設計と評価が分断されず、ユーザーが本当に求める体験へとつながります。さらにチーム運用のコツとして、異なる専門性を持つ人を早い段階で巻き込むことが大切です。開発者は技術制約を、マーケターは市場の動向を、現場のスタッフは日常の使われ方をそれぞれ持ち寄り、共創の場を増やしましょう。
HCD について友達と雑談してみた時の深掘りトークです。HCD は単に使いやすさを追求するデザインではなく、人の生活や価値観を理解して共感と意味づけを作る設計の考え方だよね。僕が学校のプロジェクトで感じたのは、観察と対話を通じて出てくる小さな真実が、機能の配置や言い回しを大きく変えるということ。たとえば機能 A を作るとき、設計者は何を解決したいのか最初に再確認する。その答えがユーザーの実際の行動と一致すると、使い心地が格段に良くなる。HCD の魅力はその再確認を繰り返す点にあり、ミスを早く見つけ、改善を小さく回せる点にある。





















