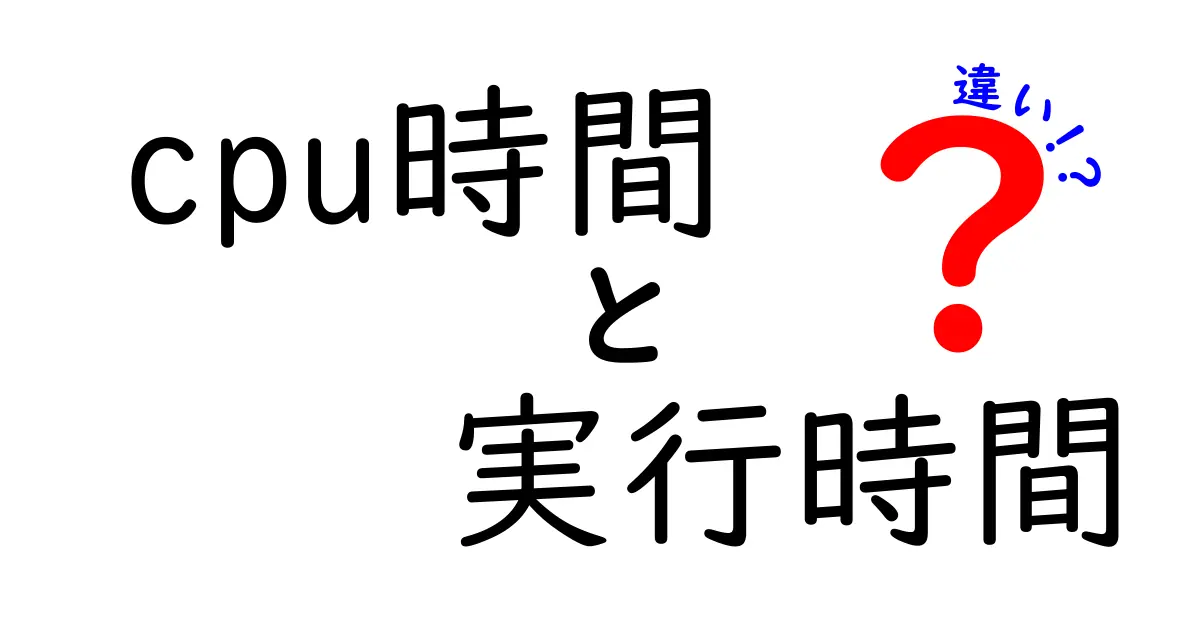

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
結論から押さえる:CPU時間と実行時間の違いを一言で
結論として、CPU時間と実行時間は同じ“時間”という言葉でも意味する範囲が全く違います。CPU時間はCPUが実際に作業として使った時間の総量で、実行時間は現実の時計が刻む経過時間のことです。プログラムを動かしているとき、CPUは計算を続ける一方でI/O待ちや睡眠状態にも入ります。
このときCPUが使われた時間は増えますが、壁時計は進み続けます。例えばファイルを読み込む操作をすると、CPUはファイルの読み出しに使われる時間と、カーネルの管理作業に使われる時間を足したものがCPU時間になります。
一方、開始時刻から終了時刻までの総経過時間は実行時間として計測され、外部資源の待ち時間を含みます。つまり、CPUが速くても外部の待機が多いと実行時間は長くなるのです。
この二つの指標を区別しておくと、どの部分の改善が必要かを正しく判断できます。
CPU時間とは何か:どこまでを測っているのか
まず基本の定義から。CPU時間とは、プログラムが実際にCPUを使って処理した時間の総計を指します。OSは通常、ユーザー時間とシステム時間の二つに分けて計測します。ユーザー時間は私たちが書いたコードがCPUで動作している時間で、システム時間はカーネルが動作している時間です。これらはプロセスごとに積算され、ディスクアクセスやネットワーク通信などの外部待ち時間は含まれません。したがって、アルゴリズムの計算の効率を測るには有効ですが、全体の体感速度を直接示す指標ではありません。
とはいえ、CPU時間を下げることは、計算処理の最適化に直結します。コードの複雑さを減らしたり、データ構造を見直したり、並列処理を導入したりすることで、CPU時間を短くすることが可能です。
実行時間とは何か:現実世界の経過時間
次に実行時間、通称 wall time について。実行時間は、プログラムを開始してから終了するまでの実世界の経過時間です。CPUが忙しく動いている間だけでなく、ファイルの読み込み待ち、ネットワークの応答待ち、他のプロセスへのスケジュール待ち、入力待ち、IO待ちなど、あらゆる外部要因を含みます。したがって、実行時間はユーザー体験の直感的な指標であり、同じ計算量でも待ち時間が長い場合には長くなります。
例えば、データベースから大量のデータを取得する処理では、CPUでの計算は短くてもディスクからデータを読み込む待ち時間が長いと実行時間は大きくなります。実行時間を短くするには、アルゴリズムの改善だけでなく、I/Oの最適化、キャッシュの活用、非同期処理の導入などが有効です。
この指標は最終的なパフォーマンスの指標として非常に重要であり、アプリケーションの応答性や全体の体感速度を判断する際の核となる値です。
実務での使い分け:どの指標をどんな場面で見るべきか
実務では、両方の指標をセットで見るのが基本です。
まず、CPU時間が高い場合は、アルゴリズムの計算量やデータ処理の実装を見直すべきサインです。コードのボトルネックを特定し、ループの最適化やデータ構造の変更、不要な計算の削減を検討します。
一方、実行時間が高い場合は、I/O待ちや外部資源の遅延が原因である可能性が高いです。ディスクI/Oの改善、キャッシュ戦略の導入、非同期処理の活用、ネットワーク待ちの緩和などが有効です。
下面の表は、指標の意味と典型的な原因を短く整理したものです。 指標 意味 典型的な原因 CPU時間 CPUが実際に使った時間の総計 複雑な計算、データ処理、アルゴリズムの非効率 ble>実行時間 開始から終了までの現実時間 ディスク待ち、ネットワーク待ち、スリープ、他プロセスの影響
このように、双方向の視点で分析を進めると、どこを改善すべきかがはっきりします。
また、実行時間とCPU時間の比率を計測することで、ボトルネックがCPU側かI/O側かを判断する手掛かりになります。
最後に、実務で大切なのは「状況に応じた適切な指標の選択」です。小さなアプリケーションなら実行時間の改善が最優先ですが、データ処理の重いバッチ処理ではCPU時間の削減が効果的なことも多いです。結果として、両方の指標を理解し、適切な最適化戦略を組み立てることが、安定したパフォーマンスを生むコツになります。
ねえ、CPU時間と実行時間の話、難しく聞こえるかもしれないけど、要するに「どれくらい CPU が働いたか」と「実際に時計が進んだ時間」を分けて考えるイメージだよ。友達と案を練るとき、計算だけ速くても待ち時間が長いと実際の体感は遅い、って話に近い。CPU時間を減らすにはアルゴリズムを賢くする、実行時間を短くするにはI/Oを減らす工夫をする――この二つの視点を持つだけで、プログラムのパフォーマンス改善がぐっと見えやすくなるんだ。





















