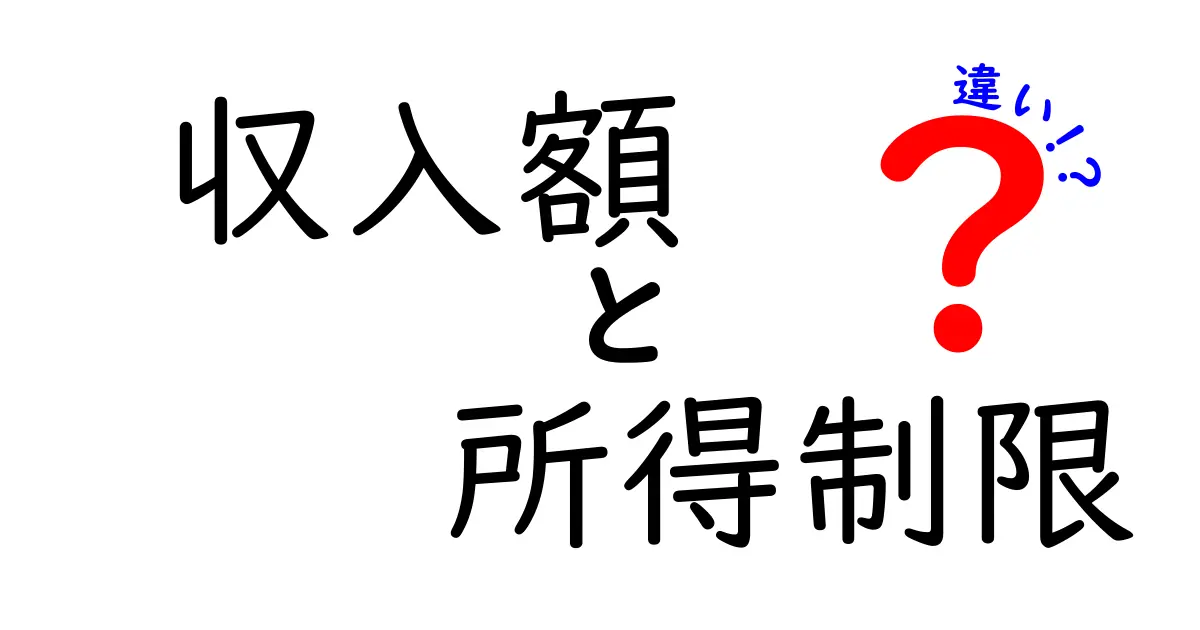

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
収入額と所得制限の基本的な違い
まず収入額とは、働いたり投資したりして得たお金の合計のことを指します。たとえば、給料やボーナス、おこづかい、株式配当などを合わせた額が収入額です。
一方、所得制限は、その収入額の中で特定の社会制度やサービスを利用するときに適用される制限です。所得制限は主に税金や福祉制度で使われ、一定の収入(正確には所得)を超えると利用できない場合があります。
つまり、収入額は持っているお金の合計で、所得制限はそのお金の基準によって使えるサービスを制限するルールだと言えます。これらは似ているようで意味が違うので、混同しないように注意しましょう。
収入額と所得のちがいについての説明
実は収入額と所得も違うものです。収入額は働いたり得たお金の総額ですが、そこから必要な経費や控除を差し引いたものが所得になります。
例えば、自営業の方が1,000万円の売上があっても、その中から材料費や経費500万円を差し引くと所得は500万円です。この所得額が所得制限を判断する基準になります。
所得は税金計算や社会保障の適用、所得制限に直接関係し、収入額だけでは判断できません。
このように収入額が大きくても、所得制限の判断には所得額が重要な役割を果たしています。
所得制限がある制度の具体例と影響
所得制限は主に国や自治体が行う様々な制度で使われています。
例えば:
- 児童手当
- 医療費助成
- 生活保護
- 奨学金の免除や給付
これらの制度は所得が一定の基準を超えると、受けられなくなったり給付額が減ったりします。
所得制限の例
これにより、収入は多くても経費や控除が大きくて所得が低ければ助成を受けられる場合があるということですね。
まとめ:収入額と所得制限の違いを理解しよう
今回のポイントは収入額は得たお金の総額、所得制限は所得(収入から経費等を差し引いた額)を基に決まる、ある制度の利用条件だということです。
収入だけを見て判別するのは難しく、具体的には所得額を正しく計算して判断します。
社会保障や税制の利用の際には、「収入額」と「所得制限」の違いを理解しておくと、正しく制度を活用できます。
ぜひこの記事を参考に、しっかりと違いを覚えておきましょう。
「所得制限」という言葉、実はちょっと曖昧に使われがちなんです。所得って単に収入のことかと思いきや、実は収入から必要な経費を引いたもの。たとえば自営業の人は経費が多いと収入が高くても所得は意外と低いことも。だから所得制限を考えるときは、収入額だけじゃなく、経費や控除も大事なんですよ。こういうポイントを押さえておくと、社会制度の利用条件がもっと分かりやすくなるんです。意外と知られていないけど大切な話ですね。





















