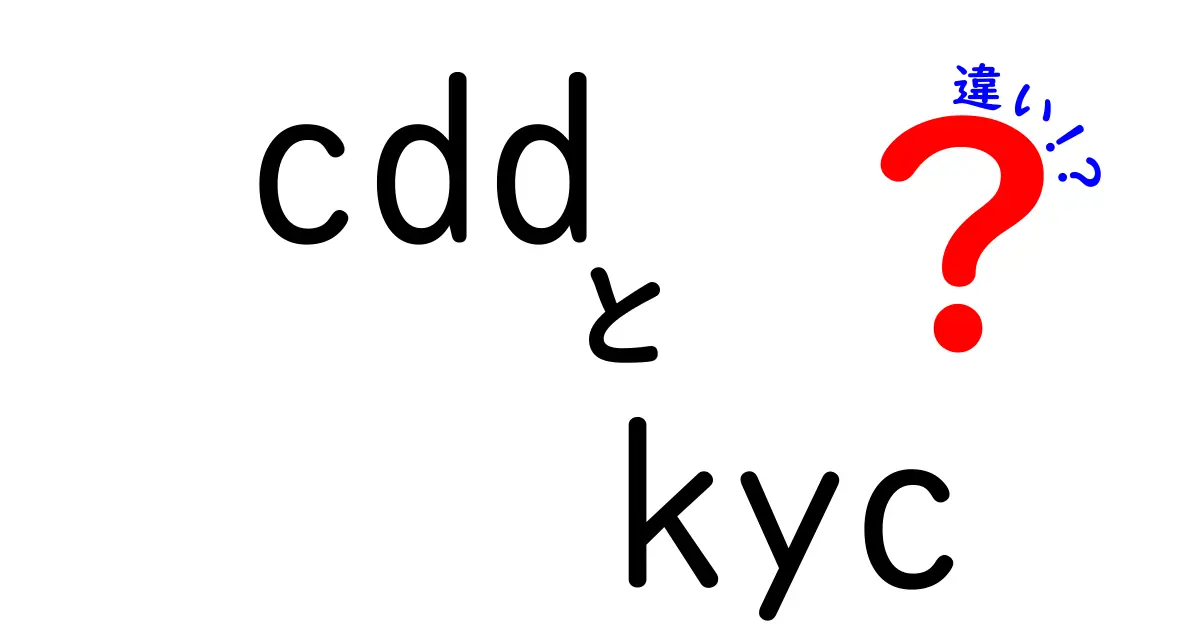

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CDDとKYCの違いを知ろう
金融機関ではお客さまの身元を確かめ、資金の流れが正しいかを見守るための仕組みがいくつもあります。その中でも特に覚えやすいのが KYCと CDD です。KYCは Know Your Customer の略で、「あなたは誰ですか」を確認する基本的な方針です。具体的には本人確認の資料を集め、名簿のように情報を整理して、適切な手続きでリスクの低い人から対応します。これに対してCDDは Customer Due Diligence の略で、顧客に対して“どれくらいのリスクがあるか”を調べるための具体的な調査・確認の方法を指します。
つまりKYCが全体像、CDDがリスクベースに沿った実務的な手順だと覚えるといいでしょう。以下にもう少し詳しく見ていきます。
まず基礎のポイントとして、KYCとCDDは同じ目的を持つ二つの枠組みです。目的は「お金が正しい人の手から正しい目的で動くか」を確かめることです。これを軽く説明すると、KYCは顧客を知るための方針と基本的な手続きの集合、CDDはその方針の中で“高いリスクや特定の条件を持つ顧客に対して行う詳しい調査”ということになります。中には EDD(Enhanced Due Diligence)というさらなる厳格化の仕組みもあり、リスクがさらに高い場合に用いられます。
この違いを実務に結びつけると、日常の銀行窓口やオンライン申請で見かける「本人確認」「資金の出どころ」「取引目的の説明」などの要素が、KYCとCDDのどちらに該当するのかが分かるようになります。
以下のポイントを押さえると、初心者でも理解しやすくなります。
- KYCは全員に適用されるべき基本ルールで、初回の登録時に必須情報を確認します。
- CDDはリスクが高いと判断されたときに発動する詳細な調査で、追加情報の提出を求めます。
- リスクベースのアプローチを取り、規模の大きい取引や不審な動きがあればEDDへ移行します。
- 企業間取引や国際送金では、CDDとKYCの両方が厳しく適用されることが多いです。
このように、KYCとCDDは似たような言葉ですが、使われ方や意味には区別があります。違いを理解することで、どうしてこの手続きが必要なのか、どんな情報を集めればよいのかが見えやすくなります。
実務での違いと具体的な手順
次に、現場での実務的な違いを、もっと具体的な手順のイメージで説明します。KYCの基本は「顧客を正しく識別し、リスクを評価すること」です。これは銀行窓口やオンライン口座開設のときに、本人確認書類の提出、氏名・住所の照合、過去の取引履歴の確認などを含みます。これらは一度の手続きで終わるのではなく、取引が続く間も監視し続けるのが特徴です。
一方、CDDはリスクが高いと判断された顧客に対して、追加の情報を求め、資金の出どころ・取引目的を詳しく確認するための追加情報を求める(CDD)ことが中心になります。
例えば大きな金額の送金が複数回あったり、出身国がリスクの高い国だったりする場合には、追加の資料提出を求め、取引の正当性を確認します。
この実務は「リスクベース・アプローチ」と呼ばれる考え方で動きます。リスクが低い顧客には最小限の確認で済ませることもありますが、リスクが高いと判断された場合は情報の深掘りが必要です。
EDDはCDDの中でも最も厳格なカテゴリーで、資金の合法性を厳しく検証するための追加資料・調査を求めることになります。
このように、CDDはリスクが高いほど情報の量と質が必要になる点が大きな違いです。
具体的な手順の整理として、次のような流れが一般的です。
1) 取引のリスク分類をして、どのレベルの調査が必要かを決める。
2) 本人確認を含む基本情報の収集を実施する。
3) 資金の出どころ・取引目的を確認するための追加情報を求める(CDD)。
4) 取引が継続する間、監視・レビューを継続する。
5) 高リスクにはEDDを適用する。
この流れを覚えておくと、日常の金融手続きがなぜ厳しくなるのかが分かりやすくなります。
最後に、実務での留意点をひとつ挙げます。情報は正直かつ最新のものを提出することが大切です。提出された情報が古かったり不正確だったりすると、後で調査が難しくなり、手続きが遅れる原因になります。常に「自分が何を説明して、なぜそれが必要なのか」を意識して対応しましょう。
友達とカフェで雑談しているような口調で深掘りします。KYCは“Know Your Customer”の頭文字で、銀行があなたを正しく識別し、信頼できる取引かを判断するための基本的な仕組みです。これだけを聞くと“身元確認”だけを想像しますが、実際には本人確認の書類を集めるだけでなく、取引の背景を見てリスクを評価する作業全体を含みます。一方CDDはそのKYCの中の“高度な調査”の部分です。資金の流れや出所、取引目的を詳しく確認することで、マネーロンダリングや不正を未然に防ぐ役割を果たします。つまりKYCは全体像、CDDは状況に応じて踏み込む深掘り、という関係です。必要な情報は状況に応じて変わるので、質問を分解して“何を知りたいのか”を整理する癖をつけましょう。
次の記事: 横領と背任の違いを徹底解説|実務での見分け方と事例のポイント »





















