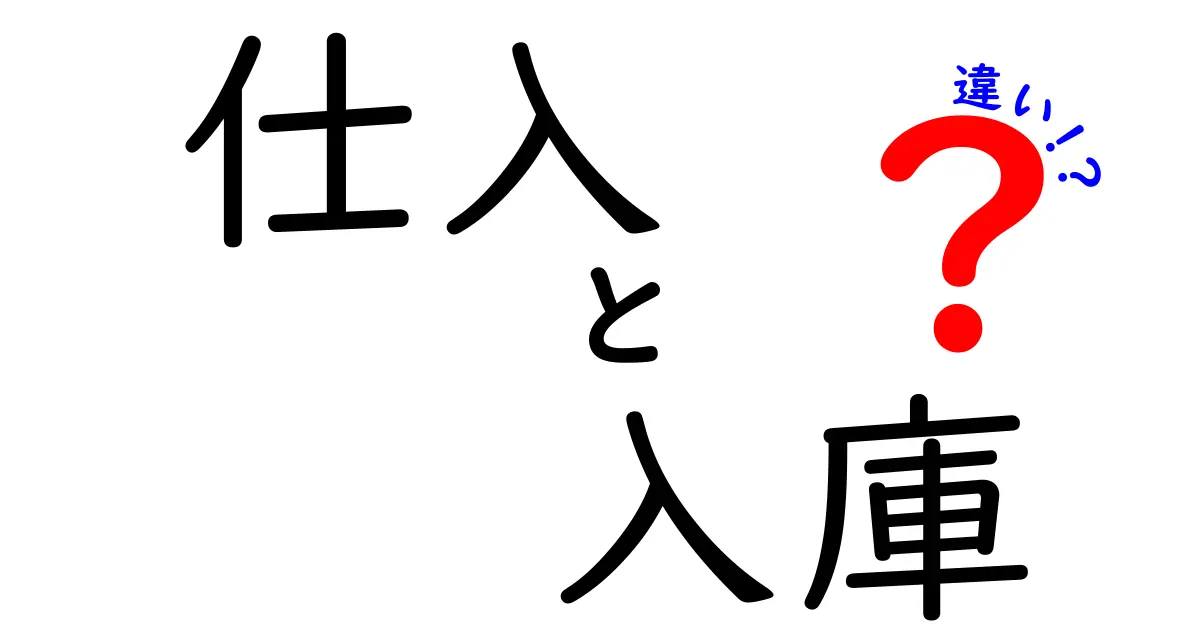

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
仕入と入庫の基本を整理する
仕入と入庫は日常の仕事の中でよく出てくる言葉ですが、意味をはっきり区別できていない人も多いです。
ここでは、まずそれぞれの定義を分かりやすく整理します。
仕入は商品を外部の供給先から手に入れる行為であり、会社の売上原価を作るための第一歩です。
一方、入庫はその商品が実際に自社の倉庫に到着し、在庫として管理できる状態になることを指します。
つまり、仕入は「買う行為」そのものであり、入庫は「貯蔵を始める実務の瞬間」です。
こうした違いを理解していないと、会計の科目計上や在庫数量の把握で混乱が生じます。
以下では、さらに詳しい違いと実務の流れを見ていきます。
まず大切なポイントは仕入は費用計上と密接している点です。
企業は仕入原価を計上し、在庫として保有すれば資産として扱います。
したがって仕入のタイミングと入庫のタイミングを分けて管理することで、原価計算と在庫管理の両方を正確に行えるようになります。
ここを曖昧にすると、月次決算で実績と予算のズレが大きくなり、上司や顧問と話すときに焦る原因になります。
実務では、仕入伝票と入庫伝票を分けて処理し、検品が済んだ時点で入庫の完了とみなすケースが多いです。
これにより、発注と入庫のタイミング差を把握でき、在庫の過不足を早期に発見できます。
実務の流れとポイント
この項目では、仕入と入庫の関係性を現場感を交えて整理します。
仕入は外部の取引先から商品を購入する行為であり、発注書や仕入伝票が先行することが多いです。
入庫は実際に商品が倉庫に到着して棚に置かれ、在庫として数えられる状態になることを指します。
つまり、仕入は「買う行為」、入庫は「貯蔵を始める行為」であり、両者のタイミングは必ずしも同じではありません。
この違いを守ることで、原価計上と在庫管理の両方を正しく把握できます。
実務では、発注→納品→検品→入庫→会計処理の順に動くケースが一般的です。
ここで覚えておきたい3つのポイントを挙げます。
1. 発注と入庫のタイミング差を管理する
発注時点と入庫時点を分けて管理することで、未着の仕入れや在庫過剰を早期に発見できます。
2. 検品と数量照合を徹底する
到着時の検品で数量と品質を確認し、差異があれば原因をすぐ追跡します。
3. 会計と在庫の整合性を保つ
入庫伝票の処理と会計処理をセットにして行うと、数字のズレが減り経営判断が安定します。
友人Aと雑談していたときのことだ。彼は仕入と入庫の違いがよくわからないと言っていた。私はこう返した。
「仕入は外部から物を買う行為、入庫は実際に倉庫に置く作業。発注と入庫の間には必ずずれがあることが多いんだ。」
彼は「買うだけじゃなくて受け入れて数えるまでがセットなんだね」と納得し、ノートに図を書き始めた。これで次の授業の“在庫と会計の結びつき”が見えると言って笑った。





















