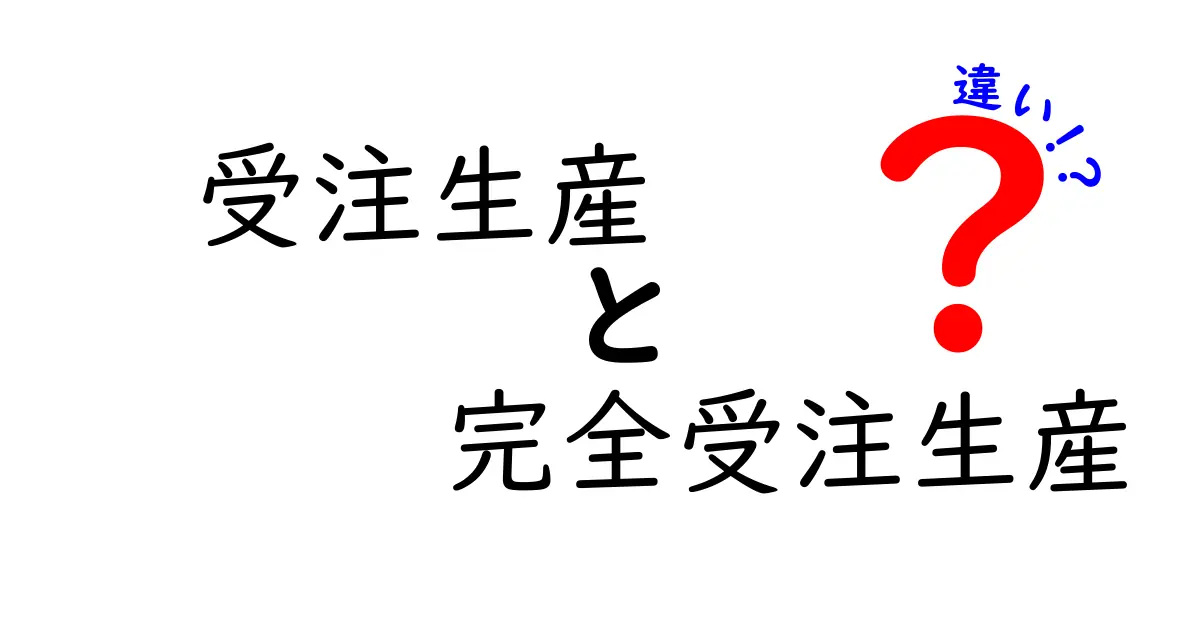

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
受注生産と完全受注生産の基本を押さえよう
受注生産と完全受注生産は、物を作るときの考え方を示す言葉です。両者とも注文を受けてから作る点は似ていますが、実務に影響する細かな仕組みが異なります。まずは基礎をしっかり理解しましょう。
受注生産は、顧客の注文を受けてから製造を開始します。需要の動きを見ながらロットを組むことが多く、在庫を大きく持たずに済む場合が多いのが特徴です。これにより、在庫コストを抑えつつ柔軟性を保つことができます。
一方、完全受注生産は、注文が確定して初めて材料の発注や加工を進める方式です。完成品の在庫をほぼ持たず、顧客一人ひとりのニーズに合わせたカスタマイズが可能になります。
ただし、この場合は納期が長くなりがちで、顧客には待ち時間が発生します。納期管理が難しくなることもあるため、需要の見通しをどう立てるかが大きな課題です。
この2つの違いを理解するには、業界の特性や製品の性質、需要の安定性、競合状況などを考えることが大切です。
例えば、部品が標準化されていて大量生産が成立する分野では受注生産が適していることが多いです。反対に、オーダーメイドや高いカスタム性が求められる製品では完全受注生産が適している場合が多いです。
自社のビジネスモデルに合う選択をすることが成功の鍵です。市場の変化に対応するためには、在庫コストと納期のバランスをどう取り、顧客満足をどう確保するかを考える必要があります。ここでの判断が、キャッシュフローや納期の安定性、顧客の信頼感に直結します。
違いのポイントを詳しく比較する
ここでは、実務で重要になる4つの観点から両者を比較します。
- 在庫リスク:受注生産は在庫リスクを抑えやすく、完全受注生産は基本的にゼロ在庫を目指します。
- リードタイム:受注生産は需要動向に左右されるものの短縮の工夫が可能です。完全受注生産は通常、納期が長くなりがちです。
- 初期コスト:受注生産は比較的低めの投資で始められることが多いですが、完全受注生産は高度な設備や柔軟な生産ラインが必要になる場合があり初期コストが高いことがあります。
- カスタマイズ幅:受注生産は標準化と適応のバランスを取りやすいのに対し、完全受注生産は高いカスタマイズ性を実現しやすいです。
この4つの観点を自社の状況と照らし合わせると、どちらの方式が適しているかの判断材料になります。
以下の表は、基本的な違いをひと目で把握するための要約です。
結論としては、在庫を抑えつつ柔軟に対応したい場合は受注生産、顧客の細かい要望に合わせた高いカスタマイズと品質管理を優先したい場合は完全受注生産が有効です。どちらを選ぶにしても、需要予測の精度とサプライチェーンの強さが決定的な要素となります。
koneta: 友達のミキと私の会話風に進めます。ミキ「受注生産と完全受注生産ってどう違うの?」僕「基本は同じく注文を受けてから作る点だけど、現場の動きが違うんだ。受注生産は需要の波を見ながら在庫を最小限に抑える柔軟な生産。ミキ「在庫を減らせるっていいね」僕「そう。ただし納期は比較的短くなることが多い。完全受注生産は注文が確定してから材料を動かすので、在庫はほぼゼロ。だからカスタマイズはしやすいけど納期は長くなる可能性が高い。ミキ「じゃあ、急ぎの人には受注生産、こだわりのある人には完全受注生産って感じ?」僕「その通り。市場や製品の性質、需要の安定性を見て使い分けるのがコツだね。実務では、需要予測とサプライチェーンの強さが勝負を分ける。僕らの中学生でも分かるポイントは、在庫コストと納期のバランスをどう取るか、そして顧客満足をどう保つかということだよ。結局は、ビジネスモデルに合わせた最適解を見つけることが大切なんだ。





















