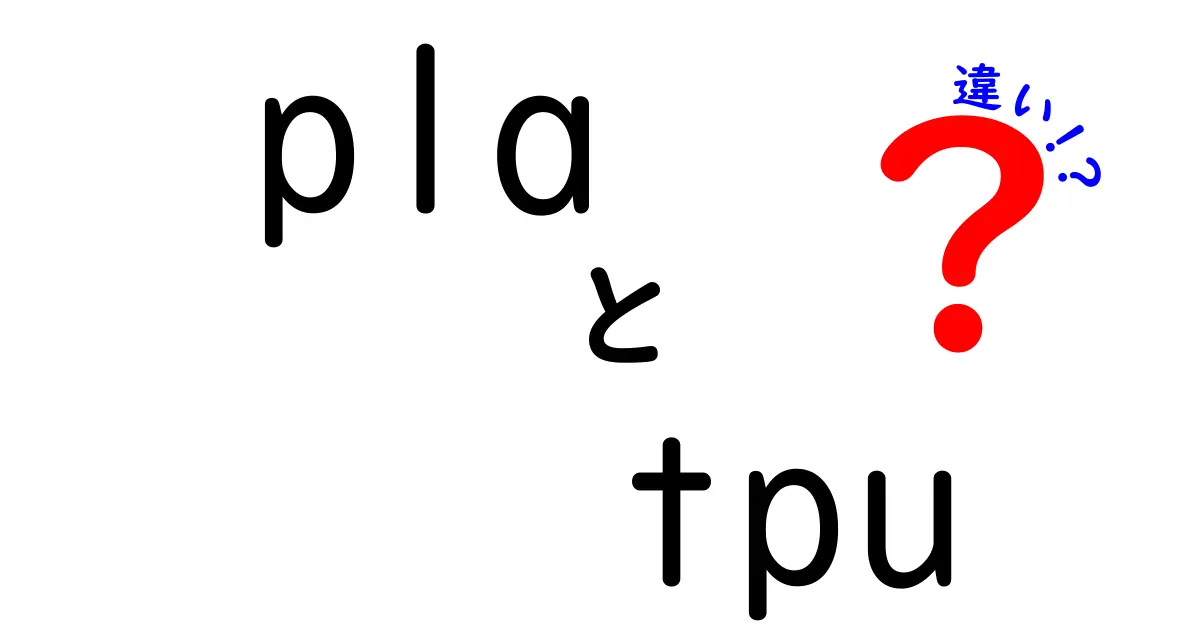

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
初心者必見!PLAとTPUの違いを徹底比較ガイド
このページでは PLAとTPUの違い を分かりやすく解説します。3Dプリンタを始めたばかりの人にとって、材料選びは作品の仕上がりを大きく左右します。PLAは硬めで扱いやすい定番素材、TPUは柔軟性と耐摩耗性を両立させる部材向きの素材です。どちらを選ぶべきかは、作りたいものの用途と求める手触り、強度、耐久性によって変わります。以下の章では、それぞれの特徴を詳しく比較し、実際の印刷時に気をつけるポイントやトラブル対処法を紹介します。初心者でも読みやすいように、具体例とコツをたくさん盛り込みました。
最後まで読めば、作品に最適な素材を迷わず選べるようになります。
PLAとは何か?特徴と向く用途
PLAはポリ乳酸という生分解性の素材で、プリント時の挙動は安定しており、層の積み重ね方が綺麗に出やすいです。溶融温度が低く、ノズル温度は180〜210度程度が目安とされます。
冷却が効くため、薄い壁やサポートが少ない形状にも向くことが多いです。印刷時にはヘッドの移動が滑らかで、ウォームアップの時間が短いので初心者におすすめです。欠点は熱に弱く、衝撃で割れやすいことや、長時間の荷重がかかる部品には向かない点です。匂いが少なく、周囲の機材への影響も比較的少ないのが特徴です。PLAは透明度の高い種類もあり、建築模型や装飾品、プロトタイプの作成に適しています。
TPUとは何か?特徴と向く用途
TPUは熱可塑性ポリウレタンという素材で、ゴムのような柔軟性と弾性を持ちます。印刷条件はPLAより難しく、ノズル温度は210〜230度程度、ベッド温度は50〜60度程度が目安です。TPUは曲げても元に戻る性質があり、靴の穴やケース、可動部品などの衝撃を吸収する部品に向いています。薄くて細い壁や長いチューブ状の形状は特に難しく、プリンタの機構や熱管理の影響を受けやすいです。TPUを安定させるコツとしては、引っ張りやすい素材なのでフィラ率を低めに、印刷速度を遅めに設定すること、エクストルーダーの供給を一定に保つことが挙げられます。実際の製品づくりでは部品の柔軟性と耐久性を両立させるための微調整が必要です。TPUは難易度が高い反面、柔らかさや耐久性を活かせる創作の幅が広くなります。
慣れるとぬいぐるみ(関連記事:アマゾンの【ぬいぐるみ】のセール情報まとめ!【毎日更新中】)のように柔らかい部品や衝撃を吸収するケースなど、PLAでは再現しづらいアイデアが実現します。
印刷性と仕上がりの比較
PLAとTPUの大きな違いは性質と印刷条件の両方にあります。PLAは高精度で表面が美しいのが特長で、複雑な形状の再現にも適しています。ノズル温度と冷却条件を適切に設定すれば、階層の縁も滑らかに出やすいです。一方のTPUは柔軟性があり厚みのある部品でも形状を保持しやすい一方、壁の薄さや長尺の部品は反りや層の剥がれが起きやすいです。印刷中はベッドの温度管理やエクストルーダーの供給安定性が重要で、速度を落とし、適切なリトラクション設定を使うことがコツになります。美しい仕上がりを狙うならPLA、柔軟性と耐衝撃性を優先するならTPUと覚えるとわかりやすいでしょう。
用途別の選び方と失敗を避けるコツ
用途に応じて素材を選ぶことが最も重要です。小さな部品で形状を重視する場合はPLAを選ぶと作業が楽です。機能部品で曲げや衝撃を受けるものはTPUの方が適しています。失敗を避けるコツは、設定を一度に大幅に変えず、温度と速度を段階的に調整することです。PLAは冷却を強くかけすぎると縁が割れることがあるため適度に冷却し、TPUは詰まりを防ぐためノズル温度と供給安定性を優先します。もう一つのポイントはベッドの温度管理です。PLAは室温付近でも印刷が安定しますが、TPUは床板の温度が低いと接着が悪くなりやすいです。
初心者はまずPLAで基本的な形を練習し、慣れてきたらTPUの柔らかさを活かした作品に挑戦すると良いでしょう。
実践的な印刷のコツと注意点
実際の印刷で成功率を上げるコツをまとめます。PLAはノズル温度と冷却のバランス、TPUは供給安定とエクストルーダーの圧力制御が鍵です。PLAは初期の設定をそのまま試してOKな場合が多いですが、TPUは機械の個体差が大きく、事前に機械のベンチマークテストを行いましょう。印刷時はガイドローラーの張り具合やベッドの接着剤の選択にも気をつけると、剥がれを防げます。失敗例としてはTPUのノズル詰まり、PLAの層間の不均一、いずれも発生しますが、温度と速度の微調整でかなり改善します。最終的には、素材の特性を理解したうえで自分のプリンタに最適な設定を見つけることが長期的な成功につながります。
この章を読み終えれば、初めての作品でも安定して仕上げられるようになるはずです。
今日は友達とTPUの話をしていて、柔らかさのある部品の作り方について雑談になりました。TPUは確かに難しい素材だけれど、設定さえ掴めば驚くほどの弾力や耐久性を持つ部品を作ることができます。私が最初に壁にぶつかったのは、ノズル温度と印刷速度のバランスでした。低速で押し出すと詰まりやすく、高速だと連続的な押し出しが難しくなる。そこで友達と話し合って、まずは温度を少しずつ上げる実験を重ね、次にエクストルーダーのトルクを安定させる設定を探しました。徐々に均一な押し出しが得られ、柔らかく弾力のある部品が形作れるようになったのです。TPUを使いこなすには、根気と試行錯誤が大切だと実感しました。\n





















