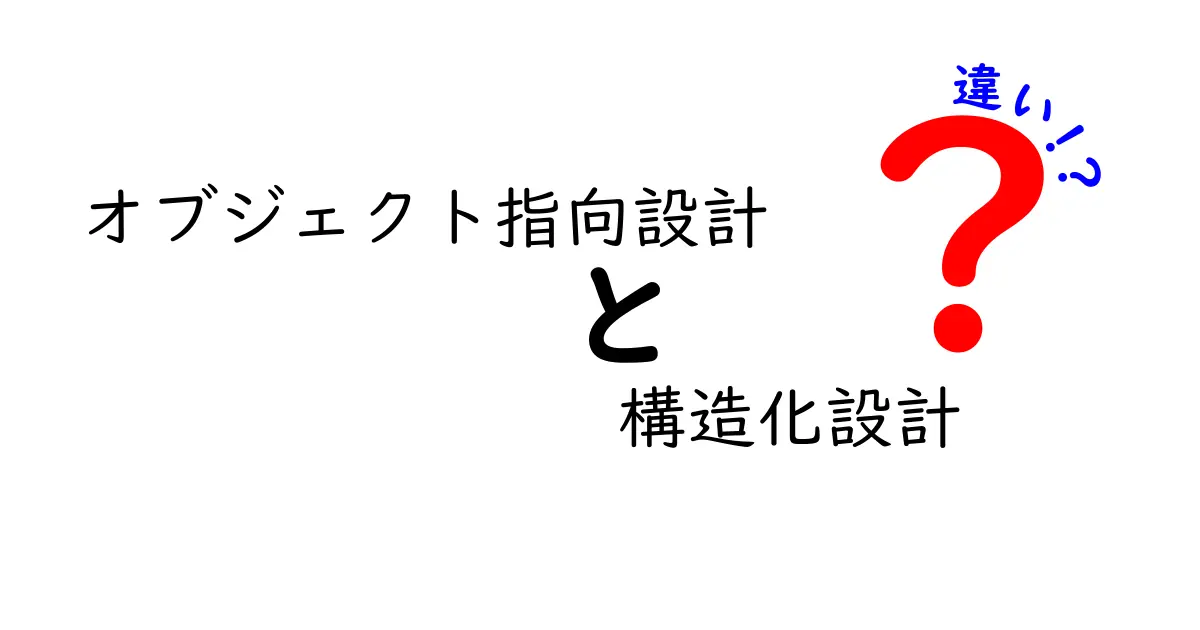

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
オブジェクト指向設計と構造化設計って何?
まず、オブジェクト指向設計と構造化設計は、プログラムを作るときの設計方法のことです。
わかりやすく言うと、家を建てる前に設計図を描くようなものです。
この設計図をしっかり描くことで、作るものがうまく動くようになります。
では、この2つはどう違うのか見ていきましょう。
「構造化設計」は昔から使われている方法で、プログラムを小さな手順(関数)に分けて作ります。
例えば、料理をする時に「野菜を切る」「煮る」「盛り付ける」という順番で作業を細かく決めていく感じです。
一方で「オブジェクト指向設計」は、ものや情報を「オブジェクト」と呼ばれる箱にまとめて設計します。
例えば、ゲームの中の『キャラクター』を一つのオブジェクトにし、その中に動き方や持っている道具を一緒に入れて考える方法です。
このように、構造化設計は順番や手順を大事にし、オブジェクト指向はものの性質や役割を一つにまとめることを重視します。
オブジェクト指向設計の特徴とメリット
オブジェクト指向設計の主な特徴は、「カプセル化」「継承」「ポリモーフィズム」という考え方があります。
カプセル化は、オブジェクトの中にデータや処理をまとめて隠すことです。外から直接触れられないので安全です。
継承は、新しいオブジェクトが既存のものの性質を受け継ぐこと、ポリモーフィズムは同じ操作が違うオブジェクトで違う動きをすることを意味します。
この設計のメリットは、プログラムの再利用や修正がしやすく、複雑なシステムも整理しやすい点です。
また、実世界の物事に近い形でプログラムを書けるのでイメージしやすい利点もあります。
ただ、慣れるまで少しむずかしいところもあります。
例えば、学校の生徒と教師をオブジェクトにして、それぞれの特徴や動きを箱の中で管理すれば、シンプルに考えられます。
変更があった時も、その部分だけ直せばよくなりプログラム全体を壊しにくくなります。
構造化設計の特徴とメリット
構造化設計の主な特徴は、プログラムを機能ごとに分けて順番に処理していく方法です。
わかりやすく言うと、料理のレシピのように「材料を準備する」「料理する」「盛りつける」という順序がはっきりしています。
処理の流れを明確にすることで、間違いが見つけやすくなります。
メリットは、手順を追いやすいため、初心者が理解しやすいことや、小さなプログラムなら作りやすい点です。
シンプルな問題を解決したい時や、すごく昔からあるシステムには今もよく使われています。
ただし、規模が大きくなると複雑になりやすく、修正が難しくなる場合があります。
例えば、単純な計算を順番に行うプログラムを作る時は構造化設計が向いています。
処理の手順を文書でしっかりまとめて作業を追いやすくします。
オブジェクト指向設計と構造化設計の違いを表で比較!
まとめ
今回は、オブジェクト指向設計と構造化設計の違いについて説明しました。
構造化設計は手順を重視し、小さな処理に分ける方法で、初心者でも理解しやすいのが特徴です。
一方、オブジェクト指向設計は複雑なものをものごと(オブジェクト)にまとめて考え、再利用や変更がしやすい利点があります。
これからプログラムを学びたい人は、まず構造化設計で基礎を学び、慣れてきたらオブジェクト指向設計に挑戦すると良いでしょう。
どちらも大切な考え方なのでぜひ覚えておいてくださいね!
オブジェクト指向設計の「カプセル化」って聞いたことある?これはプログラムの中でデータや処理をまとめて隠す仕組みなんだ。まるで秘密の宝箱みたいに、大事なものを守りながら使いやすく整理できるんだよ。例えばゲームのキャラクターなら、動きや体力の情報を一つにまとめてしまい、外から勝手に触れられないようにできる。これがあると、プログラムの安全性と管理がとても良くなるんだ。ちょっと難しいけど、おもしろい概念だよね!
次の記事: UMLとXMLの違いとは?初心者でもわかる基本ポイント徹底解説! »





















