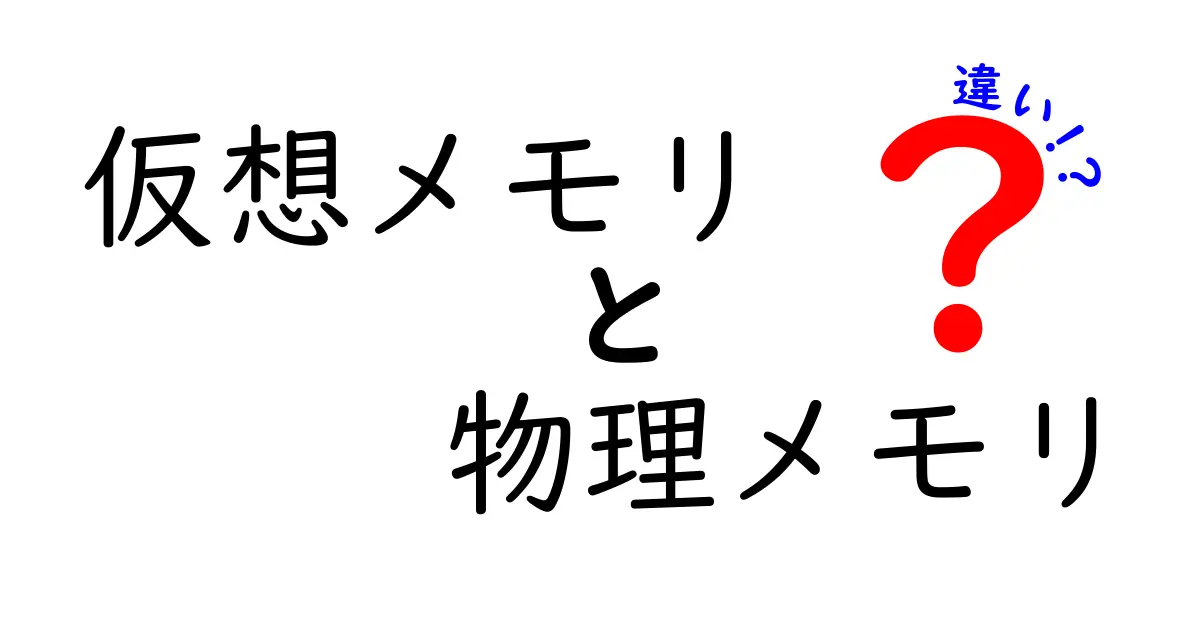

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
仮想メモリと物理メモリの違いを知ると、パソコンの仕組みが見える
「仮想メモリ」と「物理メモリ」という言葉、授業やニュースでよく耳にしますが、実は私たちが日常的に使っているパソコンの動作を左右する大切な仕組みです。
物理メモリは実際に機械の中にあるRAMのことを指し、強いスピードでデータを読み書きします。これに対して仮想メモリは、RAMの容量だけでは足りない場合にも「見かけ上の容量」を作り出すしくみで、OSがデータを入れ替えながら使える領域を広げます。
この二つは単に容量が違うだけでなく、どうデータを管理するかという点で大きく役割が異なります。
仮想メモリの仕組みがあるおかげで、同時に複数のアプリを起動しても動作を続けやすくなりますが、過度に依存すると処理が遅くなることもあります。
つまり、仮想メモリは RAM の不足をカバーする“補助役”、物理メモリは高速さと安定性を支える“実力派”というわけです。これは生活の道具箱に例えると、RAMが作業スペース、仮想メモリが引き出しの仕分け役みたいな関係です。
この考え方をもとに、次のセクションでは仮想メモリの仕組みをさらに詳しく見ていきます。
仮想メモリの仕組みと日常での影響
仮想メモリの仕組みは、パソコンのソフトとハードの間に「代理人」を置くイメージです。OSは仮想アドレスと呼ばれる住所を割り当て、実際のRAMのどこにデータを置くかを管理します。
ここで大事なのは、アプリは自分が使える仮想空間を自由に使えると感じる一方で、OSは頻繁にデータをRAMとストレージの間で移動させ、実際のRAM容量を超える要求にも対応します。これを実現しているのが「ページング」という仕組みと「ページテーブル」です。OSはアプリが使う仮想メモリの住所を管理し、必要に応じてデータを物理メモリに置くか、ディスク上に退避させます。
このやり取りは瞬間的に行われることが多く、私たちが気づかないうちに起こることが多いです。
頻繁なデータの入れ替えはCPUの時間を食うため、極端に仮想メモリを使いすぎると「遅くなる」原因になります。
また、仮想メモリを効率的に使うためには、現代のパソコンには高速なキャッシュ技術やTLBと呼ばれる仕組みがあり、これによりアプリの応答を少しでも速く保つことができます。
実生活の例えで言えば、部屋の中にモノがたくさん散らかっていても、仕分け棚と引き出しのルールを決めておくと、使いたいものをすぐ取り出せる状態を保つ感じです。しかし、仕分け棚が適切でないと、取り出すのに時間がかかり、作業全体の遅延につながります。
このように、仮想メモリは「使える容量を増やす工夫」であり、適切な設定とアプリの作法が重要です。最後に、仮想メモリと物理メモリの関係を理解すると、なぜ一部のゲームやアプリが「多くのメモリを要求する」と表示されるのか、また、なぜメモリ解放(不要データの削除)が効くのかが腑に落ちやすくなります。
koneta: 放課後、友だちと PC の話をしていて仮想メモリの話題になりました。彼は「RAM が足りなくなると本当に全て止まるの?」と聞き、私はコーヒーの泡を見つめながらこう答えました。「仮想メモリというのは、RAM が足りないときにも動き続けるための“仮想の広場”を作る仕組みなんだ。OS が仮想アドレスと実際のRAMの場所を橋渡しする役目を担います。必要に応じてデータをディスクへ退避させることで、同時に多くのアプリを走らせる体験を可能にします。もちろん退避のタイミングが悪いと読み込みや切り替えが遅くなり、体感としての遅延が出ます。この現象を「仮想メモリの使い方」次第で改善できることもあれば、ある程度の遅さは必然だという現実もあると学べました。





















