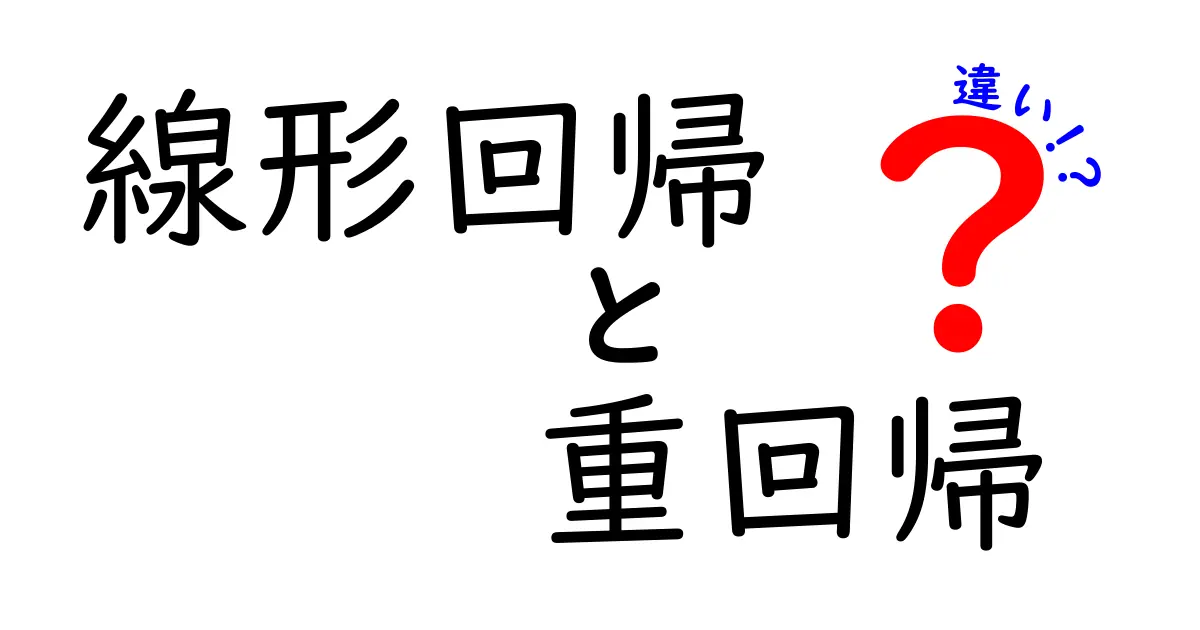

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
線形回帰と重回帰の違いを徹底解説:中学生にも伝わる基礎と見分け方
線形回帰と重回帰の違いを理解するうえで、一番大事なポイントは「説明変数の数とその関係の描き方」です。
まず線形回帰は説明変数が1つだけのときに使います。
例えば、雨の日の売上をこの1つの要因だけで予測するなら、線形回帰を使って式を作ります。式は y = a + b x の形で表され、ここで x は説明変数、y は予測値です。こうすることで、1つの要因が結果にどれだけ影響するかを分かりやすく示せます。
次に重回帰は説明変数が2つ以上になるときに使います。複数の要因が同時に影響する場面で、天気と曜日、広告費とキャンペーン期間など、複数の要因を同時に組み込んで予測を行います。式は y = a + b1 x1 + b2 x2 + … のように、各説明変数に対して係数がつきます。ここでのポイントは、「どの要因がどのくらい影響するのか」を同時に見られる点です。
こうした違いの理解には、最小二乗法という計算手法の役割を知ることも欠かせません。最小二乗法とは、観測データと予測データの差を二乗して足し合わせたものをできるだけ小さくする方法です。これにより、現実のデータに最も近い直線や平面を求めます。
また、データを扱ううえで欠かせない前提条件として、データが独立していること、説明変数と目的変数の関係が線形であること、そして外れ値の扱いなどが挙げられます。これらが崩れると予測力が落ち、誤解を生みやすくなります。
このように、線形回帰と重回帰の違いは基本的には「説明変数の数と関係の描き方」に集約されますが、実際のデータでは前提条件を満たすかどうかを確認し、適切な変数を選ぶことがとても重要です。実務での使い分けを学ぶときには、シンプルな例から始めて、徐々に複雑さを増していくのがコツです。
実務での使い分けと理解を深める図解と実例
現場での使い分けを考えるとき、まずは「予測に使う要因が何個あるか」を最初の判断材料にします。
もしデータに含まれる要因が1つだけなら線形回帰を選ぶのが自然です。解釈のしやすさが最大の魅力で、係数の意味がとても直感的に伝わります。例えば広告費だけを変えて売上を予測する場合、係数の正負と大きさで広告費が売上に与える影響を素早く理解できます。
一方、要因が複数あるときには重回帰の出番です。ただし注意点として、多くの説明変数を同時に扱うと「どの変数が本当に影響しているのか」が分かりにくくなることがあります。これを防ぐためには変数選択や正規化、さらには主成分分析 PCA などの手法を使います。
現場の練習として、データセットを用意して「データを集める → モデルを作る → 予測と評価をする → 改善する」というサイクルを回すと理解が深まります。以下の表は、線形回帰と重回帰の実務的な違いを簡潔にまとめたものです。
ある日の放課後、友だちと統計の話をしていたときのことです。
先生はこう言いました。「線形回帰というのは、一本の説明変数と目的変数の関係を、まっすぐな線で表す方法だよ」と。私はすぐに思い出しました。道案内で例えると、地図に引いた一本の直線が、目的地までの距離を示す道筋のようなものです。もし友だちが天気だけを見て明日の気温を予測するなら、それは線形回帰で十分です。
でも実際には天気だけでなく風向きや湿度、前日の売上の影響も加味したい場面が多い。そんなときは重回帰を使います。複数の要因を同時に扱える分、予測は強力になりますが、変数が多すぎたり相関が強すぎたりすると係数が分かりにくくなります。そんなときには「どの要因を本当に使うべきか」を話し合い、時には変数を減らす決断も必要です。私は友だちと、データを集める順序、モデルを作るときの仮定、そして評価のしかたを、まるでスポーツの練習メニューを決めるように組み立てるのが好きです。結局、数字を読み解く力は、練習と試行錯誤の積み重ねなのだなと感じました。強さの秘密は「適切な変数選びと適用の工夫」にあるのです。





















