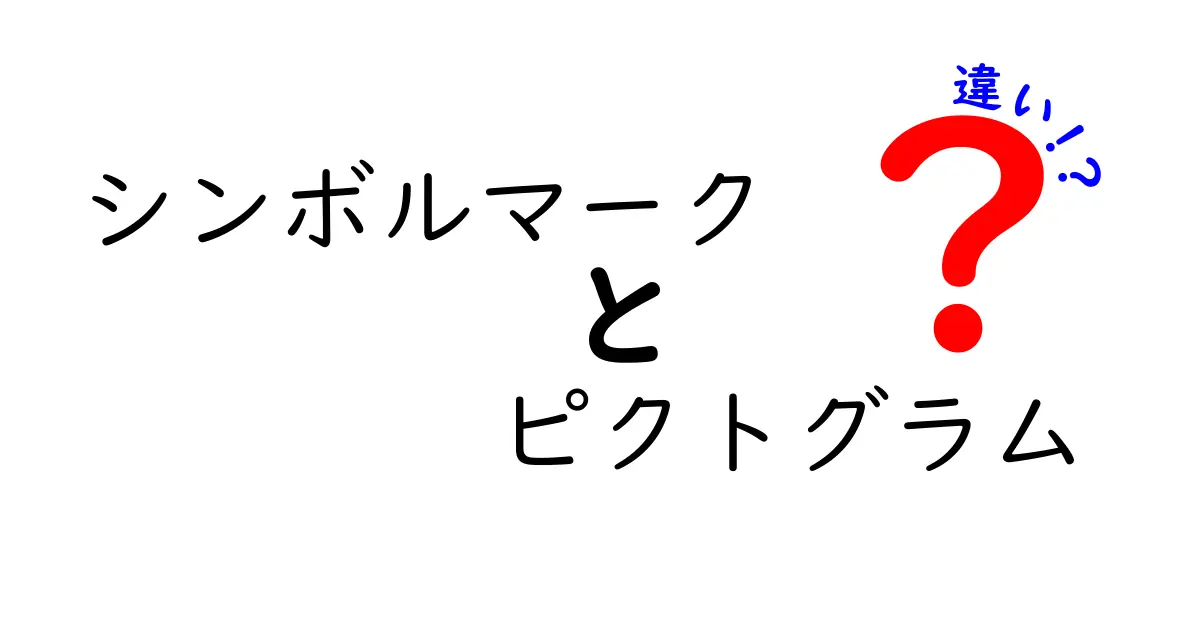

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
シンボルマークとピクトグラムの違いを徹底解説
シンボルマークとピクトグラムはどちらも視覚情報の手段ですが、目的や使われ方が大きく異なります。
一言でいうと、シンボルマークはブランドの「顔」を作るためのデザイン要素であり、長期的に同じ形と色で覚えられることを狙います。
一方、ピクトグラムは情報を素早く伝える道具であり、言語の違いを超えて理解されることを目指します。
この二つを混同するとデザインの意味がズレてしまうことがあるため、まずは基礎から整理します。
歴史的には、シンボルマークは企業の成長とアイデンティティの確立に伴って発展してきました。
現在ではブランド戦略の中核として機能し、広告媒体だけでなく商品パッケージ、店舗のサイン、ウェブサイトのロゴなど、さまざまな場面で一貫した視覚表現を提供します。
一方のピクトグラムは、国境を越えた情報伝達の道具として設計されてきました。道案内、交通標識、非常時の表示など、文字や言語に頼らず意味を伝えることで、旅行者や外国人、子どもにも読み取れるよう工夫されています。
このように目的の違いを踏まえると、デザインのアプローチ、色使い、形の選択、さらにはガイドラインの有無まで、さまざまな点が区別されるのです。
この記事では、具体的な例とともに違いを感覚的に掴めるよう、わかりやすい言葉で解説します。
最後に、日常の場面での見分け方のコツも紹介しますので、デザインの勉強をしている人だけでなく、普段から情報を読解する力を高めたい読者にも役立つ内容を目指します。
シンボルマークの特徴と使われ方
シンボルマークは企業やブランドの「顔」として機能します。
商標登録が可能で、長期にわたって同一性を維持するため、独自性やブランドガイドラインが重要です。
色彩は心理に作用し、市場での印象を決めます。青は信頼を、赤は強さや注意を、緑は自然や健康を連想させるといった、色の意味づけがあります。
形は曲線と直線の組み合わせで安定感や動きを表現します。
有名な例としてはNikeのスウッシュやAppleのリンゴマークが挙げられます。
これらは文字を使わず、直感的に企業名や価値観を伝える点が特徴です。
シンボルマークはサイズを縮小しても読みにくくならず、広告媒体やWebなどさまざまな場面で一貫した表現を可能にします。
ピクトグラムの特徴と使われ方
一方のピクトグラムは情報を「絵で伝える」ための道具です。
文字を使わず、読み手の言語に依存しない情報伝達を目的とします。交通標識や非常口のマーク、トイレの案内など、世界中で同じ意味を持つように設計されています。
形は抽象化され、複雑さを削ぎ落として認識速度を高めるのが狙いです。
例えば出口のマークは人のシルエットと矢印だけで場所を示します。
ピクトグラムはデザイン規範が整備されており、色の組み合わせや視認性の基準が定められている場合が多いです。
公共の場で使われることが多く、案内板の統一感を保つ役割を果たします。
まとめと具体的な見分け方
違いを一言で言えば、シンボルマークはブランドの顔、ピクトグラムは情報の道具という役割の違いです。
見分けるコツは、作品全体の文脈を観察すること。広告やパッケージならシンボルマークの可能性が高く、案内板や安全表示ならピクトグラムの可能性が高いです。
また、デザインの細部もヒントになります。ブランド用のマークは独自の曲線や色の組み合わせで記憶に残る工夫がされています。一方のピクトグラムは読みやすさと普遍性を最優先に、単純化と対比を重ねて作られています。
ピクトグラムを深掘りすると、実は私たちの生活の中で言語を超える会話が生まれていることに気づく。たとえば駅の案内標識を見て、英語が読めなくても矢印と人のシルエットだけで次の動作を理解できる。ここには文化の差を超える普遍性と、デザインの工夫が詰まっている。では、なぜ一部のピクトグラムは誤解を生むのか。意味を伝える符号が混ざると、形の認識と意味の対応がずれてしまう。だからデザイナーは線の太さ、角の角度、色のコントラストを細かく設計する。結局、ピクトグラムは言語習得の負担を軽くするための小さな言葉の集まり。ねぇ、私たちは普段看板を見て何かを選ぶとき、心の中で小さな物語を作っている。それが読み手の共感を生み、情報の伝達をスムーズにしているのです。
前の記事: « 構造主義と記号論の違いを図解で理解!中学生にもやさしい解説





















