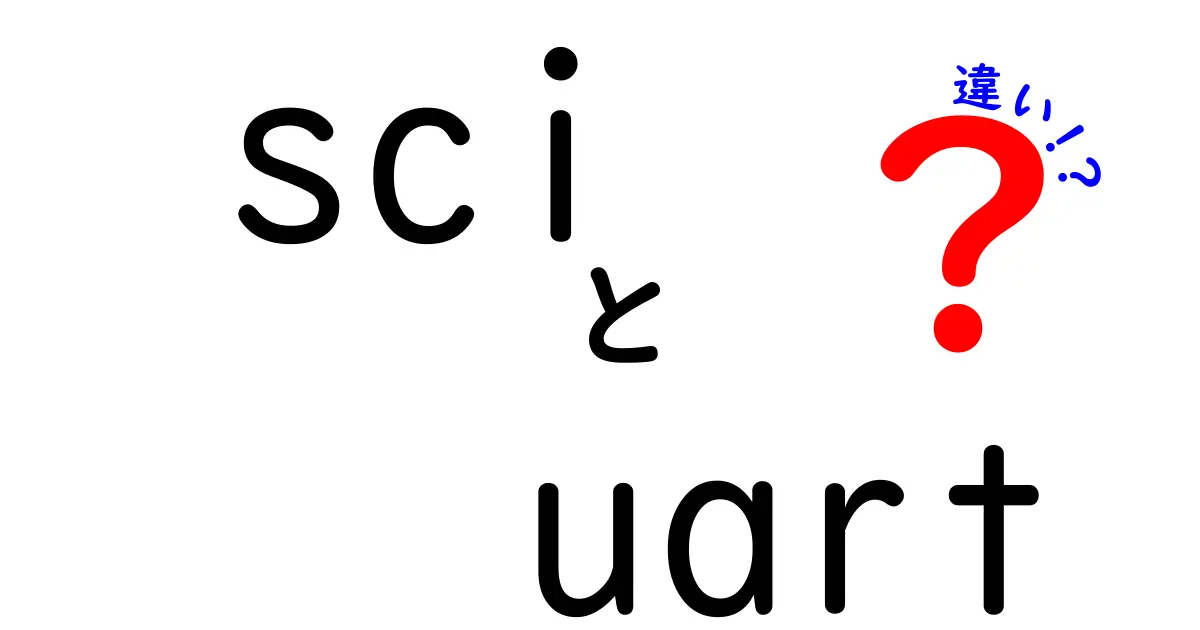

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
SCIとUARTの違いを理解する
情報技術の現場でよく耳にする SCIとUARTは、見た目には似たものに思えるかもしれませんが、役割や使い方が大きく異なります。まず覚えておきたいのは、SCIは“シリアル通信を扱うための機能の総称”であり、実装する機器やマイクロコントローラごとに呼び方が違うということです。つまり、ある機種の取扱説明書ではSCIという名前の周辺機能があって、それが複数のモードを持つことがあり得ます。対して、UARTは“非同期のシリアル通信を実現する具体的な規格”として設計されており、データを1ビットずつ送るための規則(開始ビット・データビット・停止ビットなど)を持っています。これにより、SCIが広い箱のような概念で、UARTがその箱の中にある具体的な通信の方法という理解になります。
この違いは、実務で機器を組み合わせるときに特に現れます。SCIを使っている機器同士であれば、同じシリーズの別のボード間でもモードを切り替えることで、UART相当の動作を実現できることがありますし、反対にUART専用のポートを使うことで、外部センサや他のデバイスと安定したデータ転送を行いやすくなります。大事なのは、UARTが「データをどんな順序で、どれくらいの時間間隔で送るか」という具体的な約束事である点です。
一方でSCIは「この周波数で動く別のモードにも対応できるような拡張性」を持ち、場合によってはSPIやI2Cの要素を併用する設計も存在します。つまり、SCIを選ぶ場面では、どのモードが必要か、どの規格と組み合わせて使えるのかを事前に確認することが重要です。
SCIの特徴と使い方
SCIは Serial Communication Interface の略で、マイコンの周辺機器として搭載されていることが多いです。SCIの特徴は、非同期と同期の両方モードを機器ごとに選べる点です。実装時にはレジスタの設定やボーレートの選択、データ長の指定、パリティ設定などを行います。複数のモードを持つ設計では、同じSCIユニットで複数の通信形態を切替可能ですが、その分設定の理解が必要です。初学者はまず文書にある各モードの説明を読み、実際の回路図と照合しながら、最低限の動作確認を行うのがコツです。ここで重要なのは、電圧レベルの整合性や信号線の配線方法も通信の安定性に直結するという点です。
現場では、baud rateだけでなく、データビット数やストップビットの組み合わせが通信の実用性を左右します。SCIを使った設計は、将来的に他の通信モードへ拡張する余地を残しておくと、後の機器差異に強くなり、保守性が高まります。
このような背景を理解すると、SCIの特徴と使い方が少しずつ見えてきます。SCIは広い機能の集合であり、モードの切替え次第で通信の形を変えられる点が魅力です。初学者には、まず「SCIは機能の総称」「UARTは非同期の具体的規格」という二つの要素を分けて考えると理解が進みやすいでしょう。続いて、規格の細かな設定をデータシートの表に沿って確認し、実験ボードで実際に通信を行ってみることが大切です。
UARTの特徴と使い方
UARTは非同期のデータ送信を実現する代表的な規格です。開始ビット、データビット、停止ビットといったシンプルな構成で、送信側と受信側がビット列を同じ速度で解釈することを前提としています。現場では、3.3Vや5Vといった信号レベル、ボーレート、データ長、パリティの設定を正しく揃えることが最初のステップです。接続は TXと RX をクロスさせて行い、外部機器との接続には電源の安定性とグラウンドの共通化が欠かせません。
UARTはRS-232のような電気的規格にも派生しますが、マイコン間の“TTLレベル”での通信として扱われることが多いです。この違いを把握するだけで、回路図の読み方やデバッグの手順が大きく楽になります。クロックの同期を必要としない点が特徴で、配線が単純で導入が早い反面、ノイズや長距離伝送には弱いという特徴も理解しておく必要があります。
UARTを選ぶ現場の実務的なポイントは、まず通信相手の仕様を確認することです。相手がUARTを採用しているか、ボーレートとデータ長の組み合わせは互換性があるか、電源電圧と信号レベルは一致しているかなどを、回路設計の初期段階で決めておくと良いでしょう。さらに、必要に応じてCTS/RTS などのハンドシェイク線を使い、通信の安定性を高める工夫も有効です。これらの判断は、最終的にはデータシートと実機検証で確かめるのが確実です。
実務での選び方とヒント
結論としては、sci と uart の違いを正しく理解し、相手の機器が何を求めているかを読み解くことが大切です。機器間の互換性や設計の拡張性、デバッグのしやすさを軸に判断します。名前の揺れ方に惑わされず、データシートの用語が指す意味を素直に読み解く訓練を積みましょう。実務では、SCIが持つ多様なモードのうち、現場の要件に最も適したものを選ぶことが失敗を避けるコツです。UART はシンプルな伝送を素早く実現できる点が強みなので、外部機器との接続が主体なら最適な選択になることが多いです。最後に、設計の初期段階で「この通信路はどういうデータを、どのくらいの速さで送るのか」を必ず文書化しておくと、後の保守や機器差異対応が楽になります。
放課後の技術クラブでsci uart 違いについて雑談したときの話。SCIは“シリアル通信を扱う機能の総称”で、UARTはその中の代表的な具体的な規格、という整理が最初は難しく感じました。話を深めるうちに、SCIは箱のような広い概念、UARTはデータを並べて送る具体的な手順という点が見えてきました。設計書を読むとき、SCIとUARTの区別をつける癖をつけておくと、部品選びがスムーズになり、トラブル時の原因特定も楽になります。実際の実装では、ボーレートやデータ長、信号レベル、データの整列性など、細かな設定が通信の成否を決める大事な要素です。





















