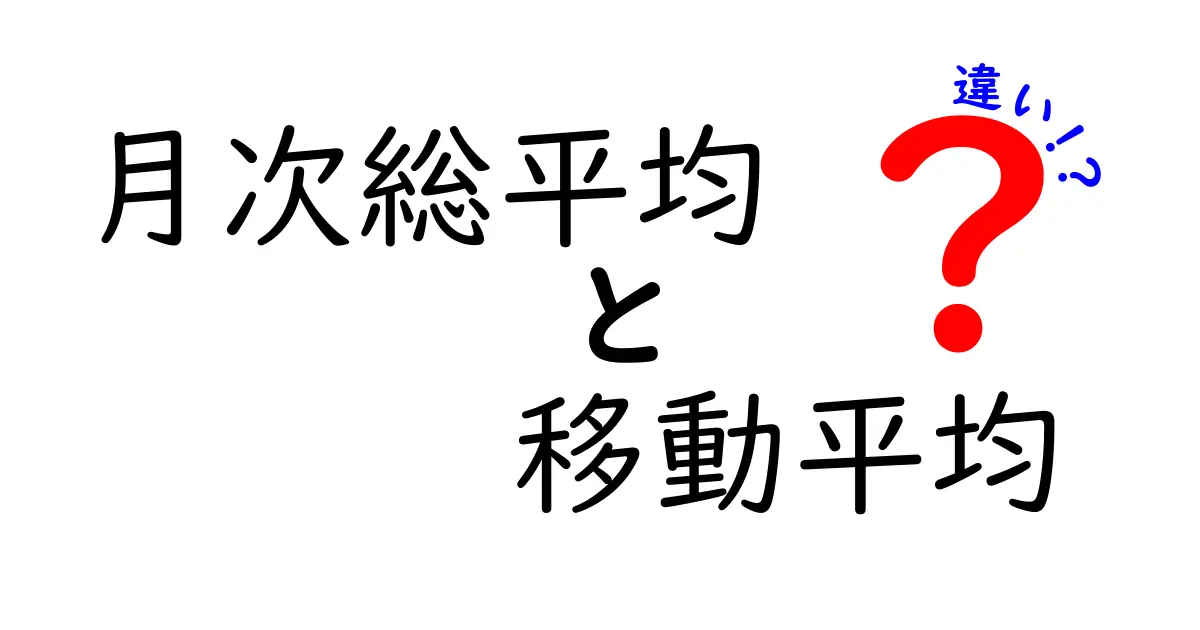

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
月次総平均と移動平均の違いを徹底解説
データを日々見る人にとって、月次総平均と移動平均は似ているようで“別物”です。まず、月次総平均は1か月単位のデータを1つの値にまとめる計算で、月の全体的な水準を示します。これは学校の成績を月ごとに平均したときのように、月の平均的なレベルを教えてくれます。日付の揺れや特定の日の大きな変動の影響を受けにくく、データの分布がどうなっているかをざっくり知るのに向いています。例えば今月の売上が急に伸びた日があったとしても、月次総平均はその影響をある程度緩和します。
ただし、データの中で大きな偏りがある場合には、実態の“動き”が見えづらくなることがある点には注意が必要です。
一方で移動平均は“最近の動きを滑らかに見る”ための手法です。決まった期間を選んで、最新のデータを継続的に取り込み、古いデータを捨てるという仕組みです。たとえば7日間の移動平均を使うと、直近1週間の様子が分かりやすくなります。新しいデータが来るたびに平均値が更新され、急な変動のノイズが抑えられて、全体の傾向が見やすくなります。移動平均は「トレンドの方向性を捉える力」が強い反面、期間を長く取りすぎると最新の変化を見逃すことがある点が欠点です。
この二つの考え方をどう使い分けるかが、データ分析の腕の見せ所です。月次総平均は「月全体の水準を確認するための基準値」として使います。移動平均は「最近の動きを把握するための追跡線」として使えるため、短期の変化を追いたいときに有効です。実務ではこの二つを組み合わせる場面が多く、たとえば月次総平均で月の基準値を決め、移動平均で日々の動きをモニタリングする、といった使い方が一般的です。期間の選択は目的次第、データの欠測には注意、比較のためにはデータの前処理が重要という点を必ず押さえておくと良いでしょう。
最後に、実務での例として、金融データの時系列を用いた比較を簡単に紹介します。
株価データや為替レートは、日次データが小さな変動を繰り返します。ここで月次総平均を使うと「この月の大まかな水準」が見える一方、移動平均を使うと「最近の数週間の動き」がわかります。データの読み方がわかれば、投資の判断やビジネスの計画にも活かせます。
今日は友達と放課後のデータ談義をしていたときのこと。月次総平均と移動平均の違いを雑談風に深掘りしてみました。要は、月次総平均は当月の“全体の水準”を一つの値で示す呑み込み型、移動平均は“最近の動き”を追う追跡型です。どちらを選ぶかは、見たい情報が短期の波なのか長期の安定なのかで変わります。データを解釈する視点を切り替えるだけで、数字が語るストーリーが変わるのです。





















