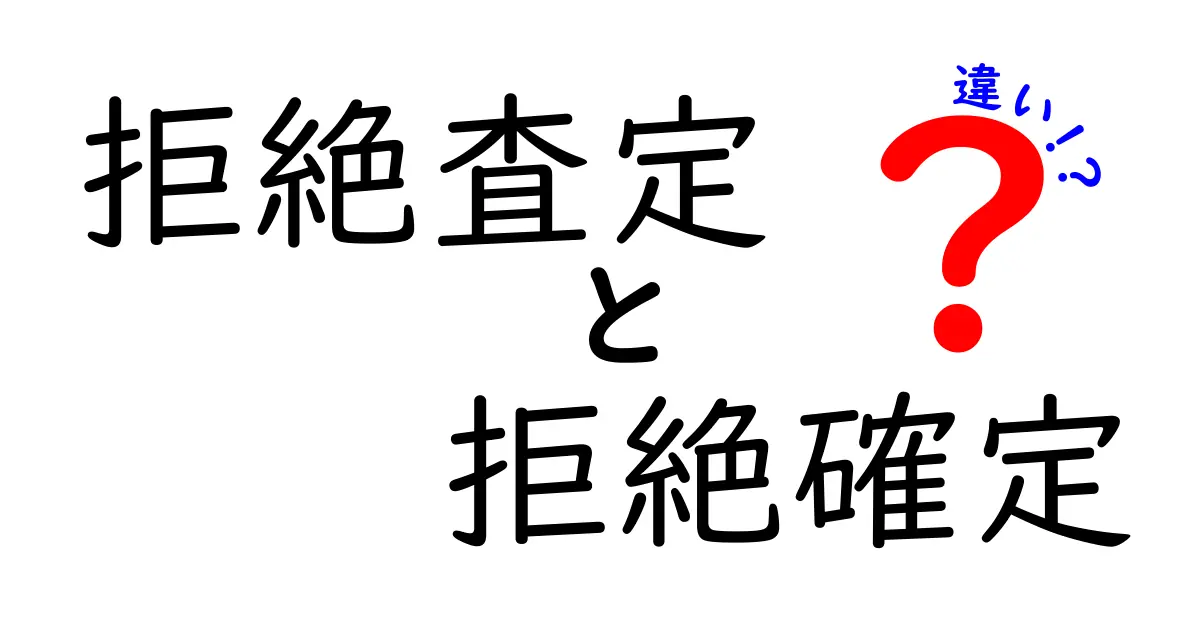

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:拒絶査定と拒絶確定の違いを正しく理解する
知財の世界では申請と審査の過程が長く複雑で、時に専門用語が難解に感じられます。特に 拒絶査定 と 拒絶確定 は、出会うタイミングや意味が異なるため混同されがちな用語です。この記事では中学生にも分かるよう、両者の定義や発生タイミング、意味する結果、そして今後の対応について丁寧に解説します。まず大切なのは、拒絶査定は審査の結果としての拒絶通知であり、必ずしもその場で最終決定になるわけではない点です。申請者には補正や意見書の提出、さらに不服審判の請求といった選択肢が用意されています。これらの手続きで再度審査を受けられる可能性があるのです。一方、拒絶確定は一定の期日内に適切な対応が行われなかったり、不服審判で覆されなかった場合に成立する、最終的な結論に近い状態です。つまり拒絶査定が出た時点で終わりではなく、適切な対応次第で逆転の機会があるのが拒絶査定、一定期間経過後に結論が確定してしまうと次の手続き選択肢が大きく絞られるのが拒絶確定というわけです。
この違いを正しく理解することは、知財戦略を組むうえで非常に重要です。審査の流れをざっくり知っておくと、次に何をすべきか判断しやすくなります。出願後、技術の新規性や進歩性が問われている場面で、審査官側の判断に納得がいかなければ意見書や補正を検討します。これにより、拒絶査定を受けても再度の審査を受ける道が開かれることがあります。反対に、期限を過ぎてしまえば拒絶確定となり、別の出願戦略を立てる必要が出てきます。ここから先は、実務での具体的な違いと対応のポイントを詳しく見ていきます。
拒絶査定と拒絶確定の実務上の違いと対応
まず基本となるのは 拒絶査定 が出たときの対応です。審査の結果として一部の請求項が認められず、他の請求項は通る可能性がある状況が考えられます。この時、補正を行って請求項の範囲を適切に整理することで新たな審査を受け直せる場合があります。補正は請求項を狭めることで新規性や進歩性を再評価してもらう手段です。補正がうまくいけば拒絶査定を覆し、特許査定へと転じる可能性があります。加えて意見書を提出する方法もあり、審査官に技術的特徴をより分かりやすく伝えることが目的です。ここでのポイントは、技術的特徴を明確に、かつ先行技術との比較を丁寧に説明することです。期限内に適切な資料を揃えて提出することが非常に重要で、遅延があると不利になることがあります。
また、不服審判の請求という道もあります。これは別の審判手続きで、技術的な観点や法的解釈を再検討してもらう機会です。期間は制度で定められており、期間を過ぎると請求できなくなるため、早めの判断と計画が求められます。
一方 拒絶確定 となった場合には、再審の選択肢が狭まることが多くなります。新規に出願を行うか、別の発明として新規性や進歩性を満たす新しい技術的特徴を追加するかといった戦略的判断が必要です。企業ではこの局面でのビジネス影響を考え、製品開発計画や特許ポートフォリオの見直しを進めます。拒絶確定は、期限内に適切な手続きを行わないと避けられない結果になることが多く、スケジュール管理が特に重要です。
なお、拒絶確定だからといって全く手がないわけではなく、別の出願領域や別の請求項での保護を探す、あるいは他社の特許動向を踏まえたライセンス戦略を検討する、といった選択肢は残っています。
表で見る違いと今後の対応
実務で使えるポイントとまとめ
実務では、拒絶査定が出たらすぐに期限と手続きのスケジュールを整理します。補正の方針を立てる際には、技術の核心を強化するポイントと、先行技術との差別化点を明確化することが大切です。意見書は審査官の理解を深める機会なので、技術的説明だけでなく、市場での活用可能性やビジネス上の優位性も織り交ぜて伝えると効果的です。期限を守ることは基本中の基本ですが、期限内に適切な資料を揃えるためには、社内での共有と外部専門家の協力を得ることが重要です。拒絶確定を避けるためには、出願戦略の見直しや、他の出願領域の検討、複数案の同時進行といった作業が有効です。最終的には、知財は企業の資産です。長期的な視点で出願ポートフォリオを設計し、革新的な技術が適切に守られるよう計画的に進めましょう。
まとめと今後の行動ガイド
この記事の要点は、拒絶査定と 拒絶確定 の違いを理解し、それぞれに適切な対応を取ることです。拒絶査定は補正・意見書・不服審判などの道があり、戦略次第で覆る可能性があります。拒絶確定は通常は再審の道が限られるため、早めの判断と新たな出願戦略が重要です。表に整理したように、状況別の対応を事前に準備しておくと、急な判断が求められても落ち着いて対処できます。知財は企業の強みを守る大切な資産です。今後も最新の審査手続きの変更点をチェックし、適切な専門家と連携して、計画的なポートフォリオ運用を目指しましょう。
友達のAとカフェで雑談していたときのこと。Aは最近 拒絶査定を受けて落ち込んでいた。私は「大丈夫だよ、拒絶査定は終わりの合図じゃなくて、復活のチャンスの始まりかもしれないんだ」と促す。実際、補正して新しい道を探せば審査は再開される可能性がある。反対に期限を過ぎてしまうと 拒絶確定 になってしまい、別の道を探す必要が出てくる。だから「今できること」を一つずつ整理するのが大事だよと話し、二人で次の補正案を練る。小さな一歩でも積み重ねれば道は開ける、そんな気持ちになる話だった。





















