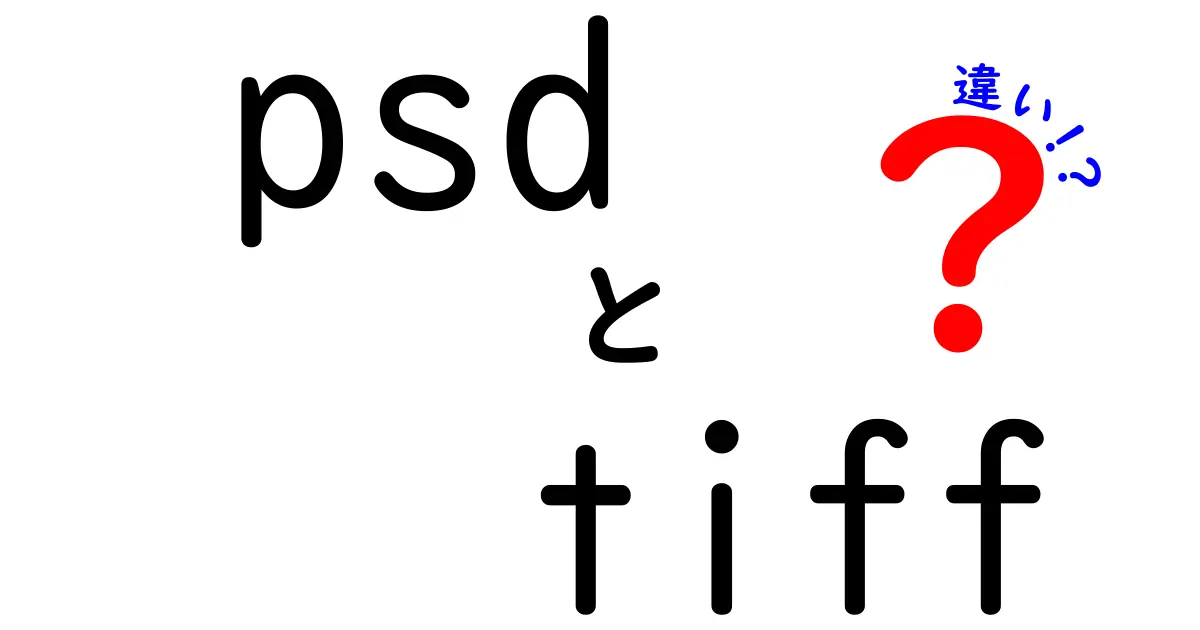

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
PSDとTIFFの違いを徹底解説
画像ファイルにはいろいろな種類がありますが、中には編集の工程や保存形式として選ぶべき場面がはっきり分かれているものがあります。特に「PSD」と「TIFF」は、デザイナーや写真編集者にとって基本中の基本になる二択です。
PSDは「Photoshop Document」の略で、レイヤー情報をそのまま保存できることが最大の特徴です。これにより、後から個々のレイヤーを編集し直したり、効果を調整したりする際の自由度が高くなります。
一方TIFFは「Tagged Image File Format」の略で、長期保存に強い汎用フォーマットとして設計されており、様々なソフトウェアでの互換性が高く、色深度や圧縮設定の選択肢が豊富です。
この二つは「編集重視」と「保存と共有重視」という視点で使い分けるのが基本です。
この記事では、初心者でも分かるように、結論を先に伝えたうえで、実務での使い分け、注意点、そして実例を具体的に紹介します。最後には、ワークフローの中でどのように選択すればよいかのチェックリストも用意します。
1つ目のポイント:ファイル形式の基本と使い方
PSDの基本用途は、デザイナーがレイヤーを自由に重ね、色調整、マスク、フィルター、文字情報などを「そのままの状態」で保存することです。
このため、編集を続ける前提の作業に最適です。PSDファイルは通常圧縮されますが、レイヤーや透明度、スマートオブジェクト、チャンネルなどの情報を含むため、ファイルサイズは大きくなりがちです。
作業環境としては、PhotoshopやIllustrator、または対応ソフトを使うことで、非破壊編集のまま調整を繰り返せます。
ただし、他のアプリへの移行時には、レイヤー情報の再現性が限定されることもあるため、最終納品用には別形式へのエクスポートが必要になることがあります。
PSDの特徴は、まさに編集の自由度の高さにあります。レイヤーの統合を避けて作業を続けられる点、スマートオブジェクトで非破壊編集が可能な点、そして文字情報やカラー設定が一つのファイルにまとまる点が大きな利点です。
ただし、ファイルサイズが大きくなりやすい点や、他のアプリでの互換性の揺れが起こる場合がある点には注意が必要です。
TIFFはどうかというと、長期保存に適した汎用フォーマットであり、色深度や圧縮方法の選択肢が豊富です。
単純な写真データの保存から、複数チャンネルの情報を保持する画像、印刷用データの保管まで、さまざまな場面に対応します。
TIFFは「レイヤーを保持するか」「圧縮をどうか」「カラー部分をどのように保存するか」という設計により、編集向けよりは保存・共有向けの性質が強いことが多いです。
このため、別のソフトに渡すときでも、色域や圧縮設定が崩れにくいという点が評価されます。
まとめると、PSDは編集のための道具箱、TIFFは保存と伝送の安定性を重視したフォーマットという理解が基本です。
続く章では、実務での使い分けの具体例と、知っておくべき落とし穴を詳しく解説します。実務の現場では、編集を続けるためのPSDと、納品・アーカイブに適したTIFFを状況に応じて使い分ける判断力が求められます。
この判断を間違えると、後で修正が難しくなったり、色の再現性が狂ったりすることがあります。
この記事を読んだ後は、あなたのワークフローに合わせた最適な選択肢がすぐに選べるよう、具体的なチェックリストを手元に置けるようになります。
2つ目のポイント:実務での選択基準と適した場面
実務では、まず「目的を明確にする」ことが第一歩です。
写真撮影の現場での編集が続く場合は、PSDを第一選択とするのが自然です。後からのレタッチ、色補正、マスクの調整、文字入れなどを、レイヤーを保持したまま行えることが大きな利点です。
一方、完成品を長期間保管・共有するシーンでは、TIFFの汎用性と色の再現性が強みになります。印刷用データとしての安定性や、別のソフトでの閲覧・編集の互換性を重視する場面で特に有効です。
それぞれの長所と短所を整理しておくと、プロジェクトの初期段階で迷いを減らせます。以下の表は、代表的な用途別の選択基準をまとめたものです。項目 PSD TIFF 補足 主な用途 編集・再加工向け 保存・伝送・印刷向け 状況に応じて使い分ける レイヤーの扱い レイヤーを保持 レイヤーを保持する場合もあるが環境依存 最終納品は未加工か再編集可能かで判断 ファイルサイズ 比較的大きい 設定次第で抑制可能 ストレージと帯域も影響 互換性 ソフト依存がある 高い汎用性 プラットフォーム間での再現性を重視 推奨場面 デザイン作業中の原稿データ 納品・アーカイブ・印刷用 用途と相手先の要件を確認
上の表を見れば、編集重視のPSDと、保存・伝送重視のTIFFが一目で分かります。実務では、プロジェクトの初期段階でこの二つを使い分けるルールを設定しておくと、ミスを防ぎやすくなります。例えば、原稿データはPSDで保存しておき、納品用にはTIFFや他のフォーマットへエクスポートする、という流れが一般的です。
また、カラー設定やインクプリントの要件が厳しい場合は、TIFFの方で色管理を徹底する必要があります。結局のところ、最も大切なことは、納品先の仕様とワークフロー全体の整合性を取ることです。ここまで理解すれば、PSDとTIFFを使い分ける判断基準がしっかり見えてきます。
最後に、実務で役立つちょっとしたコツを一つ紹介します。
プロジェクトの初期段階で、両方の形式を同時保存しておくと、後工程でのトラブルを避けられます。特にチームで作業を回すときには、誰がいつどのファイルを編集したのか履歴を保つことが重要です。
このような実務的な配慮が、納期の安定と品質の両方を守るカギになります。
友人とカフェで雑談しているとき、 PSDの話題が出た。私『PSDは編集の宝箱みたいだよね、レイヤーを重ねていろいろ試せるのが魅力』友人『でも、最終的に渡すときはTIFFの方が安全だよね。色の再現性と互換性が高いから』私『そのとおり。実務ではPSDで作業を続けつつ、納品用にはTIFFへエクスポートするのが定番になりつつあるんだ』。こうした実務の現実味を帯びた会話を通じて、PSDとTIFFの使い分けが自然と理解できるはず。日常のデスクワークの中にも、ファイル形式の選択が大きな違いを生む場面がたくさんあり、だからこそ迷うときこそ基本に立ち返ることが大切だ。
実際には、プロジェクトごとに適した形式が異なるため、最初に要件を整理しておくことが最も有効です。





















