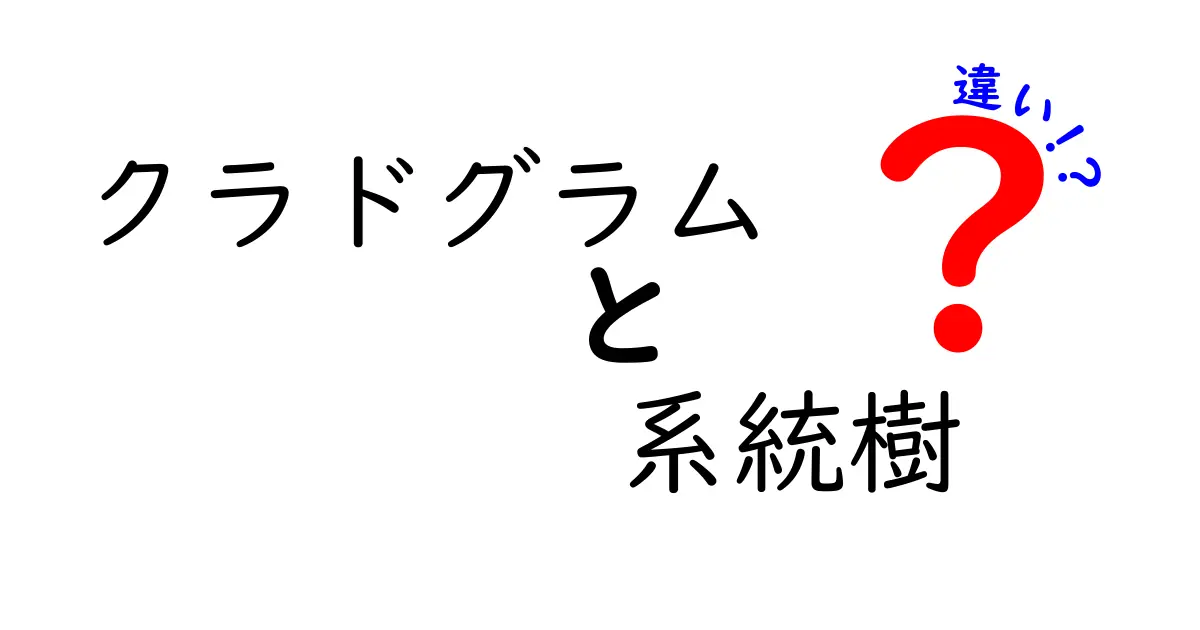

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クラドグラムと系統樹の違いを徹底解説
クラドグラム(Cladogram)と系統樹(Phylogenetic tree)は、生物の進化や関係を理解するための図ですが、それぞれの役割や見方には大きな違いがあります。
本記事では、両者の基本的な定義、作られ方、そして日常の研究や教育現場でどう使い分けるかを、中学生にもわかりやすい言葉で解説します。
まずは「何を表しているか」が最初の分かれ道。クラドグラムは「共通の特徴を起点に、どの特徴がいつ現れたか」を示す図です。
一方で系統樹は「生物同士の最近の共通祖先と分岐の順序」を、進化の系統的な距離として表現します。
この違いをつかむと、同じ“樹の形”でも意味が全く違うと気づくことが多くなります。
さらに、錐体状の見た目だけで判断するのはNG。クラドグラムは特徴の現れ方が重要であり、系統樹は遺伝子データや化石記録、生態的情報をどう組み合わせるかが勝敗を分けます。
このページを読めば、言葉の違いだけでなく、実際のデータの扱い方の違いもわかってきます。
それでは、個別の要素を順番に見ていきましょう。
クラドグラムとは何か
クラドグラムは、特徴の出現順序を重視して分類する図です。枝先には現生の生物が並び、枝の分岐は「この時点で共通の特徴をもつグループが分かれた」という意味を持ちます。
この図の目的は、進化上の「共通の特徴を持つグループがどのように広がっていったか」を見せることです。
注意点として、クラドグラムは「祖先の生物がどんな特徴を持っていたか」を正確には示しません。
現生種がどのように分岐してきたかを、特徴の出現順と関連づけて描くのが基本です。
ですから、枝が長い/短いという情報は、必ずしも“時間”を意味しない場合があります。
クラドグラムの作成では、対象とする生物群の「共通する新しい特徴(派生形)」を探し、それを根本(基部)から順に並べます。
こうして、ある特徴が現れた点を境界として、同じ特徴を持つ生物を同じグループにまとめます。
結果として、葉に並ぶ現生種同士は、共通の祖先を意識しながら、どのように分岐してきたかの仮説を得られます。
ここで大事なのは、クラドグラムが常に“時間を正確に示す”わけではないという点です。単純に「早く現れた特徴ほど古い」ではなく、データの解釈次第で解釈が変わることもあるのです。
クラドグラムの作成では、対象とする生物群の「共通する新しい特徴(派生形)」を探し、それを根本(基部)から順に並べます。
こうして、ある特徴が現れた点を境界として、同じ特徴を持つ生物を同じグループにまとめます。
結果として、葉に並ぶ現生種同士は、共通の祖先を意識しながら、どのように分岐してきたかの仮説を得られます。
ここで大事なのは、クラドグラムが常に“時間を正確に示す”わけではないという点です。単純に「早く現れた特徴ほど古い」ではなく、データの解釈次第で解釈が変わることもあるのです。
クラドグラムの作成では、対象とする生物群の「共通する新しい特徴(派生形)」を探し、それを根本(基部)から順に並べます。
こうして、ある特徴が現れた点を境界として、同じ特徴を持つ生物を同じグループにまとめます。
結果として、葉に並ぶ現生種同士は、共通の祖先を意識しながら、どのように分岐してきたかの仮説を得られます。
ここで大事なのは、クラドグラムが常に“時間を正確に示す”わけではないという点です。単純に「早く現れた特徴ほど古い」ではなく、データの解釈次第で解釈が変わることもあるのです。
系統樹とは何か
系統樹は、進化の「系統的な距離」や「祖先と子孫の関係」を、木の枝の形で表す図です。葉には現在生きている種が並び、根(または基部)は最も古いとされる祖先を示すことが多いです。
系統樹は、遺伝子データ・化石の配置・生態のつながりなど、複数の情報を組み合わせて作られることが多く、統計的手法を使って分岐の順序や距離を推定します。
この「距離」の意味は、単なる時間だけでなく、遺伝子の変化の程度や生物間の近さを意味する場合が多いです。
系統樹は、データの取り込み方や計算方法に左右されるため、同じグループを別の方法で描くと別の木が得られることもあります。
実際、クラドグラムと系統樹は“同じ現象を別の見方で表す道具”と考えると理解しやすいです。
クラドグラムは派生形の出現に焦点を当て、系統樹は祖先-子孫の関係と距離を示すという基本方針の違いがあります。
実務や教育の場では、研究目的に合わせてどちらを使うかを選ぶことが大切です。
以下の表は、両者の違いを一目で比較するまとめです。
最後に覚えておきたいのは、両者は“進化を理解するためのツール”であり、正しい理解にはデータの性質と目的をよく考える必要があるということです。
この理解をもとに、実際の研究文章を読むときも、図の意味を正しく読み解けるようになります。
学ぶほどに、進化の世界が少しずつ身近に感じられるようになるはずです。
友達との会話スタイルの小ネタ: ねえ、クラドグラムと系統樹、同じ進化の話を別の角度で見てるだけって知ってた?クラドグラムは“派生した特徴がどの順で現れたか”を重視するから、あるグループがどんな新しい特徴を獲得したのかを追う地図みたいなもの。対して系統樹は“祖先と子孫のつながり”を距離感で示すから、データの積み上げ方で木の形が少し変わることがある。だから、同じ生物の関係を描くときでも、クラドグラムと系統樹を並べて見ると、どの情報を強く使ったかで結論が変わるんだ。私たちはデータを集めるとき、まず「何を知りたいのか」を決めてから木を描くべきだと感じる。そうすると、進化の話が“羅針盤の針”みたいに、進むべき方向を指してくれるんだよ。





















