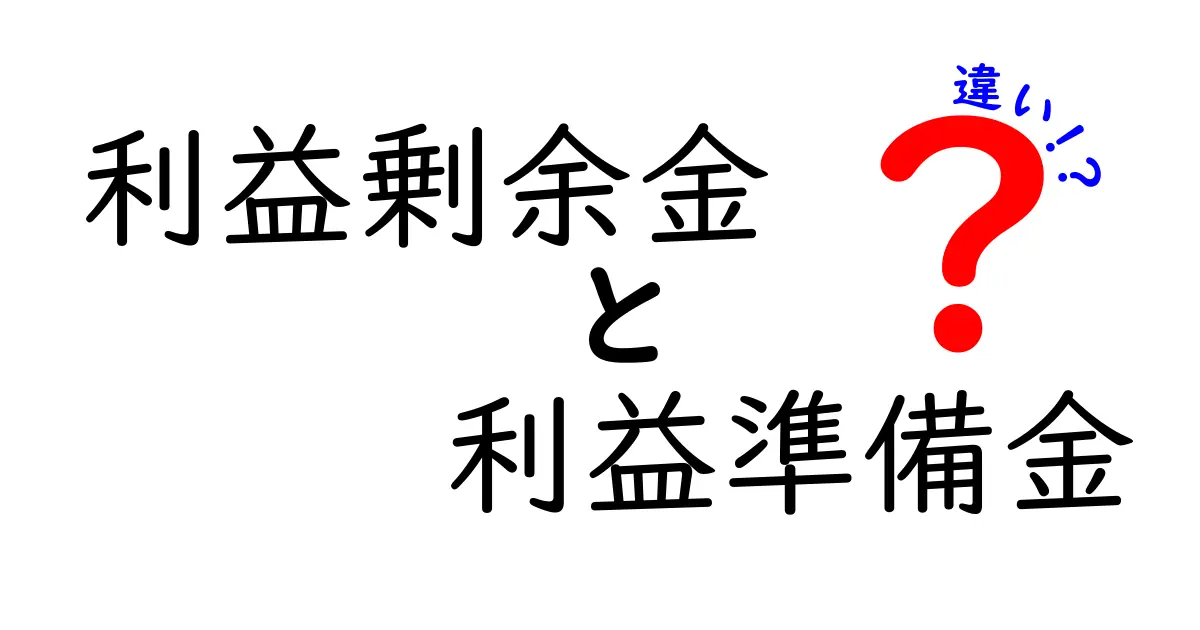

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
利益剰余金と利益準備金とは何か?基本の理解から始めよう
会社の経理や会計の話になると、よく耳にする言葉の一つに利益剰余金と利益準備金があります。どちらも会社の利益に関わる項目ですが、混同してしまいがちですよね。ここではまず、それぞれの意味と役割についてお話ししましょう。
利益剰余金とは、簡単に言うと「会社が稼いだ利益のうち、配当や経費などを差し引いた後に残ったお金の総額」です。これは会社が自由に使える資金となり、将来の投資や資金繰りに利用されます。
一方の利益準備金とは、会社が利益の一部を法的に留保しておくための制度で、法律で積み立てることが義務付けられている準備金のことです。これは主に会社の財務の安定性を保つために設けられていて、簡単には取り崩せません。
利益剰余金は会社の自由に使える資産、利益準備金は将来のリスクや損失に備えるための積立金、と理解するとわかりやすいですね。
利益剰余金と利益準備金の違いを表で比較!見やすく整理しよう
言葉だけではわかりづらいので、次に利益剰余金と利益準備金の違いを表にまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。
| 項目 | 利益剰余金 | 利益準備金 |
|---|---|---|
| 意味 | 会社が稼いだ利益のうち、配当や経費を差し引いた後に残る資金の総額 | 利益の一部を法律で積み立てることが義務付けられている準備金 |
| 法的義務 | なし。会社の自由に使える | 法律で一定割合積み立てが義務付けられている |
| 使用目的 | 将来の投資、資金繰り、配当原資などに利用可能 | 主に会社の財務の安定を保つための留保金 |
| 取り崩し | 自由に可能 | 条件を満たさないと取り崩しに制限あり |
この表を見ると、利益剰余金は比較的自由に使えるお金で、利益準備金は会社の安全を守るために留保されている資金であることが明確にわかりますね。
次は、それぞれがどうやって積み立てられるのか、そしてどんな場面で重要となるのかを説明します。
利益剰余金と利益準備金の積み立て方と実際の使われ方
利益剰余金は会社の利益が出るたびに増えていきます。会社は1年間で得た利益のうち、どれだけ配当に回して、どれだけ会社に残すかを決めます。残った部分が利益剰余金として積み上がり、将来の投資資金や経営の安定に役立てられます。
利益準備金は法律で定められたルールに従い、利益の一部を強制的に積み立てます。たとえば日本の会社法では、配当可能額の10%を最低限積み立てることが義務付けられている場合があります。このため、利益準備金は会社の資本金に近い役割を果たすことが多いのです。
また、利益準備金は簡単には使えないため、会社が倒産の危険に直面した際のセーフティーネットのような存在として大切です。逆に、利益剰余金は比較的自由に使えるので、経営戦略や配当政策を考えるときにはこちらの残高を重視する場合が多いです。
このように利益剰余金と利益準備金は、見た目は似ていても、その性質や使い方で大きく異なるのです。
利益準備金って、実は法律で積み立てが決まっているんです。だから会社は利益の一部を必ずこの準備金に回して、簡単には使えないようにしています。まるで“会社の貯金箱”みたいな存在で、急なトラブルがあってもすぐに資金が枯渇しないようにしているんですよ。
だから、利益準備金は会社の安全装置とも言えます。利益剰余金と違って自由に使えない分、地味だけどとても重要な役割を持っているんですね。
次の記事: 利益剰余金と現預金の違いとは?簡単解説!経営の基本を理解しよう »





















