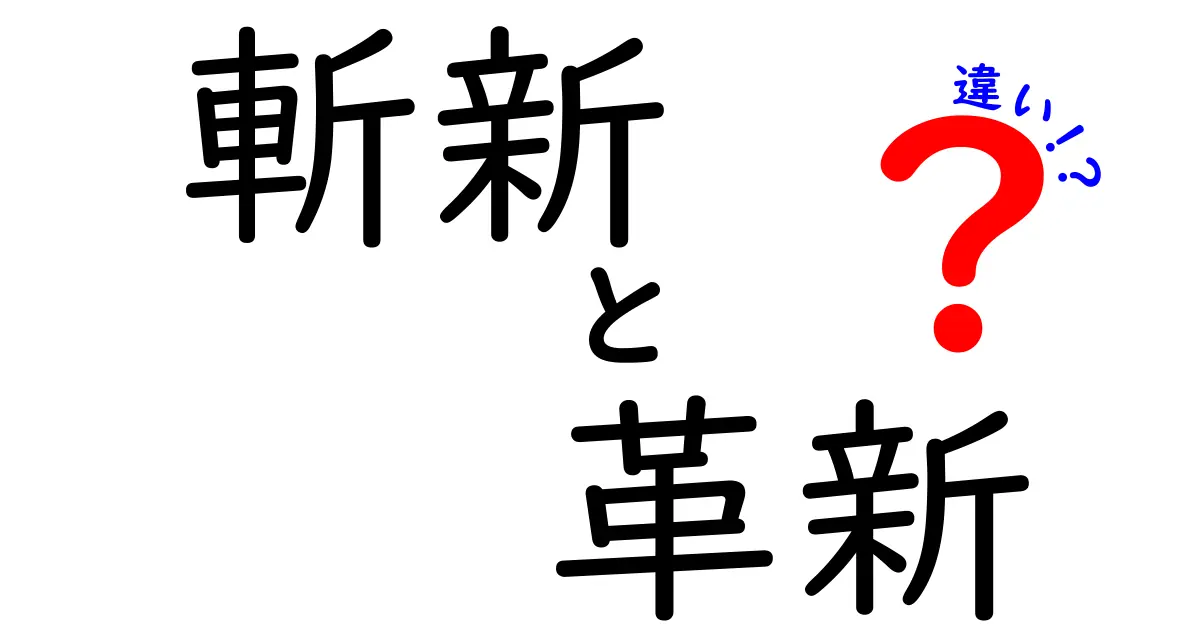

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
斬新と革新と違いの基本を知ろう
斬新とは何か、革新とは何か、違いとは何かを、まずはざっくりと捉え直します。斬新は「これまで誰も考えたことがないような新しい発想」を指すことが多く、強いインパクトを伴うことがあります。例としては、スマホを初めて持ったときの体験や、紙の地図からGPSの時代へ移行した出来事などが挙げられます。
一方で革新は「現状を保ちつつ、仕組みや技術を改良して、成果を高める変化」を指す場合が多いです。昔の機械が新しい部品で動くようになったり、ソフトウェアがより使いやすく進化したりすることを想像してください。
この二つの語は似ているようですが、使い方によって意味が変わります。違いを理解し、日常の会話やビジネスの文脈で正しく使えるようになると、伝わり方がぐんと良くなります。
本稿ではまず基本を押さえ、その後に身近な例を交え、違いをクリアにしていきます。
そして最後には小さな練習問題を用意しました。ぜひ自分の言葉で説明してみてください。強調したい点は 新しい発想の強さ と 現状の改善の積み重ね です。
日常の例で比べてみよう
日常の中で斬新と革新と違いを感じる場面を、身近な例で見ていきます。例えばスマートフォンの新機能を思い浮かべてください。たとえばある機能が新しく追加されると、それは斬新な発想の表れとして語られがちです。しかしその機能が使い勝手を大幅に良くし、操作の手間を減らすなら、それは革新の性質も持っています。
また企業の取り組みでは、業務の流れを根本から見直し、データの活用方法を変え、成果を出すための仕組みを再設計する場合を革新と呼ぶことが多いです。これに対して、ただ新しいデザインやパッケージを導入して目新しさを得るが、使い勝手が向上しない場合には斬新さだけが過剰に評価されるリスクがあります。
ここで大切なのは 実際の効果 と 長期的な価値 です。新しいアイデアが長く持続するかどうか、使い続けてもらえるかが鍵になります。次の表を見て、3つのポイントを整理してみましょう。
このような違いを理解することで、ニュース記事を読むときや会議で意見を伝えるときに、どの言葉を使えば伝わりやすいかを判断できます。
要するに、斬新は強さと衝撃、革新は実用性と持続性、違いは文脈に依存するという点を覚えておくと良いでしょう。
最後に、学んだことを自分の言葉で説明する練習をしてみてください。
例えば友だちに「この新しいアプリは斬新か革新か」と尋ねられたら、使い勝手の改善 や 実際の効果 を基準に答えると、より説得力が増します。
ねえ、斬新と革新の違いを雑談風に深掘りしてみよう。新しい発想だけが斬新ではなく、実際に使う人の生活を楽にする仕組みが革新と呼ばれる場面も多いんだ。例えば新機能のあるアプリは斬新なデザインかもしれないけれど、使い勝手が良くて作業が楽になると革新になる。さらに別の視点では、同じ言葉でも文脈次第で意味が変わることを友達と話すと、言葉の深さが見えてくる。私たちは雑談の中でこの差を体感し、説明するときのコツを掴んでいく。それが、言葉を生きたものにしていく第一歩なんだ。
次の記事: 図解で理解!已然形と連用形の違いを中学生にもわかる解説 »





















