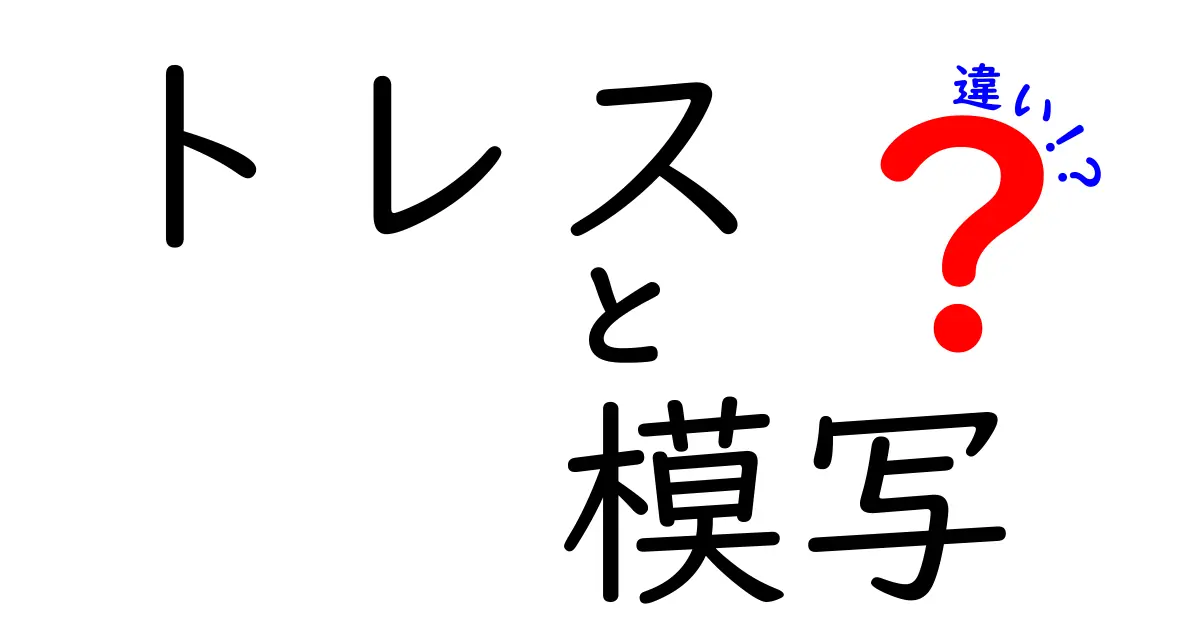

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに トレスと模写の違いを知る前提
美術の分野にはよく使われる言葉がいくつかあります。その中でもトレスと模写は似ているようで実は目的や使い方が大きく異なります。この記事では中学生にも分かる言葉で、トレスと模写の違いを整理し、具体的な場面別の使い方を紹介します。まず大事なポイントとして、オリジナル性と著作権の観点を誤解せず整理することが大切です。トレスは線の再現の技術の一つであり、模写は作品の雰囲気や技法を再現する作業です。目的が違えば選ぶ手法も変わります。
次に、練習の順序も大切です。はじめは模写で観察力と手の感覚を養い、徐々に自分の線の引き方や影の置き方を加えていくと、いつの間にか自分だけの表現が生まれてきます。この記事を読んでいるあなたが、どの場面で何を目指すべきかを判断できるよう、具体的な指標を示します。
ではさっそく、トレスと模写それぞれの基本を見ていきましょう。
トレスとは何か どんな作業か
トレスは既存の線を紙などの下敷きに写して、形を正確に再現する作業です。実際には透明な下敷きを使い、鉛筆で線を追うのが一般的です。写真や資料を見ながら、元の境界線を一点ずつ追っていくので、輪郭がほぼ同じ形になります。
この作業の良い点は、形の正確さを早く身につけられることです。難しい直線や曲線の角度を正確に扱えるようになれば、後のデッサンやキャラクター作成における基盤が安定します。
しかし気をつけたい点もあります。著作権の問題や、元の作品の特徴をあまりにもそのまま再現してしまうとオリジナル性が失われがちです。練習用の資料は自分が公開する作品と区別するルールを決め、学習の途中段階として扱うことが大切です。
さらに、デジタルの世界ではトレス用のレイヤーを使い、元の線を非破壊で並べ替えられる利点もあります。
この方法を使うと、後で調整がしやすくなり、線の太さを変える、不要な線を消すといった操作が簡単になります。ですがデジタルでの練習も同様に、学習目的をはっきりさせ、公開作品と練習用ファイルを分けて管理することが必要です。
模写とは何か どんな作業か
模写は元の作品の雰囲気や技法を観察し、線の引き方、陰影の置き方、質感の表現までを再現する練習です。ここでの狙いは単なる線の再現ではなく、作者が使っている道具の使い方まで学ぶことにあります。布の柔らかさを表現する筆致、紙の質感を感じさせる影の落とし方、ハイライトの置き方など、細部に目を向けることで観察力が養われます。
模写を続けると、元の作品の"なぜこの順序で描かれているのか"という秘密に気づくことが増え、 オリジナル性の入り口が広がります。
模写のポイントは、線をただ追うのではなく「なぜこの部分がこのように描かれているのか」を理解することです。最初は薄い線で下書きを作り、次に太さを変えて重ね描きするなど、段階を踏みながら練習すると良いでしょう。作品のスタイルが自分に合うかどうかを確かめつつ、他人の技法を自分の表現へ橋渡しする感覚を身につけることが目標です。
この過程で失敗したら、なぜうまくいかなかったのかを自問自答する習慣をつけましょう。失敗は学習の一部であり、次の一歩を作る材料です。
トレスと模写の違い 具体的なポイント
ここがこの記事の核心です。最大の違いは目的と成果物の性質にあります。トレスは元の形を正確に再現することを目的としており、線の正確さと形の忠実性が評価の中心です。模写は形だけでなく、筆致や陰影の出し方、観察力をもとにした表現力の再現を狙います。
実務での使い分けとしては、デザインの原案を作る上での基礎練習としてトレスを使い、芸術的な表現力を高めるには模写を取り入れると良いでしょう。著作権の観点では、トレスは線の再現行為自体が法的に問題になることは少ないものの、公開作品をそのまま無断で利用するのは避け、引用ルールや権利者の意図を尊重することが大切です。
もう一つの違いは学習の段階と成長の方向性です。学習目的が技術の習熟ならトレス、観察力と創造性の伸長を狙うなら模写と考えると分かりやすいです。初めてのうちはトレスから入り、基礎線を整えた後に模写へと移行するのが自然な流れです。練習の頻度と時間配分も、個人の成長速度に合わせて調整しましょう。
実例と場面別の使い分け
日常の練習シナリオを想定して、使い分けのコツを整理します。
学校の美術課題で「正確さが問われるデッサン」を求められたら、最初はトレスで形を定着させ、次に風景や静物の質感を模写で試すと良いでしょう。創作活動ではオリジナル性を高めるため、元ネタを直接トレースするのではなく、写真や絵から観察したポイントを自分の線に置き換える練習をします。
SNSなどで作品を公開する場合は、元作品の出典を明記する、あるいは参照として抑えた要素だけを再現するなど、権利者への配慮を忘れないことが重要です。
今日はトレスと模写を深掘りする雑談風の記事の一部です。普通は“違い”だけを伝えがちですが、実はこの二つは練習の順序や心構えにも大きな意味があります。トレスは元の線を正確に写す技術で、初期には形の安定を早く得るのに役立ちます。一方で模写は描き手の観察力と表現力を育て、同じ形からでも線の強弱や陰影の置き方で表情が変わることを体感させてくれます。この二つを上手に組み合わせると、技術と創造の両方を同時に高められると私は感じます。
前の記事: « 写真と風景画の違いを徹底解説|同じ“風景”でもこう変わる理由





















