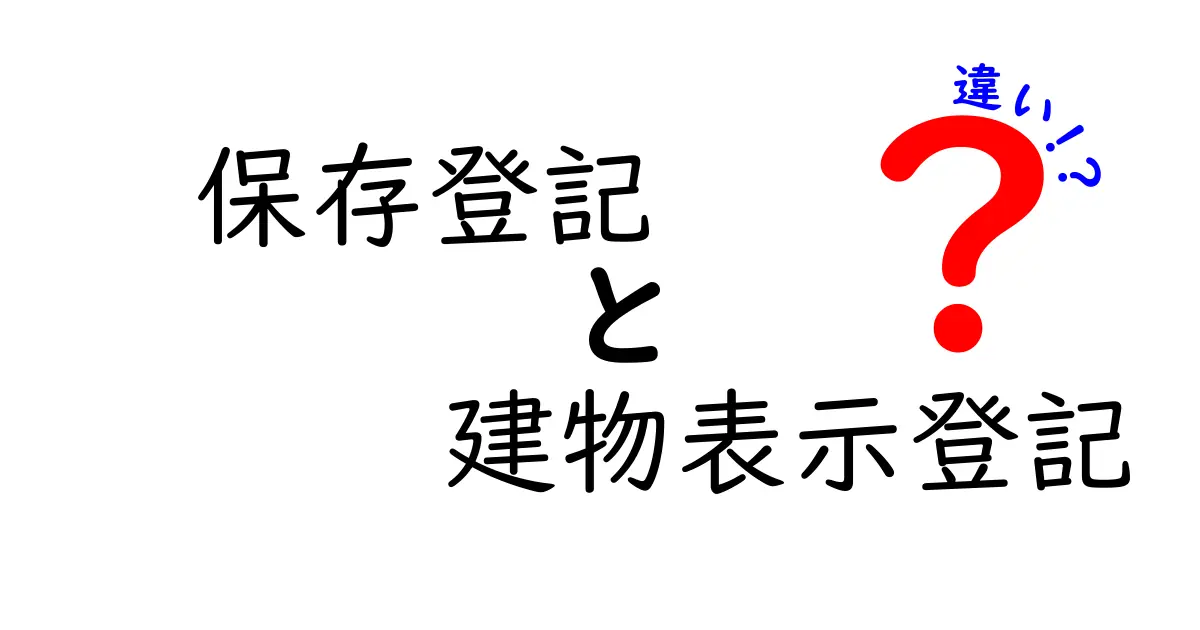

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
保存登記と建物表示登記とは何か?基本を理解しよう
建物を新しく建てるとき、不動産の管理や権利関係をしっかりさせるために、登記を行います。特に「保存登記」と「建物表示登記」はよく聞く言葉ですが、違いがわかりにくいですよね。
まず、保存登記とは、新築の建物ができたときにその建物の所有権を法的に登録することです。これにより、その建物の持ち主がだれかを公的に証明できるようになります。
一方、建物表示登記は、その建物がどこにあり、どんな構造や形をしているのかを詳しく記録する登記のことです。つまり、建物の存在や形状、所在場所の情報を登記簿に記録する役割があります。
このように保存登記は「誰の物か」を示し、建物表示登記は「どんな建物か」を示すものと覚えておくとわかりやすいでしょう。
どんな時に保存登記と建物表示登記をするのか?具体的なケースをチェック
保存登記と建物表示登記は、どちらも新築の建物が完成した時に必要になる手続きですが、その役割とタイミングに違いがあります。
保存登記は、新たに建物を持つことになった場合に必ず行われます。これにより、建物の所有者として法的に認められるからです。保存登記をしないと、建物の所有権を証明するのがむずかしくなり、売買や抵当権設定などの手続きにも支障が出ます。
建物表示登記は、新築の建物の正確な位置や構造の情報を国に報告するために行います。これは土地の利用や周辺の調和を考えるうえでも重要な情報です。
つまり、保存登記は所有権の証明に必要、建物表示登記は建物の物理的情報の登録に必要という違いがあります。
保存登記と建物表示登記の違いをわかりやすく比較!ポイントまとめ
ここまで説明した保存登記と建物表示登記を表にまとめてみましょう。
| 項目 | 保存登記 | 建物表示登記 |
|---|---|---|
| 目的 | 建物の所有権を法的に登録し証明する | 建物の位置、構造、形状などの物理的情報を登録する |
| 対象 | 建物の所有者 | 建物そのものの表示 |
| 実施タイミング | 建物完成後すぐ | 建物完成後すぐ |
| 重要性 | 所有権の証明が必要な場面で必須 | 建物の詳細情報を明確にするために必要 |
| 登記内容 | 所有者の名前、住所など | 建物の構造や床面積、場所など |
このように、保存登記と建物表示登記は目的も内容も異なりますが、どちらも新築建物の登記において欠かせない手続きです。
両方を正しく行うことで、建物の所有にまつわるトラブルを防ぎ、安心して不動産を管理できるようになります。
「建物表示登記」って聞くと、難しく感じるかもしれませんが、実は建物の“住所や形”を役所に伝えるための大切な手続きなんです。例えば、地図でいうと建物の位置や大きさを正確に記録することで、土地の使い方や周りとの調和を保つ役割もあります。意外と知られていませんが、この登記があるからこそ、不動産の情報がきちんと整理されて、安心して住める環境が整うんですね。
次の記事: 「登記簿」と「登記記録」の違いって何?わかりやすく解説します! »





















